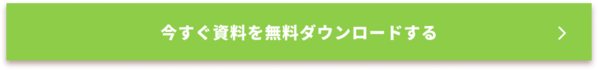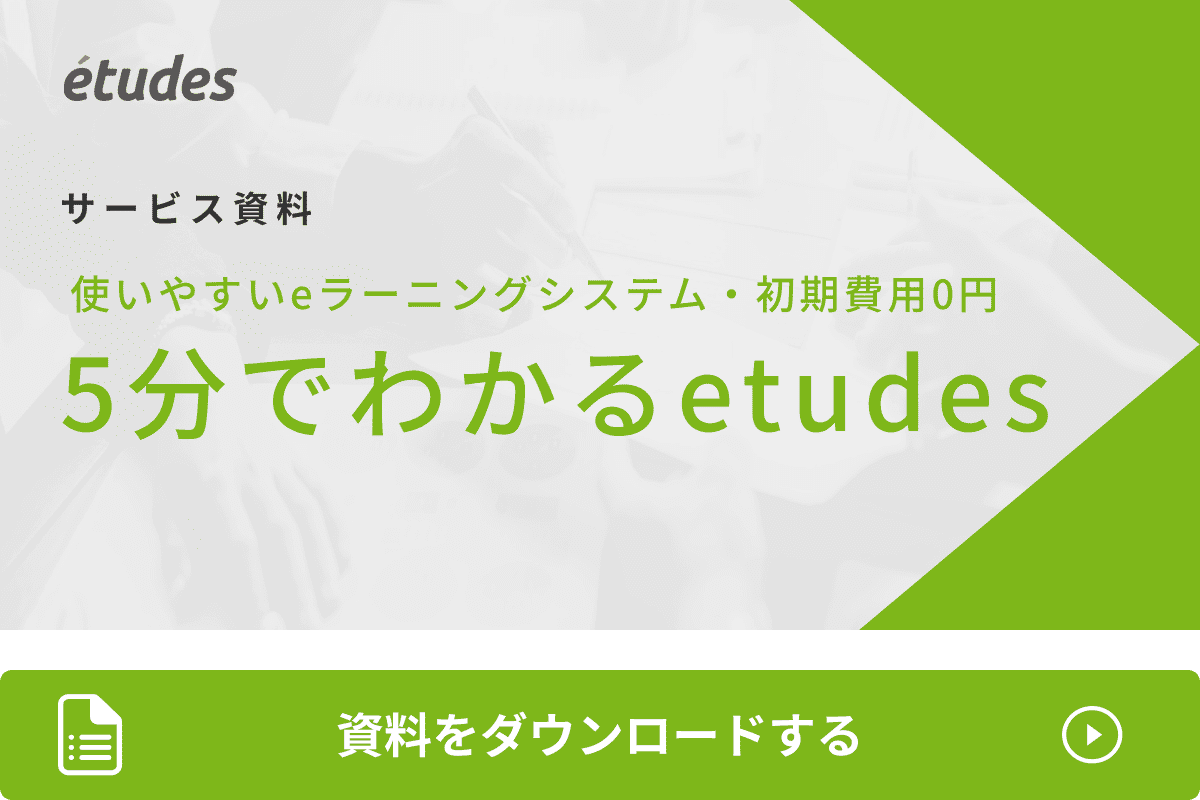eラーニングで人材育成や研修を成功に導くポイント | 企業での取り組みやシステム選定について解説
eラーニングを研修で活用する企業が増えています。eラーニングはこれまで教育機関におけるオンライン学習ツールとしても利用されてきましたが、、企業におけるeラーニングを活用した研修にも多く利用されています。本記事では企業で研修にeラーニングを導入するメリットや、eラーニングで人材育成にどうのようなメリットがあるのか、詳しく解説します。自社の研修に、eラーニングの導入を検討している場合はぜひ参考にしてください。
実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
- 1.企業でeラーニングを研修に活用する際のポイント
- 1.1.eラーニング教材
- 1.2.eラーニングシステム(LMS/学習管理システム)
- 2.eラーニングを活用した研修が注目されている理由
- 3.eラーニングを社員研修に導入するメリット
- 3.1.企業側のメリット
- 3.2.受講者・社員側のメリット
- 4.eラーニングを社員研修に導入するデメリット
- 4.1.企業側のデメリット
- 4.2.受講者・社員側のデメリット
- 5.eラーニングと集合研修の費用の比較
- 6.eラーニングを研修に導入して期待できる効果
- 7.社員研修向けeラーニング・LMSの選び方
- 7.1.既存コンテンツの充実度で選ぶ
- 7.2.自社教材の活用がしやすいかで選ぶ
- 7.3.受講管理機能の充実度で選ぶ
- 7.4.コストに無駄がないかで選ぶ
- 7.5.操作のしやすさで選ぶ
- 8.eラーニングを活用した研修で社員教育を成功させるポイント
- 8.1.eラーニングによる研修を導入する目的を明確にする
- 8.2.他の研修方法と併用したブレンディッドラーニングを導入する
- 8.3.eラーニングを浸透させる施策を行う
- 8.4.eラーニング教材作成の支援を受けるのも一つの手
- 9.eラーニングを活用した研修内容の一例
- 10.eラーニング研修のさらなる活用方法
- 10.1.社外・代理店研修
- 10.2.店舗アルバイト研修
- 10.3.ナレッジマネジメント
- 11.eラーニングを活用した研修ならLMSの「etudes」
- 11.1.ニーズの多い研修テーマのeラーニングセットプランを用意
- 11.2.必要な分だけ自由に選べる教材
- 11.3.自社での研修教材作成もサポート
- 11.4.eラーニング受け放題プラン「etudesPlus」も
- 12.etudesの導入事例
- 13.まとめ
eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
企業でeラーニングを研修に活用する際のポイント
自社でeラーニングを活用した人材育成や研修を実施するためには、「eラーニング教材」と「eラーニングシステム(LMS/学習管理システム)の二つの観点でサービスやシステムを選定することがおすすめです。また、効果的なeラーニング研修を実現するためには、eラーニング教材の質や内容を吟味するだけでなく、最適なLMSを選定し運用することが求められます。
ここでは、eラーニング教材とLMSについて具体的に解説します。
そもそもeラーニングとは?という基本情報については以下の記事で詳しく紹介しています。
『eラーニングとは?意味やメリット・デメリットについて簡単に解説』
eラーニング教材
eラーニングの受講者に対して提供する学習資料や学習教材のことをeラーニング教材といいます。
種類や形式はさまざまで、
- テキスト教材
- スライド教材
- 動画教材
などがあります。
その中でも近年主流となっているものが、情報量が多く、効率的な学習効果が期待できる動画教材です。
eラーニング教材は、サーバー上に保存しておくことで管理者が簡単に教材を更新したり管理したりできるだけでなく、受講者は各自のデバイスから個人のペースで学習できるため、利便性が高いという特徴があります。
eラーニングシステム(LMS/学習管理システム)
eラーニングシステム「LMS」とは、Learning Management Systemの略称であり、eラーニングによるオンライン学習に必要な機能や、ブレンディッドラーニングなどに活用できる研修管理機能が搭載されたツールのことです。さまざまな提供ベンダーがあるため、標準装備されている機能はツールごとに異なります。
eラーニングシステムの主な機能として、以下が挙げられます。
- コンテンツ管理機能…動画や資料などのコンテンツを登録・管理
- 学習者管理機能…受講者の情報を一元管理し、進捗状況を把握
- テスト/アンケート機能…理解度を測るテストや、アンケート集計機能
- 受講履歴管理機能…受講状況や成績を自動で記録・集計
- 通知機能…メールやプッシュ通知で受講を促す連絡が可能
このように、eラーニングシステムには学習コンテンツと受講者の一元管理に加え、テストや進捗状況の把握など、効果的な研修を行う機能が備わっています。汎用性が高いeラーニングシステムを導入すれば社員育成や研修運営にかかるさまざまな工数を大幅に削減することができます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングを活用した研修が注目されている理由
eラーニングが注目されて多くの企業で導入されるようになった理由として、主に「働き方の多様化」や「DX化の取り組み」などが挙げられます。
時代の変化により、近年では働く場所を限定しない勤務スタイルが一般化しつつあります。
誰もがオフィスに通っているわけではない状況が当たり前となった現代において、社員研修を均等に受けさせるために、eラーニングは有効な手段となりました。
また、社内のアナログな業務を見直してデジタル化する「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」も、eラーニング導入の推進を後押ししています。
しかし、オンライン研修そのものに対して「本当に学習効果があるのか」「離れている社員の研修の進捗はどのように管理するのか」といった疑問を抱く方は少なくありません。
これらの課題を解決し、eラーニングによる研修を効果的に実施するためには、eラーニング教材の質を高め、LMSを導入することが重要といえます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングを社員研修に導入するメリット
eラーニングを社員研修に導入するメリットについて企業側と受講者・社員側の双方の視点から、具体的なメリットを紹介します。
企業側のメリット
企業側の主なメリットとして、コストや手間の削減が挙げられます。
従来の集合研修は、研修会場を用意し講師を手配して行わなければならなかったため、会場費や講師への謝礼が必要でした。また、資料の印刷や配布が必須で、紙代やインク代といった面でのコストも考慮しなければなりませんでした。
しかし、eラーニングの場合はインターネット環境が整っていればオンラインで受講でき、資料や教材もWeb上で確認ができます。
これまでの集合型研修の運営で負担していた費用と管理工数が、eラーニングの導入により大幅に削減できます。さらに、eラーニング学習と集合型研修を組み合わせたブレンディッドラーニングも、システムを活用すれば簡単に行えるため、限られた社員研修の時間を有効活用し、成果を最大化することができます。
例えば、事前に各自がeラーニングで学習した知識を、集合研修やディスカッションの場でアウトプットする、などの形で研修を進めていくと効果的です。
eラーニングを活用することで、受講者の自発的な学習をより促進でき、多様化が進む現代に必要なスキルを持った人材育成が期待できるでしょう。
受講者・社員側のメリット
受講者・社員側の主なメリットとして、特定の場所に集まることなく自分のペースで学習できることが挙げられます。集合研修の場合、実務の時間を調整して研修に参加しなければならず、対面式で実施される場合は研修会場に移動する必要もあります。
研修中は業務を進めることができないため、予定の調整が難しい社員は参加できない、参加しても研修に集中できないなどの課題がありました。
eラーニングの場合は、受講者が集まる必要がなく、仕事の合間や空いている時間を活用して学習することが可能です。
録画などを活用すれば反復学習もしやすく、個々の理解度が異なる場合でも各自のスキルレベルに応じた学習が進めやすくなります。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングを社員研修に導入するデメリット
一方、eラーニングを社員研修に導入するデメリットも存在します。企業側と受講者・社員側、それぞれのデメリットを理解していなければ、効果的かつ理想的なeラーニングによる研修を実現できない可能性があります。
ここでは、具体的なデメリットについて解説します。eラーニングの導入を検討している際は、ぜひ参考にしてください。
企業側のデメリット
企業側の主なデメリットとして、集合研修と比べると参加に対する強制力が弱いことが挙げられます。上述した通り、eラーニングによる研修は研修会場などの準備が不要になり、受講者は時間や場所に縛られることなく学習を進めることが可能です。
しかし、研修の受講は対象者の学習意欲にゆだねられるため、受講者によっては実務を優先し、eラーニング受講の優先順位を下げてしまう可能性があります。
また、動画を取り入れた学習や研修の場合は、長時間動画を視聴する必要があり、受講者の集中力が続かずモチベーションの維持が難しいという問題もあります。
上記のようなデメリットを解決するためには、学習管理機能を活用して学習状況を確認しながら受講を促進したり、社員にヒアリングしてフィードバックやアドバイスをしたりといった工夫が必要です。
受講者・社員側のデメリット
受講者・社員側の主なデメリットとして、実技を伴う研修が実施しづらいことが挙げられます。eラーニングによる研修は、集合研修などとは違い、講師と受講者がリアルタイムで対面して行うわけではありません。そのため、内容によっては実技や演習には向かない場合があります。
実技や演習が必要な内容を学習する場合には、事前学習をeラーニングで行い、得た知識を集合研修でアウトプットするブレンディッドラーニングの手法を採用することでデメリットをカバーできます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングと集合研修の費用の比較
eラーニング研修のさまざまなメリットをご紹介してきましたが、中でも大きなメリットはコスト面です。しかし、eラーニングで研修を行うことで、どれだけコストが削減できるのか、具体的にはイメージしにくいのではないでしょうか。
ここでは、eラーニングと集合研修の料金シミュレーションの比較を、400人規模の研修を実施した場合の一例としてご紹介します。
eラーニング | 集合研修 | |
|---|---|---|
受講人数 | 400人 | 400人 |
スケジュール | なし | 1泊2日 |
宿泊費用 | なし | 6,000円×400人=2,400,000円 |
食事費用 | なし | 4,000円×400人=1,600,000円 |
交通費 | なし | 2,000円×400人=800,000円 |
会場費 | なし | 300,000円×10回=3,000,000円 |
教材費 | 1ヶ月1500円×400人=60万円 | 3,000円×400人=1,200,000円 |
合計 | 60万円 | 900万円 |
集合研修はコストがかさむため、必要な回数の研修実施ができないという悩みをお持ちの企業も多いでしょう。そうした場合にもeラーニングの導入はおすすめです。
eラーニングの一般的な料金体系や相場について詳しく知りたい方は『eラーニングの開発費用、利用料金とは?料金システムと相場を解説』をご覧ください。クラウド型とオンプレミス型などの運用形態別の料金相場も紹介しています。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングを研修に導入して期待できる効果
ここまでは、eラーニングによる研修のメリット・デメリット、従来の研修との費用比較について詳しく解説しました。
eラーニングによる研修で、コストが削減できることは理解できたものの、eラーニングならではの学習の効果については、まだ具体的なイメージが湧かないかもしれません。
ここからは、eラーニングによって研修がどのように変わるのか、導入による効果についてご紹介いたします。
- マイクロラーニングができる
- ブレンディッドラーニングで研修効果アップ
- 長期的な研修やリスキリングが実施できる
- eラーニング研修の成果を人事評価に活かせる
一つずつ、詳しくみていきましょう。
マイクロラーニングができる
マイクロラーニングとは、短い視聴時間の動画教材で勉強する、新しい学習方法のことです。
動画教材は、スマホやタブレットで視聴できることから、通勤中などの隙間時間を有効活用して学ぶことができます。パソコン以外でもeラーニング教材を視聴できる「マルチデバイス」対応のLMSを選択することにより、eラーニング研修でマイクロラーニングを実施することが可能です。
マイクロラーニングに利用される動画は5分以内の学習コンテンツなので、受講者の集中力が持続しやすく、スキルの定着に効果があるとされています。
マイクロラーニングについて詳しく知りたい方は「マイクロラーニングとは?メリットやコンテンツ作りのコツを解説」もご覧ください。
マイクロラーニングの効果についてご紹介しています。
ブレンディッドラーニングで研修効果アップ
前述のデメリットの項目で少し触れた「ブレンディッドラーニング」による効果的な学習も、eラーニング研修の導入で実現できます。
ブレンディッドラーニングとは、集合研修とeラーニング研修を組み合わせた研修方法です。例えば、ビジネスに必要な思考法についてのeラーニングを個人で受講し、基礎的な知識を習得した上で集合研修に参加し、グループディスカッションや演習問題を行って実践力をつける、といった方法です。
ブレンディッドラーニングにより、集合研修とeラーニング研修それぞれの弱点を補うことができます。
ブレンディッドラーニングについて詳しく知りたい方は「ブレンディッドラーニングとは?人材育成を効率化する方法について」もご覧ください。
研修の進め方や実施のポイントについて解説しています。
長期的な人材育成やリスキリングが実施しやすい
LMSには、自社オリジナルのeラーニング教材や、購入したeラーニング教材を搭載できるため、豊富な教材の中から受講者が、テーマに応じて自由に選ぶことができます。また、管理者側から必要な教材を学習者に向けて配信することもできます。
eラーニングシステムのこうした機能を活用すると、個人の課題に応じた学習(アダプティブラーニング)が進めやすくなり、長期的な人材育成が可能になります。
近年注目が集まる学び直し施策「リスキリング」を成功させた企業の多くも、eラーニングとオンライン学習プラットフォームを活用していました。
eラーニングによるリスキリングについて詳しく知りたい方は「6社のリスキリング事例を紹介!DX時代の人材育成のポイントとは」もご覧ください。
リスキリングを社内施策として成功させた企業の事例を複数紹介しています。
eラーニング研修の成果を人事評価に活かせる
従来の集合研修では、研修後のレポートやテストによって大まかに理解度は確認できても、研修に対しての取り組みや結果など、一人ひとりの数値データについては、集計する手間が膨大なため、細かく把握することが困難でした。
LMSを用いたeラーニング研修なら、社員一人ひとりの研修の成果を数値データとして正確にシステム上で把握することができます。そのため、eラーニングへの取り組みを人事評価の項目に組み込んだり、eラーニングの成績を元に、よりスキルを活かせる部署への異動を検討したりすることも可能です。
学習の成果が正当に評価される研修を行うことで、社員の学ぶ意欲の向上も期待できるでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
社員研修向けeラーニング・LMSの選び方

ここからは、研修に活用するeラーニングを選ぶ際に、重要となるポイントをご紹介していきます。
- 既存コンテンツの充実度で選ぶ
- 自社教材の活用がしやすいかで選ぶ
- 受講管理機能の充実度で選ぶ
- コストに無駄がないかで選ぶ
- 操作のしやすさで選ぶ
一つずつ、解説していきます。
既存コンテンツの充実度で選ぶ
eラーニング教材は一から作成することもできますが、実用までに時間がかかってしまいます。導入後、すぐに研修を始めたいという場合は、LMSのベンダーがパッケージで販売しているeラーニング教材を利用しましょう。 その場合、自社のニーズとマッチしたものを選ぶことが大切です。教材の内容と充実度に注目してLMSを比較するといいでしょう。
自社教材の活用がしやすいかで選ぶ
eラーニング教材の作成にあたっては、これまで自社で使ってきた教材をベースとして利用したい場合があるかもしれません。その際には、自社教材を有効活用しながらeラーニングとして配信できるかどうかという点で、システムを選ぶこともできます。
パワーポイントによる教材データをeラーニングに組み込んだり、動画データをそのままオンラインで配信できる機能を持つeラーニングシステムもあります。
ただし、活用できるかどうかは、利用するサービスによって異なります。 使用が必須の自社教材データがある場合は、事前に相談しておきましょう。
受講管理機能の充実度で選ぶ
eラーニングによる研修の導入と運用を成功させるには、効果測定がしやすく学習の管理を効率化できる機能が、どの程度搭載されているかという点にも注目しましょう。 あると便利な機能として、
- オンライン研修だけではなく集合研修の申し込み管理や出欠管理もできる
- 大規模なアカウント数に対応できる
- 進捗状況に合わせたメールを自動配信できる
などが挙げられます。
また、管理者側の使い勝手だけで利用するeラーニングシステムを決めるのでなく、受講者側にとっても使いやすいかどうかを忘れずに確認しましょう。
コストに無駄がないかで選ぶ
先述のとおりeラーニング研修は、コスト削減につながりますが、サービスの導入や運用には費用がかかります。
自社が求めるeラーニングに対して、オーバースペックな機能を搭載してしまうと、無駄なコストが発生します。
コストを削減するためにeラーニングを選んだのに、使用しない機能やプランによって余計なコストが発生してしまったのでは本末転倒です。
サービスの利用を検討する際は、無駄なコストを省くため、費用相場の調査や運用コストの予測を算出しておくことをおすすめします。
操作のしやすさで選ぶ
研修のためのeラーニングシステムを選ぶ際には、操作のしやすさにも注目しましょう。
受講者にとって、「表示がわかりづらい」「直感的に操作ができない」といったストレスは、たとえわずかなものであっても学習の妨げとなってしまいます。 全社員向けの研修にeラーニングを導入するのなら、PC操作が苦手な方でも感覚的に操作できるeラーニングシステムが望ましいでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングを活用した研修で社員教育を成功させるポイント
eラーニングを活用して社内教育を成功させるポイントは、主に4つ挙げられます。
- eラーニングによる研修を導入する目的を明確にする
- 他の研修方法と併用する
- 浸透させる施策を行う
- eラーニング教材作成の支援を受けるのも一つの手
それぞれのポイントを、詳しく見ていきましょう。
eラーニングによる研修を導入する目的を明確にする
eラーニングを研修に導入する際、まずは導入目的を明確にすることが大切です。
まず、自社で現在抱えている課題を具体的に把握し、その課題を解決するために必要な研修内容やテーマを明らかにしましょう。さらに、eラーニングの活用による研修の実施が、自社にどのような効果をもたらすのかを検討します。
eラーニングシステムには教材が豊富に揃っていますが、目的を把握しないまま導入すると、eラーニング受講が形骸化し、結果として誰も受講しないという事態にもなりかねません。研修としてしっかりと取り組むためには、まず導入目的と必要な研修内容を明確にした上で、社内での活用方法や運用方法を検討することをおすすめします。
他の研修方法と併用したブレンディッドラーニングを導入する
eラーニングによる学習だけではなく、集合研修といった他の形式の研修とeラーニングを併用するブレンディッドラーニングを実施することもポイントです。
eラーニング受講だけで研修を完結させてしまうと、実技や演習の学習が不十分になる恐れがあります。個々が得た知識やスキルをアウトプットする場が不足するため、eラーニングで学んだ知識の実務への活用が難しくなり、学習継続に対する受講者のモチベーションの維持が困難になります。そのようなデメリットを解消できるように、eラーニングによる学習と他の研修を組み合わせながら、効率的にアプローチしていくことが重要です。
eラーニングを浸透させる施策を行う
社内研修を成功させるには、eラーニングを活用した研修を社内に浸透させる施策を講じることが大切です。
企業側がeラーニングの効果を期待し、導入したとしても、社内に浸透していなければ成果を上げることはできません。また、受講者に対して自由に学習できるとただ伝えるだけでは、社員の積極的な活用にはつながりにくいでしょう。
eラーニングを導入する場合は、継続的に学習しやすい環境整備や、eラーニングへの取り組みを人事評価に組み込むといった組織的な取り組みも、成功のポイントになります。
eラーニングで学んだことを積極的にアウトプットするために、集合研修と組み合わせたブレンディッドラーニングを実施したり、得た知識やスキルを共有する場を設けることもおすすめです。各自がeラーニングにどの様に取り組み、実務に活かしているのか、受講者同士でコミュニケーションを図れる機会を用意するのも効果的です。
eラーニング教材作成の支援を受けるのも一つの手
企業によっては、既存のeラーニング教材のみでは社員育成に必要な教材をまかなえない場合もあるでしょう。eラーニング教材の内製が難しく、作成するためのリソースを割けない場合も少なくありません。
そのような課題を抱えている場合は、eラーニング教材の作成を支援している企業などへ依頼することをおすすめします。
研修などを扱っているプロの企業に依頼すれば、自社に合ったeラーニング教材の作成支援が受けられます。既存のeラーニング教材と組み合わせて、自社独自の教材を制作、導入することにより、受講者の成長を効率的に促進することができます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングを活用した研修内容の一例
ここでは、アルーが提供しているeラーニング教材のカリキュラム例を階層別とテーマ別に分けてご紹介します。研修に活用することでより効果的に人材育成を進めることができます。
階層別研修
階層別研修で使えるeラーニング教材の例を、
- 新人研修
- 中堅社員向け研修
- 管理職向け研修
の3つに分けて紹介します。
新人研修
新人研修のeラーニング教材は、社会人としての心構えや、報告・連絡・相談などの基本的な内容を学習することができます。
新人研修の内容例は、以下の表にまとめました。
テーマ | 内容 | 時間 |
学生から社会人への意識転換 | 社会人として求められる心構えと行動を学びます。 | 約110分 |
自己改善サイクル | 経験学習サイクルをベースに、自分自身をリードしながら成長する方法を学びます。 | 約120分 |
相手の期待に応える | 仕事の成果は、相手の期待に応えているかで決まります。相手の期待を自ら適切に捉え、応えるための基本的な仕事の進め方を学びます。 | 約105分 |
段取り | 与えられた一つひとつの仕事について、納期までに抜けモレなく遂行するための計画の立て方を学びます。 | 約110~140分 |
報告連絡相談 | 適切な報告・連絡・相談による業務遂行・振り返り・改善の方法を学びます。 | 約160分 |
他社の受容・尊重 | 他者を受容・尊重することで、職場メンバーと協力しながら仕事を進めていくための方法を学びます。 | 約95分 |
ロジカルシンキング | 物事を緻密かつスピーディに考え、わかりやすく伝えるための基本的な思考方法を学びます。 | 約160分 |
ビジネスマナー | 社会人として基本的・汎用的なマナーを学びます。 | 約55分 |
ビジネス文書 | ビジネス文書を書く上での基本原則を学びます。 | 約105分 |
仕事の進め方 | 「相手の期待に応える」「段取り」「報告・連絡・相談」「振り返り・改善」「ビジネス文書」について総合的にトレーニングします。 | 約195~285分 |
新入社員・内定者向けスタンダードプランは、以下のリンクからカリキュラムを一覧でご確認いただけます。
中堅社員向け研修
中堅社員に欠かせないスキルや部下育成のために必要なスキルを学習できるeラーニング教材は、以下の表の通りです。
テーマ | 内容 | 時間 |
志の獲得 | 自分にとっての仕事の意味や目的を見つめ直し、仕事を通じて実現したい「志」を明確にすることを目指します。 | 約150分 |
自己マスタリー | 自分の力量や成果など、現実を直視しつつも常に自分の描く理想の姿に向けて高い目標を掲げて、学び続けるための自分の成長戦略を描く方法を学びます。 | 約100分 |
業務本来の目的の達成 | 業務本来の目的達成につながるゴール設定の仕方を学びます。 | 約60分 |
選択肢の案出・決定 | 複雑性の高い仕事のプラン(計画)の立て方を学びます。 | 約160分 |
担当業務の改善 | 継続的な目標達成につながる、戦略的な担当業務実行の方法を学びます。 | 約105分 |
ネットワーキング | 本コースでは、「社内で自分のことを応援してくれる人を増やす」ためのネットワーキングについて学びます。 | 約70分 |
メンタリング | 経験の浅いメンバーへの簡易な実務指導を担いつつ、悩みや不安の相談に乗るなど心理的にも支えるために必要な心構えとスキルを学びます。 | 約75分 |
ロジカルシンキング | 物事を緻密かつスピーディに考え、わかりやすく伝えるための基本的な思考方法を学びます。 | 約160分 |
キャリアの自己決定 | 「人とのつながり」、「自分とのつながり」、「会社とのつながり」3つのつながりから、自らのキャリアを自己決定するための手法を学びます。 | 約135分 |
キャリアの可能性を拡げる | 中長期的視点から自身のキャリアを捉え、若手社員に必要なキャリアデザイン力を伸ばすためのポイントを学びます。 | 約90分 |
詳しくは、以下のページからご確認いただけます。
中堅社員向けeラーニング
管理職向け研修
管理職向け研修のeラーニング教材の内容例は、以下のようなものが挙げられます。
テーマ | 内容 | 時間 |
プレイヤーからマネジャーへの脱却 | 課長層としての役割を理解し、パフォーマンスを発揮していくための認知力・対応力を学びます。 | 約135分 |
理感一致のリーダーシップ | 「自分らしさ・組織らしさ」を起点として、組織からの期待に応えるためのあり方を学びます。 | 約155分 |
部署の目標を設定する | 会社全体の戦略を理解した上で、部署の現状と統合した目標を立てるポイントを学ぶことができます。 | 約100分 |
メンバーの目標を設定する | メンバーの中長期的キャリア形成を見据えた目標設定のポイントを学びます。 | 約100分 |
目標達成のための計画を策定する | 自部署の目標達成に必要な要素を構造化し、ストーリーをKPIに落とし込み業務分担を決めるポイントを学びます。 | 約120分 |
目標設定のための協働関係を構築する | チームを見立てることで協働関係を引き出す土台を作り出すポイントを学びます。 | 約80分 |
組織運営のモニタリングとフィードバックをする | KPIに基づきモニタリングと介入を行い、必要に応じてKPIを見直し、協働関係を阻害する要因を見極め、改善することでメンバーの成長機会を継続的に支援するポイントを学びます。 | 約100分 |
人事考課の基本 目標設定編 | 人事考課に必要な目標設定(目標提示、計画策定、合意形成)を学ぶことができます。 | 約100分 |
人事考課の基本 観察・介入・実行支援編 | 人事考課に必要な観察・介入・実行支援を学ぶことができます。 | 約95分 |
人事考課の基本 評価編 | 人事考課に必要な評価 (評価の方法、伝え方)を学ぶことができます。 | 約70分 |
詳しくは、以下のページから一覧でご確認いただけます。
中堅社員向けeラーニング
テーマ別研修
テーマ別研修は、企業の課題や社員の課題に合わせて実施する研修です。eラーニングでも、ハラスメント研修やメンタルヘルス研修などの研修が実施できます。
ハラスメント研修
eラーニングであれば、各社員の階層によってハラスメント研修の内容を変更することも容易です。例えば、管理職はどのような行動がハラスメントにあたるのかを学び、新入社員はハラスメントを見つけた、あるいはハラスメントに遭った場合はどのように対応すれば良いのかを学ぶなど、各階層に合わせた内容での学習が可能です。
ハラスメント研修については、以下のページから確認できます。
コンプライアンス|LMS・クラウド型eラーニングシステム「etudes(エチュード)」
メンタルヘルス研修
メンタルヘルス研修も、eラーニングで学習しやすいテーマです。ストレスのセルフチェックを行い、ストレスに関する知識を習得することにより、現在のストレス状態に気付くことが可能です。また、自分が受けているストレスに対して、状態に合った対処法を実施する力も身につけることができます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニング研修のさらなる活用方法
ここまでは、主に社内研修におけるeラーニングの活用方法をご紹介しました。
しかし、eラーニングは社内だけではなく社外向けの研修にも活用でき、eラーニングシステムにナレッジ(事例やノウハウなど)が蓄積されることによる新たな利用価値も生まれています。
eラーニング研修のさらなる活用方法を、詳しく解説します。
社外・代理店研修
eラーニングは、社外の代理店や販売パートナー向けの研修にも活用できます。例えば、新製品説明会や販売手順の研修などを、動画や資料をアップロードしてオンラインで実施するといった方法です。
代理店担当者は遠方に点在していることが多いですが、eラーニング研修なら一ヶ所に集まる必要がなくなるというメリットがあります。また、動画や資料は繰り返し視聴できるため、受講者の理解が深まります。さらに、誰がどの程度学習したかを本社で一元的に管理できます。
もちろん、教材の内容を変更したり更新したりするのもeラーニングシステムを活用すれば、簡単に行えます。
店舗アルバイト研修
eラーニングは、店舗でアルバイトとして勤務する従業員の研修にも活用できます。
アルバイト従業員は入れ替わりが激しく、対面での研修を行うのが難しい場合があります。しかしeラーニングであれば、動画や資料を見ながら自身のペースで学習できるため、効率的に知識を身につけることができます。
店舗業務の手順や規則、サービス理念など、店舗で働く上で必須の知識がスマホやタブレットで学べれば、研修の受講率アップにもつながるでしょう。
アルバイト研修へのeラーニング活用法は以下の記事で詳しく解説しています。
『アルバイト研修にはeラーニングを導入すべき!eラーニングによる研修の流れをご紹介』
ナレッジマネジメント
ナレッジマネジメントとは、社内のノウハウや業務の知識(=ナレッジ)をデータ化し、誰もがアクセスできるデータベースにまとめる施策を指します。
研修のeラーニング化は、従業員のスキル向上や工数削減にとどまらず、ナレッジマネジメントの手段としても活用できます。
社内で蓄積された知見や技術ノウハウを、動画やeラーニングコンテンツとして体系化し、全社で共有することが可能です。これにより、以下のようなメリットが期待できます。
- 優秀な人材の退職による知識の流出を防げる
- ベテラン社員の暗黙知を明文化して継承できる
- 部門や拠点を超えた知識の水平展開ができる
- 新入社員の早期戦力化を促進できる
社内で知識の偏りが課題となっている場合は、ぜひeラーニングシステムとeラーニング研修の導入を検討しましょう。
ナレッジマネジメントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
『ナレッジマネジメントとは?意味・考え方から導入のポイントまで解説』
eラーニングを活用した研修ならLMSの「etudes」
eラーニングを活用した研修の導入を前向きに検討されている方へ、人材育成会社が開発したLMS「etudes(エチュード)」をご紹介いたします。
etudesは、「アルー株式会社」が長年培ってきた人材育成のノウハウを結集させて開発したクラウド型eラーニングシステムです。
豊富な教材、すべての利用者にやさしいUI/UX、そして充実した教材作成サポートが高く評価され多くの企業に選ばれています。
次の項から、etudesならではの強みと特徴をご紹介していきます。
etudesの製品紹介を詳しく知りたい方は『製品紹介資料』をダウンロードください。etudesの特徴やデモ画面、費用についてご紹介しています。
ニーズの多い研修テーマのeラーニングセットプランを用意
etudesの特徴の一つは、アルー株式会社が開発した多彩なeラーニング教材を利用できるという点です。役職や階層に応じた研修テーマだけでなく、スキルテーマ別に、ビジネスを成功させるための思考術、コンプライアンスに至るまで豊富な教材を取り揃えています。
特にニーズの多い研修は、複数の教材を組み合わせてセットにした「セットプラン」として提供しています。多種多様な教材から一つずつ選ばなくてもこのセットプランを導入すれば、充実した「新入社員研修」や「管理職向け研修」が行えるでしょう。
etudesのセットプランについて詳しくは『eラーニング教材一覧(セットプラン)』をご覧ください。
必要な分だけ自由に選べる教材
セットプランだけではなく、教材を自由に選んで組み合わせることももちろん可能です。
etudesで配信可能なアルーの教材は、以下のようなテーマ別にカテゴライズされています。
- マネジメント・部下育成
- 思考力・コンセプチュアル
- ビジネススキル
- 考え方・価値観
- 関係性構築・チームワーク
- OJT
- グローバル
- アカウンティング
この中に、自社の研修にぜひ取り入れたい内容がありましたら、etudesの導入を検討してみましょう。
etudesのテーマ別eラーニング教材について詳しくは『eラーニング教材一覧(テーマ別)』をご覧ください。
自社での研修教材作成もサポート
etudesの運営元であるアルー株式会社では、自社オリジナルのeラーニング教材作成のサポートも行っています。
自社のノウハウを詰め込んだ研修の実施を希望する際は、独自の教材が必要となります。しかし、eラーニング教材を一から自社で開発をするには、手間や時間が必要です。
アルー株式会社は、eラーニングに精通したコンサルタントが丁寧なヒアリングで課題を確認し、ベストな教材の作成方法をご提案します。
etudesのオリジナル教材作成について詳しくは『オリジナル教材を作成』をご覧ください。
eラーニング受け放題プラン「etudesPlus」も
アルー株式会社では、豊富なeラーニング教材がすべて搭載された受け放題のサービス「etudesPlus」もご用意しております。
「今すぐにeラーニングでの研修を開始したい」「人材育成の実績に基づいた質の高い教材を利用したい」という二つの要望を同時に叶えられる、定額制eラーニング受け放題プランです。
動画コンテンツ約300本、演習教材約600本という豊富な教材を、100種類以上のカリキュラムとしてまとめて提供しています。
複数の教材からどれを選べば良いのかが一目でわかる、レコメンド機能も搭載されているため、受け放題ならではの効果を最大限に引き出すことができます。
詳しくは、etudesPlusの詳細ページをご覧ください。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
etudesの導入事例
etudesはLMSとして、多くの企業様に導入いただいています。
実際に導入いただいた企業様の中から、「株式会社メガネトップ様」の事例をご紹介します。
- 株式会社メガネトップ様
「眼鏡市場」を運営する国内眼鏡市場No.1メーカーであるメガネトップ様では、社員教育の一環としてのeラーニング研修にetudesを選択されました。全ての従業員が、どの組織でも通用するスキルセットを持つことを目標にeラーニング研修を実施し、「自ら学ぶ風土」を醸成されました。etudesのユーザビリティの高さは、受講者・管理者ともに高評価をいただいています。
その他の企業様のケースについては、etudesの導入事例ページからご覧ください。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
今回は、eラーニングで研修を行う方法とそのメリット、eラーニングによって実現する研修方法などを詳しく解説しました。
eラーニング研修を効果的に実施するには、現在どのような課題を社内で抱えているのか、eラーニングを導入することで何を解決したいのか、といった状況を明確にすることが大切です。
eラーニングによる研修の効果を最大限に引き出すためには、LMS(学習管理システム)も合わせて導入しましょう。
どのLMS・eラーニングシステムが自社に最適か迷った際は、さまざまなニーズに対応可能なクラウド型LMS「etudes」をご検討ください。