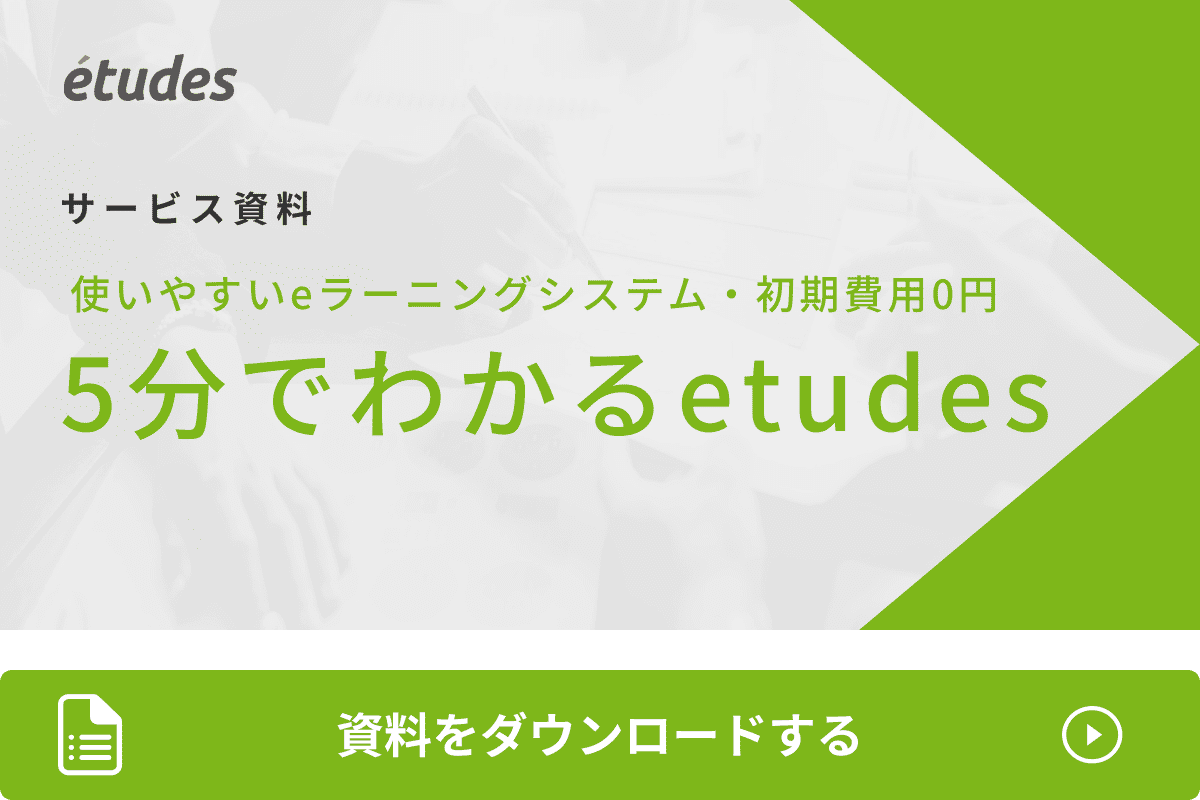マイクロラーニングとは?メリットやコンテンツ作りのコツを解説
近年、社員のスキルアップのため、eラーニングによる研修が一般化しています。eラーニングなら、隙間時間に学習ができる「マイクロラーニング」を取り入れることができます。この記事ではマイクロラーニングとは何か、導入のメリットや研修に活用するためのポイントを詳しく解説します。
実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
- 1.マイクロラーニングとは?
- 2.マイクロラーニングが生まれた技術的背景
- 2.1.スマートフォンの普及
- 2.2.クラウド型LMSの普及
- 2.3.データベースの性能向上
- 3.マイクロラーニングが取り入れられている背景
- 4.マイクロラーニングの効果・メリット
- 4.1.すき間時間を活用した学習が可能となる
- 4.2.集中力が続きやすく、定着しやすい
- 4.3.教材の作成や修正がしやすい
- 4.4.業務中に必要な内容を確認しやすい
- 5.マイクロラーニングのデメリット
- 5.1.実践や演習などを取り入れにくい
- 5.2.教材の準備に手間がかかる
- 5.3.期限を管理しないと進捗に差が生まれる
- 6.マイクロラーニングに適しているカリキュラム
- 6.1.コンプライアンス研修
- 6.2.アルバイト研修
- 7.マイクロラーニングが向いていないカリキュラム
- 8.マイクロラーニングの作り方のコツ
- 8.1.1話完結型のコンテンツを作る
- 8.2.コンテンツ数を担保する
- 9.マイクロラーニングを育成に取り入れるコツ
- 9.1.他の研修方法と併用する
- 9.2.自発的に学べる環境を整える
- 10.マイクロラーニングのプラットフォームにはLMS
- 10.1.使いやすいUI/UX
- 10.2.コース検索で必要な教材がすぐ見つかる
- 11.まとめ
eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
マイクロラーニングとは?
マイクロラーニングとは、「小さなサイズの教材を使った学習方法」のことで、短時間で学習できる短い動画や、クイズ、テキストなどを教材としています。一般的には5分~10分程度で学習が終わるように作られています。
学習者はタブレットやスマートフォンを使って、すき間時間や移動時間などを活用して勉強でき、学習する人の負担にならない新しい学習スタイルです。学習コンテンツの中には、ゲーミフィケーションを取り入れた形式のものもあり、楽しく学習できる工夫がされています。
また、マイクロラーニングはeラーニング形式で実施されることもあります。
eラーニングの基本情報について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
『eラーニングとは?意味やメリット・デメリットについて簡単に解説』
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
マイクロラーニングが生まれた技術的背景
企業での研修は、受講者が集まって1日~数日かけて行う集合研修のスタイルが主流でした。しかし、eラーニングなどのオンライン研修の増加に伴い、マイクロラーニングが注目されています。
ここでは、マイクロラーニングが生まれた技術的背景についてご紹介します。
スマートフォンの普及
マイクロラーニングが生まれた背景として、スマートフォンの普及が挙げられます。
2010年にスマートフォンを保有している世帯の割合は9.7%でしたが、2020年には86.8%と約9倍となっています。
短時間のコンテンツを見るためにパソコンを開くのは手間ですが、スマートフォンの普及によって短いコンテンツをいつでもどこでも手軽に視聴できるようなったことが、マイクロラーニングの普及につながりました。
参考:若者を取り巻く社会環境の変化 | 消費者庁
クラウド型LMSの普及
マイクロラーニングを行う場合、短尺の動画で学習をするとなると、何百本何千本という大量の動画をアップする必要があります。マイクロラーニングが普及した背景には、そうした大量の動画教材を扱える機能を持ったクラウド型LMS(学習管理システム)が出てきたことがあげられます。さらに、細かい単位の学習であるマイクロラーニングでも、LMSの学習履歴管理機能を使えば学習管理がしやすくなります。
データベースの性能向上
前述した通り、マイクロラーニングを行う場合には大量の教材が必要になります。大量の教材から学びたいものを検索して見つけ出すには、LMSの検索機能などデータベースの性能の向上が重要です。高性能なデータベースがクラウド型LMSに搭載され、多くの教材から必要な教材を受講者が選びやすい環境が整えられたことによって、従来よりもさらにマイクロラーニングを導入、活用しやすくなりました
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
マイクロラーニングが取り入れられている背景
ここでは、現在企業の研修でマイクロラーニングが取り入れられている背景についてご紹介します。
研修にコストが割けない
近年、人手不足による業務の増加や、社員に求めるスキルの多様化により、従来の集合研修では多くのコストがかかる傾向が見られます。
産労総合研究所の調査によると、2021年度の企業の教育研修費用総額は5,221万円に上り、前年と比べて596万円増加している事からも、研修コストが上昇していることが分かります。
参考:2022年度 教育研修費用の実態調査
この状況を受け、コストを抑えつつ効果的な研修を実施する需要が増し、マイクロラーニングが取り入れられるようになりました。マイクロラーニングやeラーニングは、一度教材を作成すれば繰り返し利用でき、集合研修のように社員の交通費や宿泊費がかかることもありません。
集合研修は実技やアウトプットの場として活用することで、必要最低限に抑えることができるので、結果として研修コストを抑えることにつながります。
通常の研修では集中力が長続きしない
これまでの研修は30分~1時間と長時間になることが多く、座学のみでは集中力が続かないことがありました。
人が継続して集中できる時間は、15分と言われています。集中力を維持しながら学習するためには、1回の学習が短時間であるマイクロラーニングが最適です。
短時間に集中して学べるため、継続して取り組むことができ、学習の習慣化と知識の定着が可能となるでしょう。
手軽かつ短時間で学ぶ学習スタイルが普及した
前述しましたが、スマートフォンの普及やTikTokなどに代表される短尺コンテンツの普及などにより、手軽かつ短時間で情報収集することが主流となってきています。
マイクロラーニングは学習内容を細かく細分化し、一つのコンテンツにつき一つのテーマが完結するように構成されています。それにより、学習者に対して学びたい内容をピンポイントで伝えることが可能になりました。
そのため、「悩んでいることをすぐに解決できる」「重要なコンテンツの見直しがしやすい」などのメリットがあり、企業の研修にも注目されています。
ビジネスの変化が早く、教材がすぐに陳腐化してしまう
従来の研修では、ビジネスの変化が早いため、教材がすぐに陳腐化してしまうことがデメリットでした。研修内容が変わってしまうと、教材や資料の作り直しが必要になります。マイクロラーニングは全てのコンテンツが短時間のため、作り直しがしやすく、新しい情報を常に取り入れることが可能です。
技術開発の影響などで変化しやすい学習テーマや、社内独自の内容など組織運営とあわせて変わるような学習テーマの場合は、マイクロラーニングの活用をおすすめします。それにより、教材制作の手間を削減できるだけでなく、変化にも対応することができます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
マイクロラーニングの効果・メリット

ここまでは、マイクロラーニングとeラーニングの違いや、マイクロラーニングが生まれた背景について解説しました。実際にマイクロラーニングの導入を検討している企業にとっては、メリットやデメリットも把握しておきたいポイントでしょう。
マイクロラーニングの効果・メリットには、以下の3点が挙げられます。
- すき間時間を活用した学習が可能となる
- 集中力が続きやすく、定着しやすい
- 教材の作成や修正がしやすい
それぞれ詳しく解説していきます。
すき間時間を活用した学習が可能となる
まとまった時間が必要な従来の研修は、後回しにされやすく、受講しないままになってしまうかもしれません。また、通常の業務も並行して行わなければならないため、長時間の研修は業務の妨げになってしまうことがあります。
マイクロラーニングは、5分〜10分ほどの短時間で学習できるので、すき間時間を生かした学習ができます。通常の業務が忙しい場合でも、移動時間などを利用して受講できるため、普段の業務を圧迫しません。
集中力が続きやすく、定着しやすい
マイクロラーニングは一つのコンテンツの学習時間が短いため、集中力が続きます。そのため学習効果が高く、記憶が定着します。
また、通勤時間や業務の合間などで学習できるので、、生活の中に取り入れやすいことも特徴です。学習意欲はあるものの、なかなか習慣づけることができなかった方も、受け入れやすい学習方法です。
教材の作成や修正がしやすい
デジタル技術に関する内容など、変化が著しい分野について学ぶ場合、従来のeラーニングではコンテンツの作成や更新に工数がかかります。
マイクロラーニングの教材は、1つのコンテンツがコンパクトにできているため、作成や修正がしやすい点もメリットです。
また、受講者の状況を見て教材の内容を変えることも容易ですので、研修のPDCAを回しやすいことも大きなメリットといえるでしょう。
eラーニング教材は購入すべきか、自社開発すべきか詳しく知りたい方は『eラーニングの教材は購入すべき?開発すべき?良い教材のポイントも』をご覧ください。それぞれのメリット・デメリットを紹介しています。
業務中に必要な内容を確認しやすい
マイクロラーニングは学習内容を細分化し、一つのコンテンツにつき一つのテーマが完結する構成になっているということを前述しました。
そのため、学習や研修だけでなく、業務中でも必要な内容をすぐに確認することができるため、「以前習ったことを忘れてしまった」「久しぶりに使うツールの使い方が分からない」という時に、データベースとして活用できます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
マイクロラーニングのデメリット
上記ではマイクロラーニングのメリットを解説しました。しかし、デメリットもあることを理解しておかないと、うまく活用できません。
マイクロラーニングのデメリットには、以下の3点が挙げられます。
- 実践や演習などを取り入れにくい
- 教材の準備に手間がかかる
- 期限を管理しないと進捗に差が生まれる
では、それぞれ詳しく解説していきます。
実践や演習などを取り入れにくい
マイクロラーニングは、動画やクイズ、テキストを中心とした小さなコンテンツの集まりです。そのため、実践や演習を取り入れにくい点がデメリットです。また、長時間の学習が必要な資格取得のための学習や、複雑で難しい内容の学習は、短いコンテンツ内では十分な解説ができないため不向きです。
実践や演習が必要な内容については、ロールプレーやグループワークを取り入れやすい集合研修と組み合わせると良いでしょう。集合研修とその事前準備としてのマイクロラーニングの組み合わせで、より高い効果が得られます。
教材の準備に手間がかかる
マイクロラーニングは、一つのコンテンツが短い分、全てを修了するためには多くのコンテンツが必要になります。
一つのコンテンツの作成時間は短いものの、量を担保しなければならないため、教材の作成は準備に手間がかかるでしょう。また、LMSでの管理や更新にも工数がかかるので、事前に管理方法を決めておくことが必要です。
期限を管理しないと進捗に差が生まれる
マイクロラーニングは期限を管理せず運用すると、利用者個々人のあいだで進捗の差が生まれてしまいます。
いつでも受講できる手軽さはメリットですが、通常の業務が忙しい場合には後回しにされ、忘れられてしまう可能性があります。指定の学習をいつまでに終わらせる、などの期限を設けておくことが重要です。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
マイクロラーニングに適しているカリキュラム
マイクロラーニングに適しているカリキュラムとして、以下の2つが挙げられます。
- コンプライアンス研修
- アルバイト研修
それぞれ、理由と取り組みの例についてご紹介します。
コンプライアンス研修
コンプライアンス研修は、全社員に対して必須のカリキュラムです。いつでもどこでも、短時間から進められるマイクロラーニングなら、「時間がないからできなかった」という理由での未受講を防ぐことができます。
1〜2週間ほどの受講期間を設定し、「それぞれ進められるタイミングで進めてください」と要請しておくことで、誰もが無理なく受講することができます。一方、強制力が低下しないように、途中で受講のリマインドを配信するといった施策も必要です。
アルバイト研修
店舗で接客を行うアルバイトが、業務のスキルを身につけるための研修にもマイクロラーニングが適しています。
アルバイトは、全員がPCを所持しているとは限りません。スマートフォンで手軽に学べるマイクロラーニングなら、短い動画を視聴するだけで学べるため、心理的な負担も少ないでしょう。また、研修で学んだ内容を業務の途中で確認したい時も、コンテンツが細かく分かれているマイクロラーニング教材なら効率的に再視聴ができます。
マイクロラーニングが向いていないカリキュラム
マイクロラーニングが向いていないのは、時間や量が学習に必要なカリキュラムです。
例えば、学習量の多い資格試験対策は、マイクロラーニングで学習しようとすると、多くの短い教材を視聴しなくてはならないため、時間が掛かってしまいます。
そのため、全体的な学習はeラーニングなどで行い、重要なポイントや頻出問題などの復習として、マイクロラーニングを活用することをおすすめします。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
マイクロラーニングの作り方のコツ

ここまで、マイクロラーニングのメリットやデメリットなどをご紹介しました。実際にマイクロラーニングの教材は、どのように作れば良いのでしょうか。
ここでは、教材を作成する時のコツをご紹介します。
以下のポイントを意識してみましょう。
- 1話完結型のコンテンツを作る
- コンテンツ数を担保する
では、それぞれ詳しく解説していきます。
1話完結型のコンテンツを作る
マイクロラーニングのコンテンツは、1話完結型にしましょう。短いセンテンスに区切ることで、すき間時間で学習するのに最適なコンテンツが作れます。
1話完結型のコンテンツは、内容が簡潔にまとめられているので、理解しやすいメリットがあります。理解しやすいと集中力が続き、学習効率の向上にも繋がるでしょう。また、コンテンツの修正や管理も容易になります。
コンテンツ数を担保する
マイクロラーニングは一つのコンテンツが短い分、多くの内容を含むにはコンテンツ数を担保する必要があります。
コンテンツ数が少ない状態で始めてしまうと、コンテンツの続きをすぐに視聴できず、中途半端な状態で学習が中断し、学習効率が低下してしまいます。
そのため、必要な内容を全て理解できるようなコンテンツ数を担保しましょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
マイクロラーニングを育成に取り入れるコツ
下記に、実際にマイクロラーニングを取り入れる際に気を付けておきたいポイントを2つご紹介します。
- 他の研修方法と併用する
- 自発的に学べる環境を整える
一つずつ解説していきます。
他の研修方法と併用する
マイクロラーニングを育成に取り入れる場合には、全ての学習をマイクロラーニングにするのではなく、学習内容に合わせて集合研修などの他の研修方法と併用することが大切です。
マイクロラーニングは実践や演習を取り入れられないため、例えば、ロールプレイングを通して自分の課題を発見し解決方法を考える研修や、必要なマインドセットを習得するための研修、テレアポなど電話対応の演習などは集合研修で行うと良いでしょう。
基本の考え方はマイクロラーニングで学び、演習を集合研修で行うことで、研修の効果を最大限に引き出せます。
自発的に学べる環境を整える
マイクロラーニングは、いつでもどこでも学習できることがメリットですが、その利便性から後回しになってしまう可能性があります。
そのため、ある程度強制的に、「マイクロラーニングでの学習が完了した受講者だけが集合研修に参加できる」「学習完了後にのみ必要なツールにログインできる」などの仕組みづくりが大切です。
また、学習環境へのアクセスのしやすさ、操作のしやすさも自発的に学ぶ環境を作る一つのコツです。配信ツールやLMSの選定時に、アクセスはしやすいか、必要な情報がしっかりと検索できるかなども確認しておきましょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
マイクロラーニングのプラットフォームにはLMS
自社でマイクロラーニングを行うには、学習のプラットフォームとなるLMSの導入が必要不可欠です。
LMSはコンテンツをアップロードして配信できるだけではなく、受講者一人ひとりをアカウント化し、学習の進み具合を可視化して管理できるというマイクロラーニングに最適な機能も搭載されています。
弊社アルー株式会社では、使いやすいクラウド型LMSである「etudes」を提供しています。
ここでは、etudesの特徴をご紹介します。
使いやすいUI/UX
etudesは受講者向け機能と管理者向け機能の両面で、LMSとしての使いやすさを重視して開発されており、直感的でわかりやすいUI/UXを採用しています。特に受講者は、マニュアルなしで操作が可能です。
マイクロラーニングを育成に取り入れる場合、受講者の教材へのアクセスのしやすさはとても重要です。etudesのUI/UXなら、すぐに学習したい教材にアクセスが可能です。
コース検索で必要な教材がすぐ見つかる
etudesは、受講者に必要なコースがすぐに見つかるように、キーワード検索、カテゴリ機能、関連コース表示などの機能を搭載しています。
マイクロラーニングは教材数が多いため、必要な情報が埋もれてしまいがちです。etudesは、検索機能で必要なコースをすぐ見つけられ、前回受講した教材をリアルタイムで受講画面に反映されるようになっています。
また、受講した教材に関連したコースが表示されるため、続けての学習が容易で関連知識をより深めて行くことも可能です。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
マイクロラーニングは短時間で学習ができるため、すき間時間を有効活用できることや、集中力が続きやすく定着しやすいメリットがあります。
ただし、長時間の学習を必要とする内容は、コンテンツの量が多くなり管理が煩雑になってしまうので、マイクロラーニングには不向きです。
マイクロラーニングを取り入れる際には、管理するLMSの選定が重要になります。アルー株式会社が提供しているetudesは、受講者がアクセスしやすく、コンテンツの管理がしやすいLMSです。
etudesの詳しい製品紹介を知りたい方は『製品紹介資料』をダウンロードしてください。etudesの特徴やデモ画面、費用についてご紹介しています。