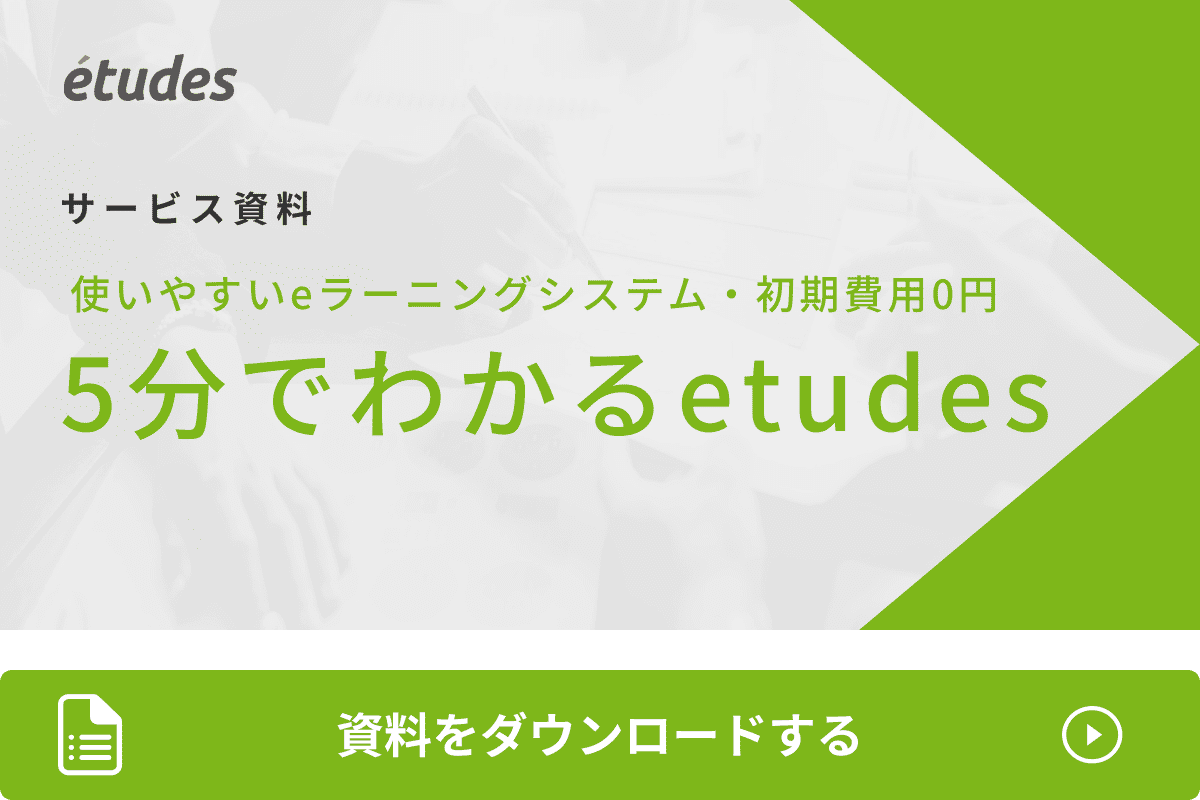eラーニング教材は自社開発すべき?購入すべき?受講者と企業の視点で解説
eラーニングに使用する教材は、ベンダーからの購入や自社開発といった方法で入手することができます。eラーニングを導入する際、どのような内容の教材が自社に必要か、目的に応じてeラーニング教材やシステムを選定することが重要です。検討前に知っておくべきことや、eラーニング教材の種類について詳しく解説します。
実際にeラーニング教材を企業でどのように活用して人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
- 1.eラーニングは教材の選択が重要!
- 2.eラーニング教材の種類
- 3.eラーニング教材で「動画」が活用される理由
- 3.1.動画教材で学ぶことのメリット
- 4.eラーニングの教材を入手する4つの方法
- 5.1.パッケージ商品を購入する
- 5.1.メリット・デメリット
- 6.2.パッケージ商品をカスタマイズする
- 6.1.メリット・デメリット
- 7.3.教材を外注し作成する
- 7.1.メリット・デメリット
- 8.4.教材を自社で作成する
- 8.1.メリット・デメリット
- 9.「etudes」が提供するeラーニング教材をご紹介
- 9.1.人材育成会社による豊富な汎用コンテンツ
- 9.2.オリジナルeラーニング教材作成サポート
- 9.2.1.サポートの流れ
- 10.eラーニング・LMS導入なら「etudes(エチュード)」
- 10.1.充実のLMS機能
- 10.2.使いやすさにこだわったシステム設計
- 10.3.「etudesPlus」ならeラーニング教材が受け放題
- 11.まとめ
eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
eラーニングは教材の選択が重要!
企業でeラーニングを導入する場合は、受講者が学習するための教材と、受講のためのシステム導入が必要になります。
- eラーニング教材
- LMS(eラーニングシステム・学習管理システム)
LMSとは、「Learning Management System」の略称で、eラーニング受講するプラットフォームとなるシステムです。eラーニング教材の受講だけでなく、システムの管理画面から受講履歴を取得するなど、学習管理をシステムで一元管理することができます。また、eラーニングを含めた研修運営全体を効率化できる機能を搭載しています。
一方で、eラーニング教材は動画中心の場合から、テストや演習がついた実践的なものまで、さまざまな教材があります。また、学習形式だけでなく、テーマも様々で、階層別のスキルや役割をテーマにしたものや、ビジネススキルやコンセプチュアルスキルなどのスキル別の教材もあります。
企業でeラーニングを導入する際、自社の課題に合わせた教材選びが重要です。階層別教育を実施したい場合に、スキル別の教材のみでは不十分になります。また、より実践的なスキルを学びたい場合に、動画視聴のみの教材では、得た知識を実務に活かしにくくなるなど、目的に応じて適切な教材を選択しないと期待する成果が出ないこともあります。
そのため、事前に自社の課題に応じてどのようなeラーニング教材が必要かを明確にした上で、教材やシステムの選定をする必要があるでしょう。
教材だけでなく、LMSについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。『LMSとは?学習管理システムの基本情報とメリットを徹底解説』
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニング教材の種類

eラーニング教材にはさまざまな手法がありますが、ここではよくある4つの教材形式を紹介します。
- スライド形式
- アニメーション形式
- 講義再現形式
- 動画収録形式
以下にて詳しく見ていきましょう。
スライド形式
スライド形式は、従来の集合研修で使用していた紙媒体の資料をスライド化し、配信するものです。
既存の研修データを活用できるため、手軽にeラーニング教材を作成できるメリットがあります。一方で、手の込んだアレンジが難しいため、シンプルな教材になる特徴があります。
アニメーション形式
動きのあるスライドに、ナレーションをつけたものがアニメーション形式です。
スライド形式と比較して、キャラクターによる動きがある教材となるため、内容がわかりやすく飽きずに学習できるというメリットがあります。
講義再現形式
講師による講義を再現する形式の動画教材です。
黒板やスライドを映す大画面と、講義を行う講師が映るワイプの2画面構成となっています。講義が進むと、黒板やスライドの文章に下線が引かれる・ポイントを指差しするといったアクションが表示され、実際の講義の様子を再現します。
集合研修で行う講義と同じような表現力があり、動画教材としても作成しやすく、導入しやすい形式といえます。
動画収録形式
講師が実際に講義をしている様子を収録する形式の動画教材です。
前述の講義再現形式は黒板やスライドをアニメーションで再現する必要がありましたが、この形式では講義そのものを収録する形になるため、動画編集の負担が軽減されます。
動画編集スキルの有無に関係なく、最も動画教材が作りやすい方法です。
反面、要点がわかりにくかったり、動画が長くなりやすかったりといった注意点があるので、実際に作成する際は工夫が必要です。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニング教材で「動画」が活用される理由
近年のeラーニングコンテンツでは「動画教材」や「動画」とその他形式の学習手法を組み合わせた教材が多くなっています。動画教材は、スライド教材などと比べて作成に一定の工数がかかるコンテンツですが、多くの企業で活用されています。動画教材ならではのメリットと利便性を解説します。
動画教材で学ぶことのメリット
動画教材によるeラーニングのメリットとして、学ぶ内容によって動画を活用することで学習効率が高まることが挙げられます。文章よりも動画の方が直感的に理解しやすいだけでなく、視覚情報として記憶に残りやすく、得たスキルを実践しやすくなります。
例えば、接客方法を教えるeラーニングにおいて、全ての動きや対応方法をテキストとイラストなどの固定した情報だけで表現するのは難しく、その場合、受講者が必要な学びのポイントを正しく理解できない可能性もあります。
一方動画教材なら、正しい接客方法を実践に近い形で目と耳で学ぶことができ、知識をインプットした後のロールプレイングなども進めやすくなります。PCが無い環境でもスマートフォンやタブレットで学習しやすい点も動画教材で学ぶメリットです。
自社で動画制作が難しい、外注できる予算がない場合でも、Microsoftのパワーポイントを使って動画教材を簡単に内製することもできます。動画教材を自社で作成したい場合はこちらの資料「パワポで完結・動画制作のポイント」の無料ダウンロードもおすすめです。
eラーニング用の動画教材の効果や配信方法については、以下の記事で詳しく解説しています。『eラーニング用動画の作成方法を解説!データ容量や配信時の注意点は?』
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングの教材を入手する4つの方法

実際にeラーニング教材を入手する4つの方法を見ていきましょう。
- パッケージ商品を購入する
- パッケージ商品をカスタマイズする
- 教材を外注し作成する
- 教材を自社で作成する
それぞれのメリット・デメリットについて、詳しくご紹介します。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
1.パッケージ商品を購入する
eラーニングベンダーが提供している数多くのパッケージ商品から、最適な教材を選択して購入する方法です。LMSを自社が保有しているかいないかによって、購入方法が異なります。LMSを保有している場合は、教材コンテンツの規格と自社LMSの規格が合致していることを確認した上で、eラーニングコンテンツだけを購入します。
LMSを保有していない場合は、教材がプリセットで搭載されたLMSを導入することで、運用開始と同時にeラーニング研修を開始できます。
メリット・デメリット
プロが作成した高品質な学習教材を使用できることが、パッケージ商品を購入する最大のメリットです。
eラーニングベンダーによっては、企業向けに提供してきた研修のノウハウを生かした教材を提供しているところもあります。コンプライアンス研修やビジネスマナー研修といった汎用的な教材から、ビジネススキルを磨くための思考法を学ぶ演習教材まで、幅広いジャンルから選べることがメリットです。
一方で、求めている内容と100%合致するeラーニングが販売されていないこともあります。パッケージ商品では、自社ならではのノウハウを学ぶオリジナル性が高い教材を得られない点はデメリットとなるでしょう。
▼eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
2.パッケージ商品をカスタマイズする
続いては、パッケージ商品のカスタマイズです。eラーニングベンダーにもよりますが、以下のような方法でパッケージ商品はカスタマイズが可能です。
- 教材を統合・分割して長さを変える
- 教材に情報を追加する
- ケーススタディを変更する
- テスト内容を変更する
- 専門用語を追加する
複数の教材の内容を統合するカスタマイズの他にも、ケーススタディを自社の実際のものに変更したり、社内で使用している専門用語を追加したりすることができます。既存のテストに、より専門的な問題を加えることも可能です。
ある程度は既存のeラーニングでカバーしつつ、少し内容を追加・変更することで更に良くなる場合には、この方法を検討すると良いでしょう。
メリット・デメリット
パッケージ商品のカスタマイズは、クオリティの高い学習コンテンツと、自社独自のノウハウの組み合わせが可能となり、大きな研修効果が期待できます。
一方で、既に作成されている学習コンテンツを加工すると、そのクオリティが下がってしまう可能性があることも否めません。学習の妨げにならないようにカスタマイズをするには、ある程度の動画編集や教材作成のスキルが求められます。
この方法を試したい場合は、教材カスタマイズの実績があるeラーニングベンダーを選び、まずは相談してみるといいでしょう。
▼eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
3.教材を外注し作成する
eラーニング(LMS)ベンダーに、教材の作成を一から依頼する方法です。以下のような企業は、教材の外注を検討した方が良いでしょう。
- どんなeラーニングを実装すればいいか分からない
- 自社のノウハウをeラーニング化したい
一から教材を作ることによって、eラーニングの自由度は格段に上がります。
eラーニング教材作成の大まかな流れは下記のとおりです。
- 情報収集
- 概要仕様確定
- 詳細仕様確定
- eラーニング内容作成
- オーサリング
- 確認・修正
情報収集では、社内の課題を明確化し、どのようなeラーニングであれば課題が解決できるかを、経験豊富なコンサルタントとともに検討します。ベンダーによっては、「優秀な社員を育成するにはどうすればいいか」といった根本的な悩みから丁寧にヒアリングし、解決策を提案してくれるところもあります。
情報収集が完了し、導入するeラーニングの概要が決まったところで、見積段階に入ります。次に実際の開発段階に入り、オーサリングと呼ばれるwebコンテンツへの組み上げ作業を経て、完成品の確認、最終修正に入ります。
メリット・デメリット
教材を100%外注することで、クオリティの高いオリジナルeラーニング教材が作成できることが最大のメリットです。
自社に特化したeラーニングコンテンツとなるため、学習による効果も高まるでしょう。顧客への対応方法を動画教材にしてマニュアル化したり、優秀な社員の営業テクニックをeラーニングにしてスキルの底上げを図ることも可能です。
デメリットとしては、費用がかかることが挙げられます。eラーニング教材を作成する4つの方法の中で、コストが高くなりやすいでしょう。
▼eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
4.教材を自社で作成する
最後のeラーニング教材入手の方法は、教材を自社で作成する方法です。
全ての行程を自社で行う場合は、PowerPointファイル、Excelファイル、音声ファイルやアニメーション動画を用意して、プログラムを組み上げていきます。社内にeラーニング開発の知識があることが必須となります。
この場合は、eラーニング(LMS)ベンダーの力を借りなくてもeラーニングの導入が可能ですが、受講にはプラットフォームとなるeラーニングシステム(LMS)が必要なため、システムの構築も自社で行うか、専門ベンダーが提供するシステムに自社で開発したeラーニングを搭載する必要があります。
メリット・デメリット
教材を自社で一から十まで全て作成するメリットは、専門業者への委託コストが一切かからないことが挙げられます。自社内でeラーニングを作成できるスキルやノウハウがあればスムーズですが、以下の課題を解決できるかが重要です。
- 受講者にとって学びやすく、学習効果のあるコンテンツを作成できるか
- 教材の作成だけではなく、継続して運用しブラッシュアップしていけるか
eラーニングベンダー提供の教材作成ツールを利用する場合は、完全自社開発ができるほどの知識は必要ありません。開発コストを押さえて、eラーニング導入を実現できる良い方法だと言えるでしょう。
▼eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
「etudes」が提供するeラーニング教材をご紹介
実際にeラーニング教材を取り扱っているetudesのラインナップからおすすめの教材をご紹介します。
etudesは、アルー株式会社が開発したeラーニングシステム(LMS)です。クラウド型・初期費用無料といった導入のしやすさ、運用のしやすさから多くの企業に選ばれています。etudesは、LMSとしての使いやすさだけではなく、豊富なeラーニング教材を取り扱っている点も大きな魅力です。
人材育成会社による豊富な汎用コンテンツ
etudesを開発したアルー株式会社は、これまでに多くの企業の人材育成をサポートしてきました。その数は1,493社にのぼります。
そのノウハウを生かして独自に開発しているeラーニング教材は、階層別の人材育成に特化しているだけでなく、内容も演習が組み込まれた実践的で実務に活かしやすいプログラムになっています。
etudesのeラーニング教材一覧から、「階層別セットプラン」と「テーマ別教材」をご紹介します。
階層別セットプラン
役職や階層ごとに求められるスキルが身に付く、eラーニング教材のセットプランです。
- 新入社員/内定者向け <スタンダードプラン>
新入社員や内定者に必要なビジネスマナーから、社会人に向けたマインドセットといった教材のセットです。コンテンツを厳選した「ライトプラン」もあります。 - 若手社員向け
新入社員を卒業し、戦力となる若手社員に必要なスキルを網羅した教材セットです。 - 中堅社員向け
会社の中核となり、将来を担う中堅社員に必要なスキルが揃った教材セットです。 - チームリーダー向け
チームをまとめ、目標に向けて進むために必要な視点、スキル、スタンスが身に付く教材セットです。 - 管理職向け
時代の変化に適応し、組織を牽引する管理職になるために必要なスキルがまとまった教材セットです。
この他にも、OJTトレーナー向けセット、DX3コースセット(DXリテラシーテスト付き)などの豊富なセットプランがあります。
テーマ別教材
社員に学ばせたいテーマ別の教材セットも用意しています。
- ビジネススキル
報告・連絡・相談といったビジネスの基本から、Excel・PowerPointなどの操作方法まで幅広く学べる教材セットです。 - マネジメント・部下育成
目標の設定方法やリーダーシップが学べる教材セットです。 - 思考力・コンセプチュアルスキル
論理的思考力やコミュニケーション能力などを磨く教材セットです。 - ITスキル
Javaプログラミングの基礎や、サーバー運用に欠かせないLinuxの資格取得が目指せる教材セットです。 - コンプライアンス
ハラスメント講座と個人情報保護法講座の教材セットです。
この他にも、多様な文化を学ぶ「グローバル」、経理のスキルが身につく「アカウンティング」といったスキルのテーマ別教材もご提供しています。
オリジナルeラーニング教材作成サポート
etudesでは、豊富なコンテンツの提供だけではなく、オリジナルeラーニング教材の作成サポートも行っています。
- 紙で共有している自社独自の営業ノウハウをeラーニング化したい
- 毎年行っている自社ならではの全社研修をeラーニング化したい
このような要望を持ちつつeラーニング教材の作成経験がない企業に向けて、アルー株式会社が教材作成をご支援します。完成したeラーニング教材は、etudesで受講することが可能です。
サポートの流れ
etudesのオリジナルeラーニング教材作成サポートは、研修のプランニングからご支援します。丁寧なヒアリングを実施し、教材のプランをご提案します。最適な教材形式で設計・制作を行い、ご指定のデータ形式での納品、学習の効果測定まで実施します。
詳しくは、etudes_オリジナル教材を作成ページにてご確認いただけます。
eラーニング・LMS導入なら「etudes(エチュード)」
etudesは、「既存のeラーニング教材を購入したい」「自社独自のeラーニング教材を作りたい」どちらのニーズにも対応できるeラーニングシステムです。
教材の充実度に加えて、システムとしてのetudesの強みをご紹介します。
充実のLMS機能
etudesは、LMSとしての学習管理機能も充実しています。受講者一人ひとりをアカウントで管理でき、学習の進捗状況をリアルタイムで把握することが可能です。学習状況に応じたメールの自動送信やテストの実施も、システム上で簡単に行えます。
また、教材視聴後にテストを行う機能や、カリキュラムを達成した際に自動で修了証を発行するといった便利な機能も搭載されています。
etudesの詳しい製品紹介を知りたい方は『製品紹介資料』をダウンロードしてください。etudesの特徴やデモ画面、費用などをご紹介しています。
使いやすさにこだわったシステム設計
学習を管理する管理者、eラーニングの受講者、双方にとってわかりやすいUIデザインもetudesの特徴の一つです。特に受講者が直感的に使いやすいシステムであれば、社内運用の際の周知がスムーズになるだけでなく、継続的に運営する際の質問なども減り、管理者側の負担が大幅に軽減されます。
受講者にとっても、操作性が簡単であれば学習内容により集中して取り組むことができ、継続しやすくなります。
育成の成果を高めるために使いやすさにこだわったシステム設計が特長です。
「etudesPlus」ならeラーニング教材が受け放題
「数多くある教材から、社員一人ひとりに最適なカリキュラムを選んで研修させたい」このような要望をお持ちなら、eラーニング受け放題プラン「etudesPlus」がおすすめです。
etudesPlusなら、LMSとしてのetudesに100以上のカリキュラムが搭載された状態で導入できます。
カリキュラムは、全てアルー株式会社の人材育成の実績に基づいて設計されています。受講者ごとに最適な教材を表示する「レコメンド機能」も搭載されており、膨大なカリキュラム・教材から迷うことなく効率的なeラーニング学習が可能です。
詳しくは、etudesPlusの詳細ページをご覧ください。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
eラーニング教材の選び方と入手について、まずは自社の状況や抱えている課題を洗い出し、それを解決に導くeラーニング教材を選ぶようにしましょう。eラーニング教材導入を成功させたいとお考えの方は、アルー株式会社の提供する「etudes」をご検討ください。豊富なセットプランだけでなく、「ビジネススキル」や「マネジメント・部下育成」などのテーマ別に教材を選択でき、貴社に合った教材を見つけることができるでしょう。