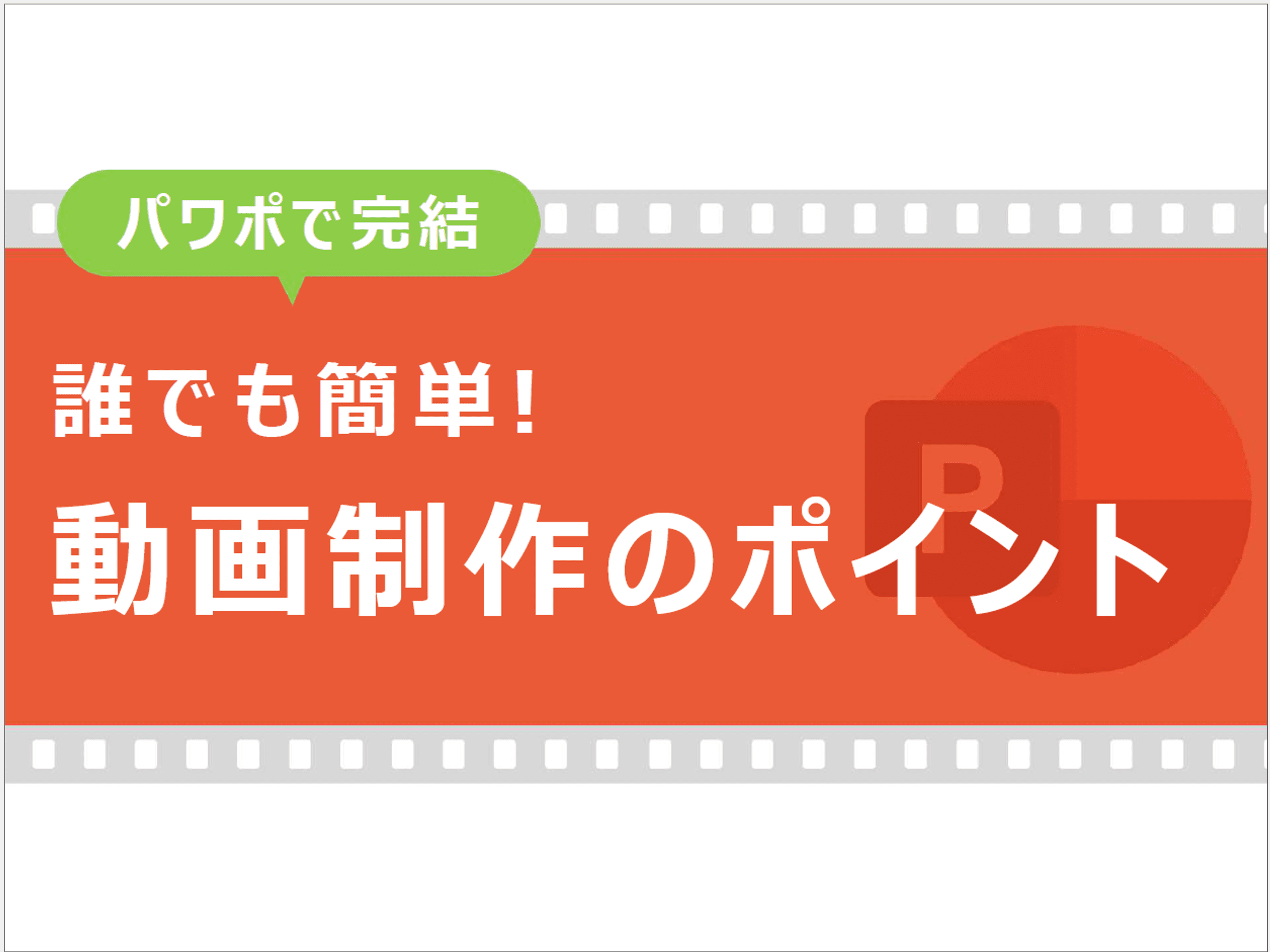eラーニング用動画の作成方法を解説!データ容量や配信時の注意点は?
近年、企業の人材育成に、eラーニングが活用されることが増えています。eラーニングとは、インターネット環境があれば、いつでもどこでも学ぶことができるオンライン学習方法です。
eラーニング教材の中でも動画コンテンツは、視覚的な情報を豊富に取り入れられるため、一般的なテキスト教材と比べて学習効果が高く、研修に取り入れる企業が増えています。
本記事では、eラーニング用動画教材の作成方法、配信する方法、ポイントを詳しく解説しています。
自社で簡単に動画を作りたい方は「パワポで完結・動画制作のポイント」の資料ダウンロードがおすすめです。パワーポイントの基本機能で簡単に動画を制作できます。
実際に企業でどのようにeラーニング活用をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
目次[非表示]
- 1.eラーニングに動画教材が効果的な理由
- 2.eラーニングの動画教材を作成する方法
- 2.1.1.オンライン会議ツールの録画機能を使う
- 2.2.2.パワーポイントから作る
- 2.3.3.スタジオなどで動画学習用の講義を撮影して作る
- 2.4.4.専門業者に発注して作る
- 2.5.5.教室で行う集合研修を撮影する
- 3.近年の動画教材のトレンド
- 4.動画教材をeラーニングで配信する方法
- 4.1.無料動画アップロードサイトで配信
- 4.2.メールで配信
- 4.3.LMSで配信
- 5.LMS導入時に確認すべきポイント
- 5.1.アップロードできるデータ容量
- 5.2.動画再生時の画質
- 6.動画教材を作成してeラーニング配信するメリット
- 6.1.LMSによって学習管理ができる
- 6.2.集合研修よりもコストがかからない
- 6.3.繰り返し視聴して反復学習ができる
- 6.4.LMSの機能で飛ばし見を防止できる
- 7.より効果的な動画教材を作成するポイント
- 8.eラーニングで動画教材を配信するなら「etudes」
- 8.1.eラーニング教材内製化支援も
- 9.まとめ
eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
eラーニングに動画教材が効果的な理由
動画教材は、視覚的に学べることから学習効果が高く、習得したスキルを実務で再現しやすいというメリットがあり、eラーニング教材として幅広く活用されています。
動画教材と比較して、テキストだけのPDF資料やスライド資料は作成が容易です。しかし、学んだスキルを実際に使用する場面が想定しにくかったり、読み飛ばしてしまい学習内容が身につきにくかったりといったデメリットは見逃せません。また、テキストだけの場合、学習者がコンテンツの視聴に飽きてしまい、学習モチベーションが下がるというリスクもあるでしょう。
そのため、eラーニングの教材を自社で作成するなら動画教材がおすすめです。
内製による動画などのeラーニングコンテンツ作成についてさらに詳しく知りたい方は、「内製eラーニング教材作りのポイント」の無料ダウンロードがおすすめです。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングの動画教材を作成する方法
eラーニングの動画教材を作成する主な方法は、次の5つです。
- オンライン会議ツールの録画機能を使う
- パワーポイントから作る
- スタジオなどで動画学習用の講義を撮影して作る
- 専門業者に発注して作る
- 教室で行う集合研修を撮影する
それぞれの作成方法によって、かかる費用や時間は異なりeラーニング教材のクオリティも左右されます。自社のeラーニングの環境や想定される受講者層、学習してほしい内容、さらにはeラーニングの予算などを考慮して最適な作成方法を選定しましょう。
企業研修用動画の作り方の手順は、以下の記事で詳しくご紹介しています。
『研修動画の作り方はこの6ステップ!効果的に実施するポイントも解説』
1.オンライン会議ツールの録画機能を使う
ZoomやTeamsなどでオンライン研修を実施し、その様子を画面録画機能を利用し保存することで動画教材を作成することが可能です。この方法であれば、研修の実施とeラーニング動画教材の作成が手軽にできます。また、画面共有機能を利用すれば、映し出した資料もそのまま録画でき、後から動画を編集して資料を挿入する手間を省くことができます。
しかし、録画時には無駄な部分が含まれてしまうこともあります。例えば、「皆さん聞こえてますか?」や「10分間休憩しましょう」といった進行上の会話などは、コンテンツ視聴者にとって必要のない部分を含む可能性があります。そのため、無駄と思われる部分は、動画編集でカットすることがおすすめです。
また、オンライン会議ツールの機能上、画面に表示するスライドの画質は落ちてしまうため、小さな文字がぼやけて読みにくくなるなどのリスクもあります。さらに、研修を実施する際のインターネット接続の状態によっては、録画された動画の音声が聞きづらいものになる可能性もあります。
これらの理由から、画質や音質にこだわらず、最新情報をタイムリーに共有することを優先したいコンテンツに向いている方法です。
2.パワーポイントから作る
パワーポイント(PowerPoint)を使うと、制作コストを抑えつつ、比較的容易に質の高いeラーニング教材を作成することができます。
文字だけでなく図やイラストを用いることで視覚的な説明を加えたり、アニメーション機能を使って動きをつけることで、インパクトを強化したりすることが可能です。動画を組み込むことも可能なため、具体的な操作手順や実際の現場での様子などをリアルに伝えることもできます。
また、パワーポイントにはナレーション音声を録音する機能もあります。音声録画機能を使えば、スライドをめくりながら説明を加えたり、マーカーで線を引いてポイントを強調したりするなど、視覚と聴覚を同時に使った効果的な動画を簡単に制作できます。
パワーポイントを使えば短時間でeラーニングの動画を作ることができるため、新しい情報や変更点をタイムリーに伝えたいコンテンツに適しています。
3.スタジオなどで動画学習用の講義を撮影して作る
スタジオなどで動画教材を作成する場合、カメラや収録場所、講師の調整などが必要ですが、高品質な教材が作成できます。さらに、パワーポイントなどの資料を組み合わせて編集することで、より視覚的で理解しやすい動画教材を作成することが可能です。
具体的な方法としては、一つ目が専用スタジオを借りて撮影する方法です。
一定の費用はかかりますが、機材や技術者をスタジオ側で用意してくれるため、講師と収録内容を確認する最低限のスタッフで撮影が可能です。
また、撮影後の編集もスタジオに依頼できるため、全体の工数を抑えることが可能です。最近では、グリーンバックの前で講師が話す動画を撮影し、スライド部分を後編集で合成する手法が増えています。この手法を使えば、スライドの文字もクリアに表示されて受講者にとって見やすい動画になります。
二つ目は、自社の会議室などで撮影する方法です。スタジオ代はかかりませんが、機材の用意、撮影や編集を自社で行う必要があります。
そのため、全体の工数はスタジオを借りて撮影する方法よりも増えてしまいます。機材においては、音質確保のためのマイク選びが重要です。雑音を防ぎクリアな音声を録音するために、可能ならピンマイクを用意すると良いでしょう。
4.専門業者に発注して作る
eラーニング教材の専門業者に発注するという方法もあります。eラーニング教材を専門業者に依頼する場合、一般的なスキルや知識を学習するコンテンツの場合は、学習内容を考えるところから業者に任せることが可能です。しかし、自社特有のビジネス知識を学習するコンテンツの場合、盛り込むべき内容やスライドの作成、ナレーション原稿のたたき台作りなどは自社で行う必要があります。
このように、依頼する作業の内容・範囲により、必要な費用や期間は変動します。そのため、業者との詳細な相談と調整が重要となります。
また、専門業者に発注するべきコンテンツは、寿命が長く自社ビジネスに特化した内容が最適です。
専門業者に発注するべきコンテンツについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「eラーニングの作り方を5ステップで解説!より良い教材を作るには?」
5.教室で行う集合研修を撮影する
教室で実施する対面式の研修を撮影する方法は、研修実施と動画作成を同時に進行できるという大きなメリットがあります。しかし、撮影には注意事項がいくつかあります。
まず、受講者にとって迷惑とならないよう配慮し、スライドや教材がきちんと読み取れるように撮影することが重要です。また、受講者のプライバシーを保護するために顔が映らないように配慮し、講師の声がクリアに録音できるようマイク設定にも気を付ける必要があります。
さらに、編集で休憩時間など不要な部分を編集し、視聴者にとって分かりやすい動画を作成する作業も必要です。
これらの作業は決して容易なものではなく、しっかりとした技術と知識が必要です。
そのため、一連の作業を専門的な技術を持つ業者に委託することもおすすめです。専門業者に依頼すれば、適切な機材を用いて撮影し、動画の編集まで行ってくれるため、より質の高いコンテンツを提供できます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
近年の動画教材のトレンド
近年の動画教材では、学習効果を高めるために以下のトレンドが注目されています。
- 結論を先出しにした短い動画
視聴者は動画の冒頭で重要なポイントや結論を理解できると、学習のモチベーションが向上し、内容を効率よく吸収できます。
- スマホでの受講を想定した画面レイアウト
スマートフォンでの視聴に最適化されたシンプルで直感的なデザインは、視聴者の利便性を向上させます。
- 知識よりも行動(アクション)の共有
学習者が得た知識を実際の行動に結びつけ、他の学習者と成果を共有することが、より実践的な学びにつながります。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
動画教材をeラーニングで配信する方法

完成した動画教材をeラーニングとして配信する方法として、以下の3つが挙げられます。
- 無料動画アップロードサイトで配信
- メールで配信
- LMSで配信
それぞれの方法について、詳しく解説します。
無料動画アップロードサイトで配信
動画教材を無料の動画アップロードサイトで配信する方法は、コストを抑えつつ広く共有する手段として有効です。具体的には、YouTubeやVimeoなどが挙げられます。
YouTubeには限定配信の機能があり、動画のURLを知らないと視聴できないという機能です。一見セキュアに見えますが、URLが広まってしまうと誰でも視聴できてしまうため、自社のノウハウが詰まったeラーニング教材の配信には向いていません。
また、VimeoのようなID・PWがなければ動画を視聴できないようにする動画配信サービスもありますが、個々の受講履歴を記録する機能が弱いため、受講履歴を詳細に取得し分析することが必要なeラーニングのニーズを満たすことは難しいです。
メールで配信
メールで動画教材を配信する方法は、受講者に直接コンテンツを届けるシンプルな手段です。
動画のリンクをメール本文に添付し、受講者に送信します。動画ファイルそのものを添付することも可能ですが、大容量ファイルは受信者に負担をかける場合があるため、クラウドサービス(Google DriveやDropboxなど)を活用することが一般的です。
この方法は、少人数の受講者向けのeラーニングであれば有効ですが、メールを作成して送る手間がかかり、送信漏れ・送信間違いといったヒューマンエラーが発生するリスクも高いです。
LMSで配信
完成した動画教材をeラーニングとして配信するには、LMS(Learning Managememt System: 学習管理システム)を導入し、動画をアップロードする方法がおすすめです。
LMSは、eラーニングのプラットフォームとして活用できるだけではなく、動画教材を誰がどれくらい視聴したのかといった学習状況の履歴データを一括管理できるというメリットもあります。
LMSの導入や運用には費用がかかるため、LMSを使わずに動画教材を配信したいと考える場合もあるかもしれません。その場合は、無料動画配信サイトやメール配信などという手段もありますが、セキュリティ面でのリスクや機能制限による管理・運営の負担などが発生しやすくなります。
クラウド型のLMSは、初期費用無料で月額利用料の料金体系も柔軟なサービスも多く、自社の予算に合わせて必要な機能を備えたシステムの導入を検討することがおすすめです。
学習管理システム「LMS」については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
『LMSとは?学習管理システムの基本情報とメリットを徹底解説』
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
LMS導入時に確認すべきポイント
動画教材をeラーニングとして配信するため、LMSを導入する際は以下のポイントに注意して比較しましょう。
- アップロードできるデータ容量
- 動画再生時の画質
それぞれのポイントと、おすすめのLMS「etudes」の機能についてご紹介します。
アップロードできるデータ容量
LMSを導入する際、学習管理機能の充実度に注目するだけでなく、保存(アップロード)可能なデータ容量にも目を向けることが重要です。特に動画コンテンツは、他の形式の教材と比べてデータ容量が大きいためです。
LMSによっては、〇〇GBまで保存可能といった容量制限がある場合や、データ容量の上限を超えた場合に追加料金が発生する可能性があります。そのため、動画教材を多数作成し配信したい場合は、追加料金を考慮した上でLMSを比較することが必要です。
特に社用スマホに「1ヶ月7GBまで」などのデータ制限がある場合は、動画視聴によるデータの使用量に注意する必要があります。
etudesならアップロード動画の本数・容量が無制限
多数の動画教材を作成する場合は、システムへの動画アップロード総データ容量が無制限のLMS「etudes」がおすすめです。
他のLMSでは、基本料金でアップロード可能なデータ容量がxxxGBとなっていることが多く、超えてしまうと1GBごとに1000円程度の追加料金が発生するケースが多いです。
このようなLMSを長期的に使っていくと、動画教材の増加に伴い、料金も同様に増えていってしまいます。
しかし、etudesの場合は動画のアップロード本数や容量に制限がありません。これにより、動画教材の数や量が増えても追加料金が発生せず、長期的に安定したコストでeラーニングを運用していくことが可能です。
動画再生時の画質
先述の通り、配信する動画の画質はそのデータ量に直結します。例えば、スマートフォンの小さい画面では、SD画質の動画とフルHD画質の動画を視聴した場合、人間の目では違いを識別することが難しいです。そのため、余計なデータ量を消費しないためにも、受講者の端末に合わせた画質での視聴が重要です。
動画のデータ量は、画質×時間によって変わります。
スマホで動画を視聴した際のデータ使用量は、下記の通りです。
画質 | データ使用量(1時間あたり) | スマホプラン(7GB)での視聴可能時間 |
1080p (フルHD) | 約2.5GB | 約2.8時間 |
480p (SD) | 約500MB | 約14時間 |
1080p(フルHD)の画質で1時間視聴すると、約2.5GBものデータを消費してしまいます。そのため、スマホで視聴する場合は、480p(SD)に設定して視聴しましょう。スマホで視聴するのであれば、480p(SD)もあれば十分視聴できます。7GB制限のあるスマホプランを利用している場合、1ヶ月で約14時間の動画視聴が可能です。
これらの概算を参考に、個々の視聴環境や契約プランに応じて適切な画質で視聴するように受講者に周知しましょう。
etudesなら受講者の端末に合わせて最適な画質で動画を配信可能
LMS「etudes」なら、受講者の端末を自動的に識別し、端末に最適な画質で動画を配信するアダプティブビットレート機能を備えているため、無駄なデータ量を消費せずに、最適な視聴体験を提供することが可能です。これに対し、アダプティブビットレート機能がないLMSでは、受講者は不必要に大量のデータ容量を消費することになります。
etudesのようなアダプティブビットレート機能が搭載されているLMSなら、データ容量の有効活用と最適な画質での視聴を実現することができます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
動画教材を作成してeラーニング配信するメリット
動画教材を作成してeラーニングとして配信するメリットとして、以下の4つが挙げられます。
- LMSによって学習管理ができる
- 集合研修よりもコストがかからない
- 繰り返し視聴して反復学習ができる
- LMSの機能で飛ばし見を防止できる
それぞれのメリットについて解説していきます。
LMSによって学習管理ができる
LMSを活用することで、eラーニング教材の配信だけでなく学習管理も一元化できるというメリットがあります。eラーニングは、自分の好きな時間と場所で学習が可能なため、非常に便利です。しかし、受講者がどの教材を学習したか、どの程度理解しているかを把握するのが難しいというデメリットも存在します。この問題を解決するのがLMSです。
LMSを使用すると、管理者は受講者の学習履歴を一覧で確認することが可能になります。これにより、一人ひとりがeラーニングをどのように進めているかを正確に把握し、必要に応じたサポートや指導を提供することができます。特に動画教材の場合、視聴した部分を1秒単位で記録することが可能なため、各受講者がどの部分を理解しているか、あるいは理解が難しいかを詳細に知ることができます。
このようにLMSを使用することで、教材の効果的な活用と学習者の理解度向上に寄与することができます。
集合研修よりもコストがかからない
従来の集合研修では、研修を行う度に会場費や交通費といった費用が発生していました。
しかし、eラーニングを活用すれば、集合研修で発生していた、講師との打ち合わせの時間や会場に移動するための時間、スケジュールを調整する手間といった、時間的・人的コストも減らすことができます。
eラーニングで必要な知識をインプットすることで、集合研修の回数も減らせるためコスト削減につなげられます。
また、eラーニングなら属人化せず均質な教育が行えるため、コストパフォーマンスにも優れているといえるでしょう。
繰り返し視聴して反復学習ができる
eラーニングは受講者の理解度に合わせて研修を進められるだけではなく、動画教材を繰り返し視聴して復習する「反復学習」も可能になります。
従来の対面研修では、反復学習は難しく受講者ごとの習熟度に差が生まれる原因となっていました。eラーニングで反復学習を行うことで、わからないところをそのままにしない、より効果的な研修が実施できます。
LMSの機能で飛ばし見を防止できる
LMSによっては、学習者が動画を視聴した進捗を追跡できる機能が搭載されており、途中で飛ばし見をすることを防止できます。例えば、動画の再生状況を記録し、一定の視聴時間を超えていないと次のコンテンツに進めない設定が可能です。これにより、学習者は動画を途中でスキップすることなく、すべてのコンテンツを順番通りに視聴し、理解を深めることができます。この機能は、学習の質を向上させ、効果的な教育を実現するために非常に有用です。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
より効果的な動画教材を作成するポイント

より教育効果の高い動画教材を作成するには、適切なプロセスを踏む必要があります。作成にあたって検討すべき主なポイントは、以下の3つです。
- 理解度を確認するためのテストを実施する
- 演習問題を組み込み実践的な内容にする
- コンテンツの視聴時間に注意する
一つずつ、詳しく見ていきましょう。
理解度を確認するためのテストを実施する
どれだけハイクオリティな動画教材を作成しても、受講者がながら見をしていたり、飛ばし見をしていたりすれば、学習効果は薄れてしまいます。また、学習がインプットのみに偏ってしまうと、実践的なスキル・知識は身につきにくいでしょう。
これらの課題を解決するためには、理解度を確認するテストの実施がおすすめです。テストを行う方法はさまざまですが、一般的な方法は動画視聴後の小テスト形式です。動画の最後にテストが行われることを事前に周知しておくことで、ながら見を防ぐこともできます。
eラーニングでテストを実施する際のポイントや問題の作り方などは、以下の記事で詳しくご紹介しています。
『eラーニングで効果的にテストを行うメリットを解説!制作例をご紹介』
演習問題を組み込み実践的な内容にする
eラーニングは、集合型研修やリアルタイム研修と比べて、インプットに偏ってしまいがちです。演習問題を組み込んで実践的な内容にするよう意識して動画教材を作成しましょう。
ビジネスで役立つ思考のプロセスを実践させたり、アウトプットとしてのレポート課題の設定を行うのも効果的です。
また、eラーニングで学んだことを対面研修で実践する「ブレンディッドラーニング」を研修方法として取り入れることもできます。
インプットとアウトプットのバランスを保つことで、より高い学習効果が期待できます。
コンテンツの視聴時間に注意する
内製した動画コンテンツや講義を録画した教材は、一つひとつの視聴時間が長くなり過ぎないよう注意が必要です。長すぎるコンテンツは集中力が続かず、教育効果が失われてしまいます。
具体的には、4〜5分程度の視聴時間が最適とされています。長い講義を録画した動画教材であっても、4〜5分ごとの短いコンテンツに分割して配信するようにしましょう。
短いコンテンツを毎日視聴して学習を継続する「マイクロラーニング」も実践できます。
マイクロラーニングについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「マイクロラーニングとは?メリットやコンテンツ作りのコツを解説」
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングで動画教材を配信するなら「etudes」
「etudes」は、アップできるデータ容量とユーザー数無制限のクラウド型LMSです。
どのようなユーザーでもマニュアルなしで使える直感的なUI/UXと、豊富な学習管理機能から多くの企業に選ばれ導入されています。
クラウド型LMSでは不安視されがちなセキュリティ面においても、Microsoft Azureの高度なセキュリティシステムを採用しているため、安心してご利用いただけます。
etudesは、開発元である人材育成会社「アルー株式会社」によるeラーニング教材も配信できますが、自社で作成したオリジナル動画教材の配信にも対応しています。
eラーニング教材内製化支援も
etudesを開発したアルー株式会社は、企業内でのeラーニング教材の内製化支援を行っています。
研修のプランニングから、運用はもちろん効果測定までをトータルでサポートするので初めてのeラーニング動画作成でも安心です。
etudesは、SCORM1.2の規格に対応しているため、LMSのリプレイスにも対応できます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
本記事では、eラーニング用動画の作成方法、配信する方法、ポイントを詳しく解説しました。
動画教材の作成方法は多種多様で、オンライン会議ツールの録画機能を使う方法やパワーポイントから作る方法など状況や要件に応じて選択することが可能です。
動画教材を配信するためには、セキュリティを確保しながら提供できるLMSを利用しましょう。
LMSであれば、受講履歴を一元管理しながら企業の内部情報や独自のノウハウの流失を防げるため、セキュリティ面でも安心です。LMSを利用する際は、アップロードできる容量を確認し、スマホで視聴するユーザーがいることも考慮することも重要です。
これらを踏まえて、より高品質な教材作りを目指していきましょう。