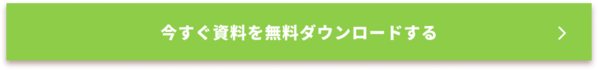eラーニングで効果的にテストを行う方法とは?メリットと出題例をご紹介
eラーニングを導入、活用した人材育成施策(スキル習得や社内研修)では、効果的にテストを実施して学習者の知識やスキルレベルを確認することが重要です。受講前後や適切なタイミングでテストを組み込むことで、より効果的にeラーニングの成果を高めることができます。
本記事では、eラーニングで実施するテストの具体例や、eラーニングでテストを実施することのメリット、eラーニングシステムを活用した運営負担の少ないテスト実施について詳しく解説します。
実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
- 1.eラーニングテストの種類
- 2.eラーニングテストの出題形式の制作例
- 2.1.1.◯✕式
- 2.2.2.択一式
- 2.3.3.複数選択式
- 2.4.4.穴埋め選択式・記述式
- 2.5.5.自由記述式
- 3.eラーニングでテストを行うにはLMSでの管理がおすすめ
- 4.テスト機能も豊富!LMS導入なら「etudes(エチュード)」
- 4.1.etudesとは?動画でご紹介
- 4.2.etudesのテスト・アンケート機能
- 4.3.etudesの修了証発行機能
- 5.eラーニングでテストを行うメリット
- 5.1.教材の理解度をすぐに確認できる
- 5.2.コスト・業務負担を軽減
- 5.3.学習者のモチベーションアップ
- 6.eラーニングのテストを作成する手順
- 7.効果的なeラーニングのテストとは
- 8.まとめ
eラーニングシステムetudesが分かる2点セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
eラーニングテストの種類
eラーニングのテストを行う際には、効果的な実施タイミングがあります。
事前に受講者の知識レベルを確認する「事前テスト」や、知識定着を測る「事後テスト」、各カリキュラム完了時に行う「理解度テスト」、研修コース修了時の集大成となる「修了テスト」などが挙げられます。
これら4種類のテストとその効果について詳しく見ていきましょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用無料・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
事前テスト
eラーニングによる研修を進める上では、受講者の前提知識を確認することが大切です。eラーニングを始める前に事前テストを実施することで、受講者が現時点での自身の知識レベルを知ることができます。
事前テストでこれを確認しておくことで、研修によってどれだけ知識が伸びたのかを把握することが可能です。さらに、「この部分に関する前提知識が抜けている社員が多かったため、次回は基礎的な内容から解説しよう」など、eラーニング研修内容のブラッシュアップにも役立つでしょう。
事後テスト
eラーニングを効果的に受講してもらうために重要なのが、受講後の知識の定着を確認する事後テストです。例えばビジネスマナー研修の事後テストでは「挨拶について」「電話応対について」など、トピックごとに区切って細かく行われます。
事後テストを行うことで、研修を受講する前の段階と比較して、受講者の知識がどれほど伸びたのかを正確に把握することができます。事前テストと同じ問題を出題して、研修による効果をより一層わかりやすくすることも可能です。
理解度確認テスト
理解度確認テストは、カリキュラムの内容ごとに実施するテストのことです。複数のeラーニングコンテンツによる学習が完了したあとに、「ビジネスマナーについて」「ハラスメントについて」など、比較的大きな枠組みで実施します。事後テストよりも出題範囲を広くし、やや難易度を上げます。実践的な思考を促す設問を含めることも効果的です。
この理解度確認テストによって、受講者は研修によって身につけた知識を改めて整理することができます。また、事後テストだけでは見えてこなかったトピックのつながりについても把握できるでしょう。教材によっては「章末テスト」といった名目で実施されることもあります。
修了テスト
修了テストは、理解度確認テストよりもさらに大きな単元にまたがって行われるテストのことです。研修によって学習したコース全体に渡って総合的な知識の確認を測ります。
出題内容が総合的であることから、「総合テスト」と呼ばれることもあります。
修了テストに合格することが、eラーニング研修完了の必須要件の一つとなるケースも多いです。また、eラーニング学習を定着させるためにインセンティブ制度を設けている企業では、修了テストの結果を判断基準とすることもできます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用無料・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングテストの出題形式の制作例

ここからは、eラーニングのテストを作成する前に知っておきたい出題形式の違いについてご紹介します。
それぞれの出題形式には難易度の差があり、出題内容によって適切に使い分けることが重要です。代表的な出題形式は以下の5つです。
- ◯✕式
- 択一式
- 複数選択式
- 穴埋め選択式・記述式
- 自由記述式
一つずつ詳しく見ていきましょう。
1.◯✕式
◯✕式は、eラーニングによるテスト出題の中でも最も手軽な質問形式です。与えられた問題に対して、内容があっているか間違っているかを選択するため、eラーニングにおけるテスト出題形式の中で最も難易度が低いといえます。問題文としては、例えば以下のようなものがあります。
「以下の内容のうち、正しいものには◯を、誤っているものには✕を記入しなさい」
シンプルで受講者も負担なく解答できる形式ですが、あまり込み入った内容までは問いきれない点に注意が必要です。
2.択一式
択一式は、複数個用意された選択肢の中から正しいものを一つだけ選んで解答してもらう出題形式のことです。正しいものを選んでもらうことが多いですが、「誤ったものを選びなさい」という出題形式もあります。択一式の出題文の一例は、以下の通りです。
「以下の選択肢のうち、正しいものを1つ選びなさい」
◯✕式と比較すると、◯✕式だけでは問いきれない細かな点にも言及できるのが特徴です。しかし、多くても4〜5個程度の選択肢の中から選んでもらうことが多いため、時には当てずっぽうの解答が当たってしまうこともあり、難易度はやや低い出題形式といえます。
3.複数選択式
複数選択式は、用意された選択肢の中から正しいものを複数個選んで解答してもらう出題形式のことです。択一式と同様、時には「誤ったものをすべて選びなさい」という形式で出題されることもあります。出題文は、以下のようなものが多いです。
「以下の選択肢のうち、正しいものをすべて選びなさい」
択一式と異なる点は、答えとなりうる選択肢をすべて選ばなければならない点です。択一式では消去法が使えますが、複数選択式の場合は正答の選択肢の個数がわからないため、消去法は使えません。択一式よりも正確に受講者の理解度を確認できるため、難易度はやや高い出題形式です。
4.穴埋め選択式・記述式
穴埋め選択式は、文章中に用意された空欄の中に当てはまる単語を選択肢の中から選んでもらう、あるいは自分で記入してもらう出題形式のことです。例えば、以下のような出題があります。
「以下の空欄に当てはまる言葉を書き入れなさい。
『廊下で上司とすれ違うときのお辞儀の角度は、( )度が目安である』」
選択肢を用意しない場合、出題者にとって予期せぬ解答が寄せられることもあるため、採点システムにおいては臨機応変な対応が求められます。
5.自由記述式
自由記述式は、受講者に解答を自由に記述してもらう形式のテストです。具体的には、以下のような出題が自由記述式に当たります。
「あなたは取引先との重要な打ち合わせに30分程度、遅刻してしまいそうです。どのような対応を取るのが適切か、200文字程度で答えなさい。」
自由記述式の出題は、出題者が自分自身で解答を一から考える必要があるため、やや難易度は高いです。採点者にも柔軟な対応が求められますが、その分受講者の理解度を正確、かつ総合的に把握することができます。
eラーニングシステムのテスト機能で自動採点を行う場合には、自由記述式は使いづらい場合がありますので、アンケート機能や提出物機能などがあるシステムを使って自由記述式のテストを行うことも一つの手法です。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用無料・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングでテストを行うにはLMSでの管理がおすすめ

ここまでは、eラーニングで行うテストの種類や形式について紹介してきました。ここからは、eラーニングでのテスト実施を効率化する「LMS」について紹介します。LMSとは、Learning Management Systemの略で「学習管理システム」とも呼ばれているシステムのことです。
LMSを導入してeラーニングと付随するテストを行うと、教材配信からテスト実施、テスト解答結果までデータを一元管理することができます。
LMSは教材をアップロードし学習者が受講するプラットフォームを簡単に作れるほか、参加のリマインドや出欠の確認など、オンラインでの人材育成やeラーニングに幅広く活用できます。
LMS(学習管理システム)のテスト機能を確認
eラーニング研修においてテストは効果測定のための重要なツールになります。LMS導入前に、システムに搭載されているテスト機能についてあらかじめ確認しましょう。代表的な機能は以下になります。
- 合格ラインを任意で設定でき、自動で合否判定ができる
- 出題ごとに配点を細かく設定できる
- テスト解答の制限時間や回数制限を決めることができる
- 選択問題だけでなく、自由記述問題にも対応している
- 提出物を管理できる
これら全ての機能を網羅しているLMSであれば、より学習効果が高いテストを実施できるでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用無料・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
テスト機能も豊富!LMS導入なら「etudes(エチュード)」
LMSは、多くのベンダーから様々な製品が展開されていますが、テストやアンケート機能が充実していて、使いやすく学習しやすいLMSをお探しなら、「etudes」がおすすめです。
etudesは企業向け人材育成において20年におよぶノウハウを持つアルー株式会社が提供しているLMSで、学習者だけでなく、管理担当者にとっても使いやすい機能を重視しています。新入社員はもちろん、幅広い年代の社員がスムーズにeラーニングを受講することができます。
アルー株式会社ならではの「オリジナル教材作成サポート」や「eラーニング学習定着支援」が受けられ、わかりやすい料金体系、大規模運用も可能な利用者数無制限といった多くのメリットによって、中小企業から大企業、省庁でも導入実績があります。
etudesとは?動画でご紹介
ではここで、etudesについて動画でみていきましょう。
エチュードについては、公式HPにてより詳しい内容を知ることができます。ぜひ一度、HPをご確認ください。
etudesのテスト・アンケート機能
etudesのテスト機能は、この記事でご紹介した出題形式(〇✕式、複数選択式など)に対応しているだけでなく、合格点の設定や試験時間、受験回数なども任意で設定可能です。
設問を作成する際には、ブログを書くような簡単な操作でブラウザから編集することができます。
もちろん、テストの結果を蓄積して受講者ごとに学習管理ができる機能も搭載されています。テストの結果および解答にかかった時間などのデータを、etudesなら過去の受験実績を全て確認できます。テストの結果は管理画面上で確認できるだけではなく、Excelデータとしての出力も可能です。
テスト結果を所属上長に共有する際も柔軟に権限設定をすることができ、etudesで直接閲覧できるため、人事部からメールなどで報告する手間も省けます。
etudesの修了証発行機能
etudesには、テストの合格点を設定し、合格した受講者に対して自動的に修了証を発行する機能も備わっています。
これによって、管理者がテストの結果を一つひとつ確認して修了証をメールで送るといった手間が省けます。etudesはテスト機能が豊富であることから、資格試験のオンライン開催などにも導入されている実績があります。
eラーニングにおいて修了証発行機能にどのようなメリットがあるかは、以下の記事で詳しくご紹介しています。
『eラーニングシステムの修了証を発行するメリットとは?選び方や事例を紹介』
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用無料・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングでテストを行うメリット
eラーニングでテストを実施することで、以下のようなメリットを得られます。
- 教材の理解度をすぐに確認できる
- コスト・業務負担を軽減
- 学習者のモチベーションアップ
それぞれ、詳しくみていきましょう。
教材の理解度をすぐに確認できる
eラーニング研修は、学習者が何度でも学習内容を復習することが可能なため、従来の対面型研修よりも知識が定着しやすくなります。一方で、理解度の深さや実務に活かせる知識が不足していないかなどの確認が重要です。
セクションごとの小テストや理解度確認テストの結果によって、受講者ごとの教材に対する理解度を確認できることが大きなメリットです。
コスト・業務負担を軽減
eラーニングシステムによってオンライン上でテストを行えば、テスト用紙の印刷や採点、集計業務といった事務作業を大幅に軽減することができます。テスト問題の差し替えや更新なども、システム上ですぐに反映できるため、研修のテスト実施にかかる負担を減らし、研修の質を高めることに集中できます。
学習者のモチベーションアップ
eラーニングを実施する際にテストを組み込めば、受講のゴールが明確になるため学習者のモチベーションを上げることができます。また、修了後にテストがあると予め伝えておくことで、より集中してeラーニングに取り組むことができます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用無料・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングのテストを作成する手順
eラーニングシステム上で効果的なテストを作成するには、以下の手順を参考にしてみましょう。
- テストの目的を明確化する
- 出題形式を決めテストの問題を作る
- eラーニングシステム上で試してから実装する
各ステップごとに、解説していきます。
テストの目的を明確化する
テストの受験は、学習者にとって心理的な負担となりやすい面もあり、目的を明示せずにテストを実施すると負担を増大させるだけで、eラーニングによる効果を正確に測定することはできません。
例えば、「学習内容の理解度を測る」「特定のスキルを評価する」「修了基準を満たしているか確認する」など、何を達成したいのかを明確に定めることが重要です。
目的が曖昧な状態でテストを組み込むと、「研修内容とテストの内容が噛み合わない」「テストの内容が不足している」といった問題が起こってしまいます。受講者のレベルや目標に応じたテスト設計を行うことで、より効果的な学習評価が可能になります。
出題形式を決めテストの問題を作る
目的が決まったら、どのような出題形式にするかを決め、テストの問題を作成します。この記事の冒頭で紹介した〇✕式問題や記述式問題など、さまざまな出題形式を選択できます。
例えば、知識の確認には選択式問題や〇✕式問題が適しており、応用力や考察力を問う場合は記述式の問題が有効です。適切な出題形式を選ぶことで、受講者がテストを通じて学習内容をしっかり理解できるようになります。
eラーニングシステム上で試してから実装する
テスト問題が完成したら、eラーニングシステム上で試験運用を行い、問題の適切性や操作性を確認します。試験運用を行うことで、問題の難易度が適切か、設問の表現に曖昧さがないか、システムの動作に問題がないかをチェックできます。
また、実際に受講者にテストを受けてもらい、フィードバックを得ることで、改善点を洗い出すことが可能です。テストの実施後には、結果の分析も重要です。受講者の正答率や解答時間を確認し、学習の定着度を測定することで、より効果的なeラーニングの活用が実現できます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用無料・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
効果的なeラーニングのテストとは
テストを作成する手順を理解したところで、続いてより学習効果が高いテストにするためのポイントをみていきましょう。
- テスト内容が妥当かつ信頼性がある
- テスト内容の問い方が統一されている
- 動画や画像を効果的に使用している
- テストを行う頻度や採点基準にストレスが無い
これらのポイントを押さえることで、初めてのeラーニングテストの導入でも失敗せずに運用することができます。
テスト内容が妥当かつ信頼性がある
eラーニングで実施するテストの内容に妥当性や信頼性がないと、学習者がテストの内容や実施の意義、eラーニングで学んだ内容そのものに懐疑的になりかねません。対面型の研修なら手を挙げてその場で質問できますが、eラーニングは個人学習となるため講義内容全体に対する信頼性が重要です。
研修で扱った内容に忠実に、研修で伝授した知識だけで十分解けるような出題をすることを心がけましょう。学習範囲外にある知識や考え方を組み込まないといった対応だけでも、テストの質は向上します。
テスト内容の問い方が統一されている
eラーニングによるテストを作成する際には、問い方を統一するように気をつけましょう。例えば、◯✕式の問題を出す際には、以下のように出題することが望ましいです。
良い例
(1)正しいものを選びなさい。
(2)誤っているものを選びなさい。
反対に、以下のように問題文が混在しているのは望ましくありません。
悪い例
(1)正しいものを選択しなさい。
(2)間違っているものを選びなさい。
(3)誤っているものはどれか。
問題文を作成する際は、同じ質問内容は同じ文章で問うなど、受験者に余計な迷いを生じさせないように注意をはらいましょう。
動画や画像を効果的に使用している
eラーニングのテストでは、テキストだけでなく動画や画像を活用することで、より高い学習効果が期待できます。視覚的な情報は、学習者の理解と記憶の定着を促進します。特に、文章だけでは伝わりにくい概念や手順を説明する場合、動画や画像を用いることで直感的に理解しやすくなります。
例えば、製造業の技術研修では、作業の流れを動画で示した後に、「この工程で注意すべき点は?」といった問題を出すことで、より実践的な理解を促せます。また、動画の一部分を空白にして、「この後に続く作業は?」と問いかけるようなクイズ形式の問題を用いることで、考えながら学習する習慣を身につけられます。
このように、学習内容に応じて適切なビジュアル要素を取り入れることで、学習者が実際の場面を想像しやすくなり、知識の応用力も向上します。
テストを行う頻度や採点基準にストレスが無い
eラーニングによるテストの実施は確かに効果的ですが、一方で先述したように学習者にとっては負担がかかることも事実です。頻繁にテストを行うと学習者にとって重要性が薄れ、モチベーションが下がる恐れがあります。
また、採点基準が曖昧なことで、「どうしてこの回答は◯なのに、こちらの記述は✕なのか」「採点者がよくわかってないのではないか」といった疑念を抱かれてしまいます。eラーニングによるテストを実施する際は、頻度や採点基準にストレスがないように気を配りましょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用無料・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
eラーニング研修でテストを行うメリットや出題形式の例、より効果的なテストを作成するポイントなどについて解説しました。
eラーニングはいつでもどこでも学習ができる画期的な学習方式ですが、学習成果を数値的に確認した上で、研修実施後にフォローアップすることが極めて大切です。
また、eラーニングによるテストを作成する際には、受講者にとってストレスとならない問題文や頻度を設計することも求められます。ぜひこの記事の内容を参考にして、本当に効果的なeラーニングテストを実施しましょう。
eラーニングでのテストを行う際には、便利なLMSを活用しましょう。LMSは、アルー株式会社が提供している「etudes」がおすすめです。etudesについて分からないことがある方は、ぜひお気軽にアルー株式会社までお問い合わせください。
アルー株式会社に問い合わせる