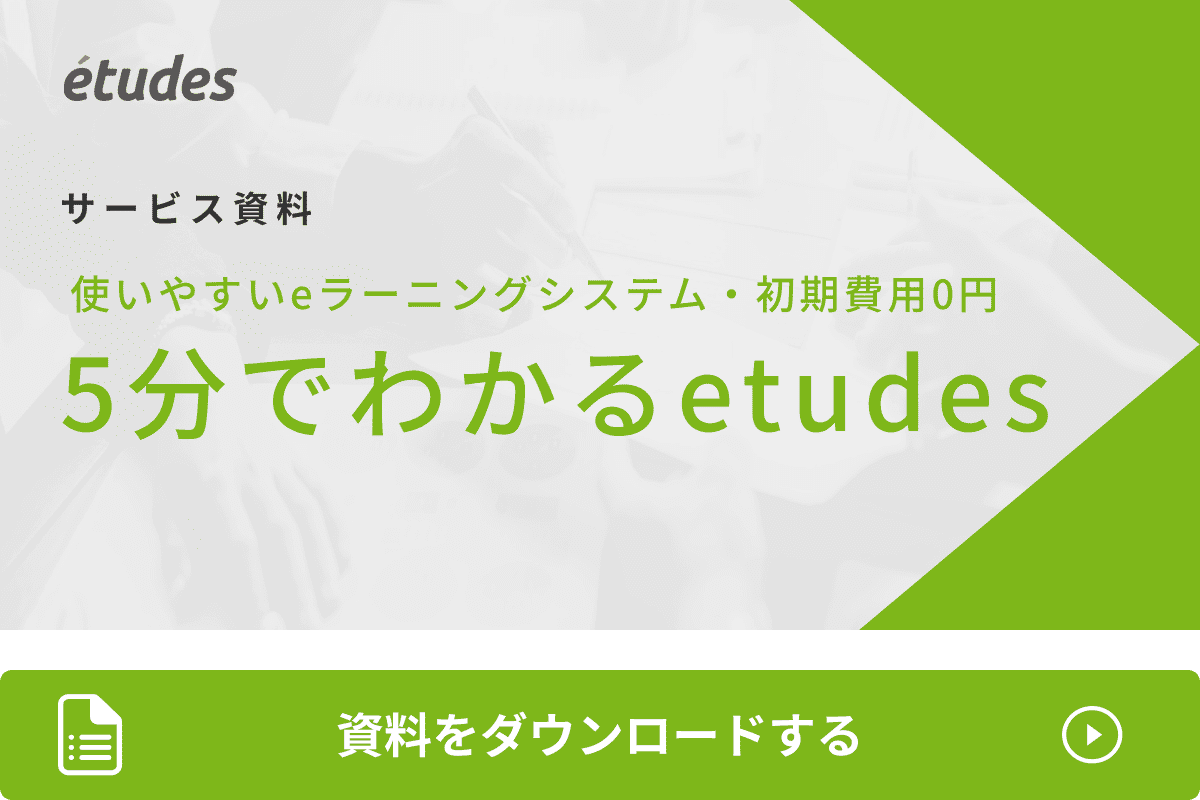ナレッジマネジメントツールの選び方・運用の注意点とは?
ナレッジマネジメントツールは、社員一人ひとりがもつ知識や経験を社内に共有するためのツールです。しかし、ツールを導入しただけでは、ナレッジマネジメントの成功にはつながりません。
この記事では、ナレッジマネジメントの基本情報と共に、ナレッジマネジメントツールの活用方法や、よくある失敗例から分かる活用のコツなどをご紹介します。
実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは、「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
- 1.ナレッジマネジメントツールとは
- 2.ナレッジマネジメントツール導入のメリット
- 2.1.ナレッジ・ノウハウの一元管理ができる
- 2.2.人材育成の効率化・属人化防止
- 2.3.ナレッジの検索機能で手間を削減
- 3.ナレッジマネジメントツール導入のデメリット
- 3.1.1.導入にはコストがかかる
- 3.2.2.定着するまでの労力がかかる
- 4.ナレッジマネジメントツール導入でよくある失敗例
- 4.1.共有されたナレッジをどのように活用すればいいか分からない
- 4.2.ツールの使い方がわからない・面倒
- 4.3.ルールが設けられておらず、整理できない
- 4.4.社員のナレッジマネジメントに対する理解不足
- 5.失敗例から学ぶ、ナレッジマネジメントツール活用を成功させるコツ
- 5.1.ナレッジマネジメントの有用性を伝える
- 5.2.ナレッジを共有することによるメリットを作る
- 5.3.完成された資料だけでなく、途中のプロセスも共有する
- 5.4.スモールスタートで成功体験を作る
- 5.5.運用体制・ルールを整えてから導入する
- 6.ナレッジマネジメントを成功させるにはLMSの活用もおすすめ
- 7.LMSを活用した効率的なナレッジマネジメント
- 8.成功事例からわかるナレッジマネジメントの課題をLMSで解決させる活用術
- 9.ナレッジマネジメントツールの選び方
- 10.使いやすいLMSなら「etudes」
- 10.1.使いやすく誰でも分かりやすいUI/UX
- 10.2.Microsoftによる高度なセキュリティ
- 10.3.eラーニング教材の作成サポート
- 11.まとめ
eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
ナレッジマネジメントツールとは
ナレッジマネジメントとは、企業や社員が独自に蓄積した知識・ノウハウなどの暗黙知を、誰にでもわかるようにマニュアル化し形式知にすることです。それをサポートするツールが「ナレッジマネジメントツール」です。
ナレッジマネジメントにおけるナレッジ(knowledge)とは、知識や情報、知見を指します。ビジネス上では、文章から得られた知識だけではなく、実体験で得られたノウハウ・経験なども含めて、ナレッジと呼ばれています。
現在、企業や個人が独自に蓄積したナレッジつまり「暗黙知」を、「形式知」にする動きが加速しており、さまざまな企業がナレッジマネジメントツールを導入しています。
ナレッジマネジメントという取り組みについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
『ナレッジマネジメントとは?意味・考え方から導入のポイントまで解説』
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用無料・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントツールは4種類
ナレッジマネジメントツールは、用途や特徴ごとに以下の4種類に分けられます。
手法 | 内容 |
① 専門知識型 | ヘルプデスク向け。社内で出た問い合わせを記録し、問い合わせ業務の時間削減をする |
②業務プロセス型 | 顧客への対応手順や業務プロセスを共有する。コールセンターなどに向いている |
③ベストプラクティス共有型 | 優秀な社員の行動パターンなどを分析して共有する。暗黙知を形式知として共有することで、社員全体の能力の底上げになる。営業職や技術職で活用される。 |
④経営資産・戦略策定型 | 成功事例をさまざまな角度から解析して、形式知とするもの。ナレッジの解析を主としており、業務プロセスの全体を調べて改善点を洗い出せる。 |
ツールを導入する際には、どの手法でナレッジマネジメントをするのかを明確にし、最適なツールを導入することが重要です。
ナレッジマネジメントツールの機能
ナレッジマネジメントツールには、効果的なナレッジマネジメントを実現するために、以下のような機能が搭載されていることが多いです。
機能 | 内容 |
FAQ | 社内の質問に対して、従業員同士で回答できる機能 |
ファイル共有 | プロジェクトで活用しているドキュメントなどを整理し、最新バージョンを確認できる機能 |
マイニング・検索 | 検索エンジンを利用し、データを発見しやすくする機能 |
eラーニング | 集まったナレッジをeラーニング教材にして、社内のOJTや研修などに活用できる機能 |
社内SNS | コミュニケーションを通じてナレッジのシェアができる機能 |
どのようにナレッジマネジメントを進めていくかによって、必要なツールの機能は変わります。例えば、営業の知識やノウハウを共有するタイプであれば「ファイル共有」で営業資料を共有し、事例別に「マイニング・検索」ができるツールを選ぶ必要があるでしょう。
また、集まったナレッジを研修に活用したい場合には、eラーニング教材を管理できる機能があるツールを選ぶなど、自社の目的やゴールに合わせて選定していきましょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用無料・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントツール導入のメリット
ナレッジマネジメントツールの活用により、一層効果的なナレッジマネジメントを行うことができます。
ナレッジマネジメントツール活用の主なメリットは、次のとおりです。
- ナレッジ・ノウハウの一元管理ができる
- 人材育成の効率化・属人化の防止
- ナレッジの検索機能で手間を削減
以下にて、詳しく内容を見ていきましょう。
ナレッジ・ノウハウの一元管理ができる
収集したナレッジやノウハウを活用する際には、情報を統合して一元管理できるようになっていなければなりません。
例えば、営業資料は個人のPCで管理する人もいれば、CRMなどで管理する人もいるなど、ナレッジをバラバラな方法で管理している場合は、収集や活用に手間がかかります。
ナレッジマネジメントツールは、このような統一性のないナレッジを一元管理し、分析や活用を容易にします。
人材育成の効率化・属人化防止
ナレッジマネジメントツールを活用することで、人材育成の効率化が図れる点も、メリットの一つです。
経験豊富な社員のスキルやノウハウを、ツールを使って共有することで、中途社員や新入社員の育成に活用でき、社員の即戦力化が期待できるでしょう。
また、特定の業務が属人化してしまい、その人が居なければ仕事がまわらない、退職や異動によって業務の質が落ちてしまう、という事態も防ぐことができます。
ナレッジの検索機能で手間を削減
ナレッジマネジメントが順調に進むと、各社員の持つ知識やノウハウ、経験などの情報が蓄積されていきます。それらを有効活用するためには、ツールの活用が必須です。ナレッジマネジメントツールを用いることで、データの収集、集計、検索等の効率化を図ることができます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用無料・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントツール導入のデメリット
ナレッジマネジメントを効率化させるツールにも、デメリットがあります。ここでは、ナレッジマネジメントのためのツールを導入するデメリットを2つご紹介します。
- 導入にはコストがかかる
- 定着するまでの労力がかかる
以下にて詳しく見ていきましょう。
1.導入にはコストがかかる
ナレッジマネジメントツールの導入には、コストがかかります。
導入の際の費用だけでなく、維持費・月額利用費などのランニングコストも必要です。無料で使えるツールの活用を検討したり、自社のナレッジマネジメントの目的により適合したツールを選定したりすることで、無駄なコストを抑えて利用することができるでしょう。
ナレッジマネジメントは、暗黙知を形式知に変換することが目的ですが、これを嫌う社員が出てくる可能性があります。
例えば、成果を出さなければならない営業などの業務は、自分の成果につながるノウハウを他人と共有したくないと考えることもあるでしょう。また、ベテラン社員は業務が忙しく、ナレッジの共有に時間をかけたくないかもしれません。
そのため、ツールの導入前にナレッジマネジメントの必要性を理解してもらう必要があります。
2.定着するまでの労力がかかる
ナレッジマネジメントツールだけでなく、企業で活用するツールに共通する課題ですが、ツール導入は、最終的なゴールとして「ツールの定着」がスムーズに進むかどうかが重要なポイントです。定着しなければ有効に活用することはできません。
ツールを導入しただけでは、社員全員が自発的に周囲に必要なナレッジをシェアし、適切に利用することは難しいでしょう。
そのため、ナレッジマネジメントツールの導入時には利用方法の研修などを実施し、導入後も活用方法を共有するなど、社員に対して繰り返し教育や働きかけを組織側からする必要があります。また、ナレッジマネジメント推進の担当者を設けて、ナレッジマネジメントの有効性やツールの使い方を伝えていくことが重要です。
また、社員の中にはナレッジを共有すること自体に抵抗を感じる方もいるかもしれません。事前に、なぜナレッジマネジメントを行うのか、どのような意図があるのかを全社員に周知しておきましょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用無料・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントツール導入でよくある失敗例
ナレッジマネジメントツールを導入しただけで、ナレッジマネジメントが自動的に進むわけではありません。社員にツールの使い方を浸透させ、一定のルールに則ってナレッジを蓄積し、それを分析・活用しなければツール導入は失敗してしまうでしょう。
ここでは、ナレッジマネジメントツール導入の際に知っておきたい、よくある失敗例をご紹介します。
共有されたナレッジをどのように活用すればいいか分からない
ナレッジマネジメントツールに共有されたナレッジが、全ての業務にフィットし、そのまま活用できるわけではなく、一定の応用が必要になります。
シェアされているナレッジを理解した上で、現場での課題にどのように当てはめ、活用することができるのかを考える必要があります。
しかし、社員にデータを読み取る力や、実務に活用するための適切なプロセスを踏むためのスキルや経験がないと、「ただデータが蓄積されていくだけで、活用されない」という事態になりかねません。
そのため、ナレッジの共有に当たっては、単なる知識を集約し、公開するだけでなく、実務に活かせるポイントや、活用のためのプロセスまで含めてシェアすることが必要です。
ツールの使い方がわからない・面倒
ナレッジマネジメントツールの導入でよくあるのが、ツールの使い方が分からない、操作が面倒ということです。
そのため、ナレッジマネジメントツールの導入前には準備が必要です。最初から全てのノウハウをツールで一元管理するのではなく、まずはヘルプデスクだけのノウハウを入れていくなど、スモールステップで導入することが大切です。
また、使い方に関する研修を実施しても良いでしょう。実際に使用している画面を録画して教材化したり、マニュアルを作成して誰でも使えるように環境を整えることが大切です。
ルールが設けられておらず、整理できない
ナレッジマネジメントでは、ナレッジの蓄積も大切ですが、蓄積されたナレッジを分析・活用できるかどうかが重要です。
膨大なナレッジがシェアされる場合に形式が不揃いだと、整理が出来ず、検索もしづらい状況に陥ってしまいます。
そのため、ナレッジマネジメント導入の前に、実行可能な運用のルールを策定し周知・徹底させることが大切です。
社員のナレッジマネジメントに対する理解不足
社員にナレッジマネジメントの知識が不足していると、
「なぜ自分のノウハウを、他の人に教えなければならないのかわからない」
「自分の持っているノウハウは、重要ではないので関係ない」
などと思われてしまい、ナレッジを蓄積しづらい状況になってしまいます。
そのため、ツール導入前にナレッジマネジメントの重要性やメリットを理解してもらうための研修を行うことがおすすめです。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
失敗例から学ぶ、ナレッジマネジメントツール活用を成功させるコツ
ナレッジマネジメントツール活用の失敗例をご紹介しましたが、ではどのように活用すれば、ナレッジマネジメントを成功させることができるでしょうか。
ここでは、ナレッジマネジメントツールの活用を成功させるコツについてご紹介します。
ナレッジマネジメントの有用性を伝える
上述しましたが、ナレッジマネジメントツールを使う前に、ナレッジマネジメントの有用性が理解されていなければ、取り組みが形骸化してしまいます。
まずはナレッジマネジメントの効用について理解を深めるために、研修を実施しましょう。他社のナレッジマネジメントの成功事例などを周知させると、有用性が伝わります。
ナレッジマネジメントの事例に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
『ナレッジマネジメントの成功事例とよくある失敗事例を解説』
ナレッジを共有することによるメリットを作る
ナレッジを共有するための言語化や図式化、ツールへの入力作業は、社員にとっては負担となります。そのため、ナレッジを共有することによるメリットを明確化しましょう。例えば、評価制度につながる仕組みにする、共有した社員にポジティブなアクションを行うなど、「ナレッジを共有したことでメリットがあった」と思える仕組みづくりが大切です。
完成された資料だけでなく、途中のプロセスも共有する
ナレッジマネジメントツールに共有される資料は、作成者が最終的にアウトプットしたものです。しかし、資料を見る人たちが本当に知りたいのは、作成者が考えたこと、調べたこと、悩んだこと、失敗したことであり、完成された資料だけでは不十分です。
これらの、隠されている作成途中のプロセスを共有することで、ナレッジマネジメントの成果が出やすくなるでしょう。
ただし、全ての資料に作成過程を掲載すると、共有する社員の負担が増えてしまいます。特に重要で効果のあるナレッジに絞り込んで、思考プロセスや活用の事例をマニュアルのようにまとめると良いでしょう。
文章を読み込むタイプの資料に限らず、動画などの形式を採用することも効果的です。
スモールスタートで成功体験を作る
最初から全ての情報をナレッジマネジメントツールに取り入れようとすると、多くの手間が掛かります。
まずは部署をしぼるなどして小さくはじめ、成功体験を作ることが大切です。
例えば、営業部門でナレッジマネジメントをはじめることにより、新入社員が受注できた、などの小さな成功事例を作り、それをもとに他部署にも展開していくと良いでしょう。
運用体制・ルールを整えてから導入する
ナレッジマネジメントツールの活用の失敗要因としては、運用体制やルールが未整備で、形式が不揃いであることだとお伝えしました。
このような事態を防ぐため、ナレッジマネジメントツールの導入前に、形式や共有方法のルールを決め、検索・整理がやりやすくなるようにしておきましょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントを成功させるにはLMSの活用もおすすめ
ナレッジマネジメントツールを導入して効果を発揮させるには、ツールの操作性や運用の仕組みづくりも必要ですが、一番に必要なのは共有されたナレッジをどのように活用すればいいかをイメージすることです。
ナレッジの活用方法をイメージさせるには、LMSの活用がおすすめです。
LMSはLearning Management Systemの略で、学習管理システムとも呼ばれるツールです。LMSでナレッジマネジメントの必要性や活用方法を共有することで、蓄積されたナレッジをどのように活用するかのイメージが湧きやすく、社員はナレッジマネジメントツールを効果的に使うことができるでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
LMSを活用した効率的なナレッジマネジメント
ナレッジマネジメントに使えるツールは、「ナレッジマネジメントツール」として特化したものがあります。
しかし、
- ナレッジマネジメントだけではなく、社内研修にも使えるツールを導入したい
- eラーニング研修を通じてナレッジを共有したい
といった要望がある場合は、学習管理システム「LMS」を導入することがおすすめです。
LMSはLearning Management Systemの略で、学習を管理する機能が搭載されたシステムです。
LMSは、企業のeラーニング研修に使われることが多いツールですが、
- 教材の保管・蓄積
- 社員のアカウント化と部署ごとのグループ化
- アカウントやグループごとに教材を自動で配信
- アカウントごとの学習進捗管理
といった機能を有していることから、ナレッジマネジメントにも活用できます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
成功事例からわかるナレッジマネジメントの課題をLMSで解決させる活用術
では、ナレッジマネジメントの課題をLMSで解決するには、どのようにLMSを使うのが良いでしょうか。
ここでは、課題を解決した事例をもとに、LMSの活用術をご紹介します。
新しいアイデアを生み出す事前学習としてLMSを活用した例
A社では、同じテーマで作成された資料を、事前にeラーニングで社員に読んでもらいました。
その後、集合型研修の中で資料作成者と情報を必要としている社員が、ブレインストーミングを行い、事前学習してきた社内ナレッジをベースに、質疑応答やワークショップを行いました。
その結果、これまでのナレッジから新しいアイデアが創出され、業務の効率化や社員のスキルアップにつながりました。
ナレッジマネジメントツールのデータを教材化した例
B社では、ナレッジマネジメントツールにアップロードした多くの資料のURLを、LMSでeラーニングコースとしてまとめ、他の社員と共有しました。
教材化の際には、テーマに応じて知識を実践的に活用しやすくし、コースの最後に実例を載せて、活用のイメージがつくように工夫しています。
ナレッジマネジメントツールを、単なるナレッジを蓄積するだけのツールから、蓄積したデータを人材教育に活かすツールへと、有効活用することができています。
社員全員が講師となるナレッジ共有にLMSを活用した例
C社には、従来より階層や職種を問わず社員同士で学び合う文化がありました。それぞれの社員が持っているナレッジに、よりアクセスしやすくなるよう、同社はLMSをナレッジマネジメントの一環として導入しました。
管理者権限の多様な設定が可能なLMSを採用したことによって、誰もが自分で教材を作成し掲載できる環境構築に成功しました。
詳しくは、以下の事例紹介からご確認ください。
etudes導入事例_「社員全員」が教育コンテンツを作成・配信し、学び合える環境を構築
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントツールの選び方
ナレッジマネジメントツールを選ぶ上で、重視しなくてはならないポイントをご紹介します。
- 無料トライアルはあるか
無料トライアルがあれば、実際の操作性などを確認できます。社員によってツールに対するリテラシーは異なりますので、誰もが使いやすい操作感かどうかを重視しましょう。
- スマホやタブレットからアクセスできるか
ツールによっては、パソコンからしかアクセスできないものがあります。社員が、移動時間にナレッジを学んだり、現場での作業中にナレッジを確認したい状況でも利用できるよう、スマホやタブレットなどのデバイスにも対応しているツールを選びましょう。
- 利用者数の制限は無いか
ナレッジマネジメントの対象者は、全社員です。グループ会社や子会社なども含めると、大人数が活用するツールとなります。導入前に、使用者数の制限の有無を必ず確認しましょう。
上記の条件を全てクリアしたLMS「etudes(エチュード)」をご紹介します。
使いやすいLMSなら「etudes」
ナレッジマネジメントにも役立つLMSを選ぶ際は、全ての社員にとっての使いやすさを重視すべきです。
アルー株式会社では、誰でも使いやすいLMS「etudes」を提供しています。
ここでは、「etudes」の特徴をご紹介します。
使いやすく誰でも分かりやすいUI/UX
etudesの特長は、マニュアルなしでも直感的に使いやすいUI/UXであることです。
受講者は、コースの詳細画面の上から順にコンテンツを受講すればよいだけなので、操作に迷うことがありません。
トップページは、アイコンやバナーなどを自由に変更できるので、社員の持つ課題に対して、最適な教材をすぐに選ぶことが可能です。
また、管理者が学習プラットフォームとしての画面を構築する際にも、パネルを移動させるような簡単な操作でデザインを作成できます。etudesは、管理者、受講者双方にとって使いやすいLMS機能を実現しています。
Microsoftによる高度なセキュリティ
eラーニング教材は、自社のノウハウや社外秘の情報を載せることも多いため、セキュリティ対策は必須です。etudesでは、Microsoft Azureの高度なセキュリティシステムを採用しています。
そのほかにもetudesは、ユーザー認証やDDoS攻撃への対策、WAF、IPSなど、あらゆる情報漏洩リスクを想定した、高度なセキュリティ機能を備えています。これにより、企業の重要な情報資産を守ります。
eラーニング教材の作成サポート
ナレッジマネジメントを進める上では、自社で蓄積されたナレッジを活用できる形に整理しなければなりません。ですが、情報を整理して社員が分かりやすい形の教材にするには、ノウハウが必要です。
アルー株式会社は、約20年に渡って人材に対する研修を行ってきました。社内教育の質の向上のために必要なノウハウを活用して、教材作成の支援を行っています。
また、etudesの利用を開始後、社内に定着して効果を発揮するまでをサポートする企業内教育コンサルティングも行っています。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
ナレッジマネジメントの成功は、導入するナレッジマネジメントツールに左右されます。
ナレッジマネジメントツール導入のメリットを把握し、どのツールが自社に合っているのかを見極める必要があります。導入の際には、その意図を社員に理解してもらい、事前に運用体制を整えておくことを忘れないようにしましょう。
ナレッジマネジメントツールは、導入するだけではなく、運用の仕組みづくりも必要です。ナレッジマネジメントツールで蓄積されたデータを整理し、有効活用できるように、LMSを用いてナレッジマネジメントの使い方を周知しましょう。
etudesであれば、さまざまな企業の要望に合わせることができ、質の高い教材作成のサポートも受けられます。教材の質の高さ次第で、ナレッジマネジメントの成果が変わるため、LMSを選ぶならぜひetudesをご検討ください。
etudesの詳しい製品紹介を知りたい方は『製品紹介資料』をダウンロードしてください。etudesの特徴やデモ画面、費用についてご紹介しています。