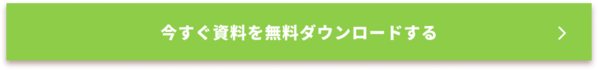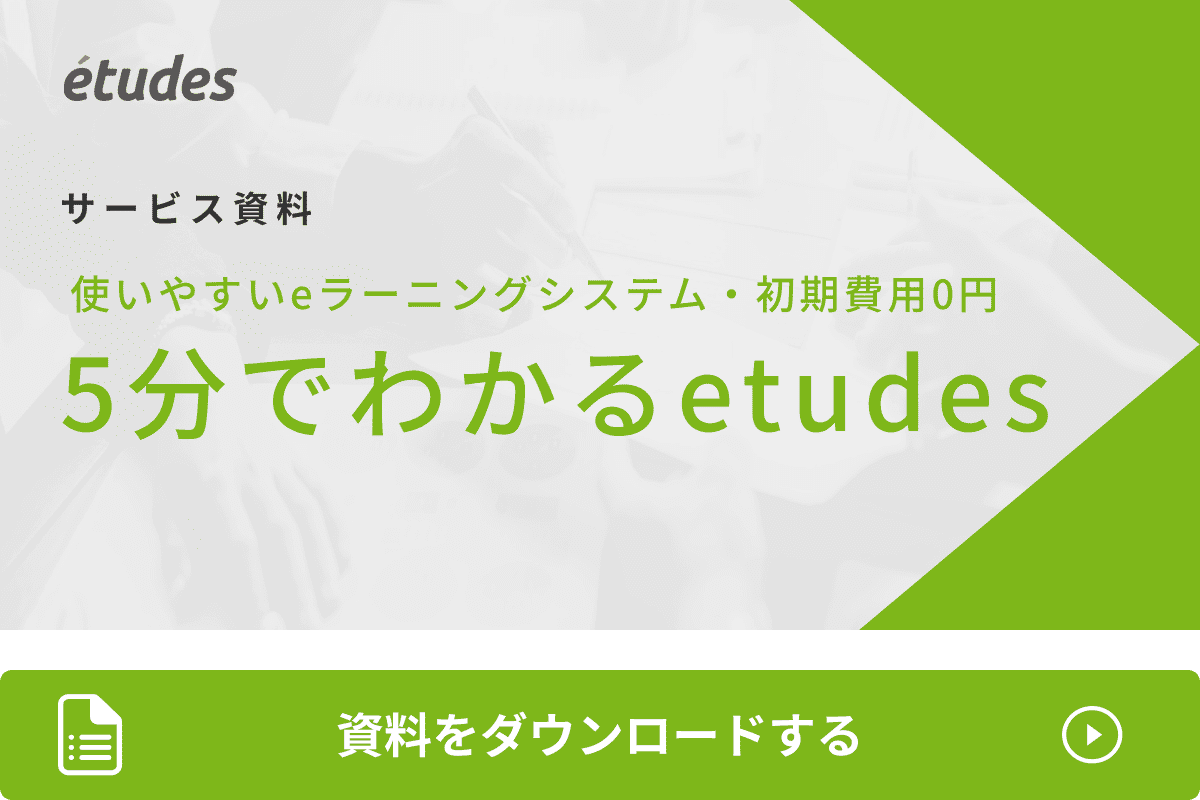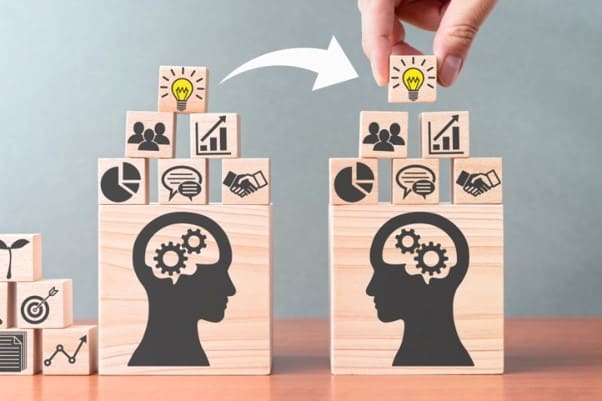
ナレッジマネジメントの成功事例とよくある失敗事例を解説
ナレッジマネジメントを導入したものの、「重要性の理解が得られなかった」「運用ルールが機能していなかった」などの理由により導入に失敗する企業が多く見られます。
一方で、ナレッジマネジメントの導入に成功した有名な企業も数多くあります。自社でのナレッジマネジメント導入を成功させるには、このような事例をきちんと知っておくことが大切です。
この記事では、ナレッジマネジメントを導入した企業の実際の事例について詳しく解説しています。
実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
- 1.ナレッジマネジメントとは
- 1.1.ナレッジマネジメント導入の効果
- 2.企業におけるナレッジマネジメントの成功事例7つ
- 2.1.富士フイルムビジネスイノベーション
- 2.2.NTT東日本法人営業本部
- 2.3.キーエンス
- 2.4.富士ゼロックス
- 2.5.チェンフー
- 2.6.磨き屋シンジケート
- 2.7.国土交通省
- 3.ナレッジマネジメントのよくある失敗事例とその解決策
- 4.ナレッジマネジメントツールが使いこなせない
- 5.ナレッジマネジメントの必要性が伝わらず失敗
- 6.運用のルールが設定されておらず失敗
- 7.ナレッジマネジメントを成功させるポイント
- 8.ナレッジマネジメントに役立つツール
- 8.1.社内wiki・データベース
- 8.2.SFA
- 8.3.FAQ
- 8.4.LMS
- 9.eラーニングによるナレッジマネジメントとは
- 9.1.ノウハウやナレッジをeラーニング教材化
- 9.2.教材の蓄積・配信
- 9.3.LMSによる学習管理も
- 10.eラーニングなら「etudes(エチュード)」
- 11.まとめ
eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
ナレッジマネジメントとは
仕事をするにあたって、企業やその社員は知識や経験、ノウハウなどを積んでいきます。仕事を続けることにより得た知識などのことを暗黙知と呼びますが、この暗黙知を企業全体で共有をして、経営に活かしていく手法のことをナレッジマネジメントと呼びます。
つまり、企業やその社員が持っている有益な情報を、企業がまとめて管理をし、有効的に活用するということです。
なお、ナレッジ(knowledge)とは、知識や情報、知見などのことを指します。ビジネスでは、文章から得られた知識などのことだけではなく、体験をすることで得られた知識や経験なども含め、ナレッジと呼んでいます。
また、暗黙知の対義語として形式知があります。形式知は、誰もが言語化、資料化することができるものを指します。暗黙知を形式知に変えることが、ナレッジマネジメントの目的の一つです。
ナレッジマネジメント導入の効果
ナレッジマネジメントを導入することにより、さまざまな効果が期待できます。
- 人材教育や育成の効率化
- 人材教育や育成は、育成する人の能力や、育成システムにより大きく差がつきます。この差を無くし、より効率的な人材教育をおこなうことができます。
- サステナビリティの実現
- 暗黙知を持った社員が退職してしまうと、その退職者によって防がれていたクレームや事故などが再度起きてしまいます。このようなことにならないよう、社員の暗黙知を形式知に変えることにより、企業として持続可能となりサステナビリティが実現します。
- 新たなナレッジの取得
- 知識が集まることにより、新たな知識が創造されていきます。ナレッジマネジメントには過去の知識をまとめることだけではなく、これからの知識とノウハウを作り出すことも含まれるのです。
- 業務改善の効率化
- ナレッジマネジメントができていないと、特定部署のみに知識が蓄積される場合があります。これを共有化することにより各部署での業務改善につながります。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
企業におけるナレッジマネジメントの成功事例7つ

業務効率を上げたり、さらなる売上を出すためにナレッジマネジメントを導入し、成功した企業は数多く存在します。
ここからは、ナレッジマネジメントを導入し成功を収めた企業を数社ピックアップし、成功事例などを紹介します。
富士フイルムビジネスイノベーション
最初に紹介させていただくのは、富士フイルムビジネスイノベーションの「何でも相談センター」です。
富士フイルムビジネスイノベーションでは、「何でも相談センター」を企業内に設置し、社員の仕事上の相談を受け付け、相談があった内容は社内をたらい回しにせず、必ずダイレクトに回答をするという取り組みをしています。
この取り組みにより、社員が仕事上の壁に直面したときどのように乗り越えたらいいのか、またそれをどのように解決したら良いのかという知識が蓄積されていきます。こうして、業務時間の大幅短縮、業務の質の向上などの成果が上がっています。
NTT東日本法人営業本部
NTT東日本法人営業部では、オフラインとオンラインともにナレッジマネジメントを導入、運用し業務改善に成功しました。
オフラインとオンラインの施策をそれぞれ見ていきましょう。
- オフラインでのナレッジマネジメント運用
「ベースゾーン」「クリエイティブゾーン」「コンセントレーションゾーン」「リフレッシュゾーン」などをオフィスに導入し、暗黙知から形式知へとナレッジ共有しやすい環境を構築しました。その結果、普段は交流のない部署同士のコミュニケーション増加を促すことに成功しました。 - オンラインでのナレッジマネジメント運用
営業本部に所属する全員が個人のホームページを持ち、プロジェクトの記録などの暗黙知を形式知へ変換し、他の社員へナレッジ共有するシステムを導入しました。システムの導入により、個々の培った知識や経験を他の社員と共有することに成功しました。
キーエンス
キーエンスでは、ナレッジマネジメントを実施しても成功しづらいとされている営業部門において、インセンティブ制度を導入することによって成功しました。
営業は組織内での競争があるため、営業同士が知識やノウハウを伝えるという意識が希薄です。そのため、「ナレッジマネジメントを導入する」という指示だけでは、ナレッジマネジメントは浸透しません。
そこで、人事評価と共にナレッジマネジメントのインセンティブ制度を確立し、人事評価5、ナレッジ共有5という割合での評価にし、ナレッジマネジメントの導入に成功したのです。
富士ゼロックス
ナレッジマネジメントの導入率は日本一とも言われている富士ゼロックス。「全員設計」というコンセプトのナレッジマネジメントを取り入れることによって業務効率改善に成功しました。
富士ゼロックスでは、商品の最終設計段階になると、設計調整が入りたびたび納期が遅れるという事態が起きていました。これは、商品の段階ごとの設計者の意見を取り入れていくようにしていたため、最終設計者は最終段階でしか設計変更を申し入れられなかったのが原因でした。
このような事態を解消すべく設計者が全員、初期段階から参加し打ち合わせ内容を記録する独自のシステムを開発し、運用を開始しました。その結果、設計段階ごとの連結化に成功し、業務効率の改善につながっていきました。
チェンフー
チェンフーはシンガポールに本社を置く、観賞魚を輸出する企業です。チェンフーは養殖事業の失敗を契機として、ナレッジマネジメントの導入検討を開始しました。
当時、チェンフーでは社員の移動が多く、社内システムにアクセスすることが難しいという課題がありました。
その結果、暗黙知が増えてしまったため、これを改善すべく社員のナレッジを共有するシステムを導入しました。結果として、社員のスキルや知識だけでなく顧客へのサービスレベルや事業生産性、売上や利益率も向上することに成功しました。
具体的には、魚の検疫と袋詰めのマニュアルが完成したことにより、商品到達時に魚がどれだけ死亡するのかという、死亡率の低減などに効果をもたらしました。
磨き屋シンジケート
磨き屋シンジケートとは、金属洋食器加工で有名な新潟県燕市にある、燕商工会議所が主催する金属加工の共同受注組織です。
磨き屋シンジケートは、格安の海外金属洋食器におされ、海外洋食器の下請け金属加工業となることに危機感を覚えていました。そのため、ナレッジマネジメントを導入し、地位改善を目指しました。
受注面では、顧客窓口、製造管理、品質管理などを担当する企業があり、別々の業務を担当していました。この別々の業務の連携を強化することにより、受注から納品までのプロセスマニュアルが完成し、受注から納品までの時間コスト削減などに成功します。
技術面では、それぞれの職人の技を共有化することにより製品の質の向上にも成功しています。その他にも、職人同士の交流が活発化し、生産モチベーションの向上、職人それぞれの技術の高いレベルでの標準化なども達成しました。
国土交通省
ナレッジマネジメントは、行政機関でも取り入れられています。
国土交通省では、災害があった際に職員が正しく判断し行動をするためのノウハウを広く伝承するという課題がありました。そこで、ナレッジマネジメントの手法を採用し、検索しやすく編集も容易なイントラネット用ブログツールを活用しました。
これによって、職員ごとにバラバラだった防災知識を均一化することで、迅速かつ的確な対応が可能となっています。
また、職員の中で経験に差があっても、効率的に教育ができるというメリットもあります。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントのよくある失敗事例とその解決策

ここまでは、ナレッジマネジメントの導入に成功した事例を紹介してきました。
しかし、成功事例があるのであれば、失敗事例も数多く存在します。失敗事例に関しては、失敗する傾向が似通っています。導入前に知っておくことで、失敗のリスクを回避することができるでしょう。
ここからは、ナレッジマネジメントを導入しようとしたが、失敗したというありがちな失敗事例を紹介します。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントツールが使いこなせない
ナレッジマネジメントの導入に失敗してしまった事例の1つ目は、ナレッジマネジメントツールの使い方が浸透しなかったケースです。
社員がナレッジマネジメントツールを使いこなせない原因として、以下のような理由が考えられます。
- はじめから全社的にシステムを採用したが、使いこなせなかった
- 社員にとって入力作業が面倒だった
ナレッジマネジメントツールは適切な規模、内容で運用を開始することが大切です。
それでは、ナレッジマネジメントツールが使いこなせないという失敗事例はどのように防げばよいのでしょうか。
ポイント・まずは一部署から徐々に規模を拡大
ナレッジマネジメントツールが使いこなせない、という失敗を防ぐためには、まず、一部の部署から徐々に規模を拡大することが大切です。
いきなり全体にツール使用を命じてしまうと、反感が表立ちやすいですが、ツール導入の必要性が高い部署から運用を開始していきナレッジマネジメントツールの必要性を社内に少しずつ広めていくのが良いでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントの必要性が伝わらず失敗
ナレッジマネジメント導入の失敗事例の2つ目は、ナレッジマネジメントそのものの必要性が伝わらず失敗することです。
このケースにもさまざまな理由が考えられます。
必要性がうまく伝わらないのは、ナレッジマネジメントのシステムとツールの使い方だけが説明され、共有のための作業を社員に強要してしまうというケースが多いです。
必要性が感じられないと「社内のライバルに知識・ノウハウを知られたくない」「通常業務が忙しくナレッジマネジメントに対応できない」といった声が上がるときがあります。
このような場合は、ナレッジマネジメントの導入前に社員に対して、ナレッジマネジメントの必要性を正しく伝え、導入の失敗を防いでいきましょう。
ポイント・導入前に全従業員に理解してもらう
ナレッジマネジメントを導入するときには、あらかじめ全社員に対してナレッジマネジメントの必要性を説明し、導入に同意できるような下地作りからしておく必要があります。
企業にとって必要だから、というような一言で導入してはいけません。
普段の業務で時間効率が悪いことが改善する、他者だけではなく自分の売上も上がるなど、社員の立場で提案をしていくことが大切です。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
運用のルールが設定されておらず失敗
ナレッジマネジメント導入の失敗事例の3つ目は、運用ルールが設定されておらず失敗することです。
ナレッジマネジメントの導入に関して、人の問題を乗り越えても、ナレッジマネジメントツール自体の問題も解決しなければなりません。
どういうことかというと、社員がナレッジマネジメントに同調し知識やノウハウをデータ化するだけではなく、集めたデータを一元化するシステムやマニュアルを用意しておく必要があるということです。
このような状態に陥ると未整理データばかりが増え、せっかくのデータが使えず暗黙知を形式知に変換することができません。このような運用のルールが設定されておらず失敗することを防ぐには、あらかじめ具体的なルールを設定してから、ツールを導入することが重要です。
ポイント・具体的なルールを設けてから導入
運用のルールが設定されていないせいで失敗することを防ぐには、当然ながら、できるだけ実用的かつ具体的な運用ルールを設けておくことが一番です。
または、データ入力・蓄積の形式が自由なナレッジマネジメントツールを導入するという方法も効果的でしょう。
運用ルールを事前に定めておけば、データを一元化しやすくなります。導入後のトラブルにも対応しやすくなるでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントを成功させるポイント
ナレッジマネジメントを成功させるには、いくつかの押さえておくべきポイントがあります。
- SECIモデルを活用して暗黙知を形式知に変換する
- 社内のナレッジを共有できる場を設ける
- ナレッジにすぐアクセスできるよう整理する
3つのポイントを詳しく解説いたします。
SECIモデルを活用して暗黙知を形式知に変換する
SECI(セキ)モデルとは、個人が持っている知識や経験といった暗黙知を、組織全体で共有できる形式知に変換し、新たな知識を生み出すフレームワークを指します。
SECIモデルは以下の4つのプロセスによって構成されています。
①共同化 | 共通の体験によって暗黙知を複数人で共有 |
②表出化 | 暗黙知を言語化し複数人で共有 |
③結合化 | 形式知を組み合わせ、新たな知識を生み出す |
④内面化 | 新たな知識を学習によって体感する |
①〜④をスパイラル構造として繰り返すことがSECIモデルです。
闇雲に社内ノウハウをデジタル化していくのではなく、このようなフレームワークに沿って行うことによってより高度な知識が身につき、ナレッジマネジメントを体系的に実施することができます。
社内のナレッジを共有できる場を設ける
ナレッジの共有には、企業側が「場」を提供するという考え方が重要です。
SECIモデルに基づいた4つの環境を社内に整備しましょう。以下の表を参考にしてみてください。
①共同化の場 | 暗黙知に関する気軽なコミュニケーションができる環境 (社内チャットや休憩所など) |
②表出化の場 | 建設的な対話やディスカッションによってナレッジを言語化できる環境 (定例ミーティングなど) |
③結合化の場 | 知識を共有・蓄積・管理できる環境 (イントラネットや情報共有ツールなど) |
④内面化の場 | 社内に蓄積された知識やノウハウを実践できる環境 (社内研修や企業内大学など) |
ナレッジにすぐアクセスできるよう整理する
先ほどの表において、「③結合化の場」に該当するポイントです。
せっかく蓄積したナレッジが、共有されずに実践されないと、結果的に失敗となってしまいます。
全ての社員がナレッジに素早くアクセスでき、業務で実践できるように、デジタルツールなどを駆使して整理することが重要です。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントに役立つツール
それでは、実際にナレッジマネジメントをする上で役立つツールをご紹介いたします。
- 社内wiki・データベース
- SFA
- FAQ
- LMS
それぞれの概要と特徴を解説していきます。
社内wiki・データベース
まず挙げられるのは、社内ネットワーク上にナレッジを集約し、自由に検索して閲覧することができる「社内wiki」のようなデータベースツールです。
社内wikiとは、インターネット百科事典「Wikipedia」の企業版といえるでしょう。誰もが操作しやすく、比較的編集も簡単であることがメリットです。
ただし、あらゆる検索ワードで的確にナレッジに辿り着けるようにキーワード設定をしなくてはいけないといった手間や、社員がどれだけ利用しているかがわかりづらいといったデメリットもあります。
SFA
SFAとは、「営業管理システム」のことを指します。
効率的に営業活動ができるよう、さまざまな機能が搭載されたツールです。
Salesforceを代表とするSFAには、各営業がどのように案件に取り組み、どのような結果を残したかが蓄積されます。営業職に関連するナレッジマネジメントには、SFAが役立つでしょう。
FAQ
FAQとは、「よくある質問」とも呼称される、頻繁に尋ねられる質問とその回答をまとめたページのことです。
主に企業から顧客に向けて展開されることが多いFAQですが、ナレッジマネジメントにも活用できます。質問と回答形式にすることによって、欲しい情報に辿りつきやすくなるという点がメリットです。
企業によっては、FAQとAIによるチャットボットを組み合わせ、さらに検索の効率をアップさせた事例もあるようです。
LMS
LMSは、「学習管理システム」としてeラーニング研修の管理に利用されるツールです。
自社オリジナルのeラーニング教材を作成してアップロードできる機能と、社員に対してeラーニングを配信できる機能を活用してナレッジマネジメントを行うことができます。
ただナレッジを蓄積するだけではなく、eラーニング配信という形でアウトプットまでできるという点が他のツールとの大きな違いです。
LMSとeラーニングを利用してナレッジマネジメントを行う方法について、次項からより詳しく見ていきましょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングによるナレッジマネジメントとは

そもそも「eラーニング」とは、パソコンやタブレット、スマートフォンなどを利用し、オンラインで学習するシステムです。
なぜeラーニングがナレッジマネジメントツールとして有用なのでしょうか。
それは、蓄積されたナレッジマネジメントデータが、通常のデータベースのものより、eラーニング教材としてのデータの方が視覚的にわかりやすく、直感的に操作できるメリットがあるからです。
ノウハウやナレッジをeラーニング教材化
前述した通り、知識やノウハウなどのナレッジをeラーニング化し、社員に向けた教材として使用することができます。このことにより、大規模な集合研修を実施しなくても、ナレッジマネジメントを行うことができ、時間・コストの削減につながります。
また、社員は自由に研修を受けることができるため、効率よく蓄積されたデータによって学習していくことができます。
eラーニング教材は購入すべきか、自社開発すべきか詳しく知りたい方は『eラーニングの教材は購入すべき?開発すべき?良い教材のポイントも』をご覧ください。それぞれのメリット・デメリットを紹介しています。
教材の蓄積・配信
ナレッジマネジメントツールとしてeラーニングシステムを利用する場合、eラーニング教材を作成する必要があります。
初めから受講者に教えることを目的としてナレッジを収集すれば、よりわかりやすく共有しやすい内容にまとまるでしょう。
eラーニングの教材を作成したことがないという企業でも、eラーニングシステムのベンダーからサポートを受けることで高クオリティな教材作成が可能となります。
こうして作られた自社ノウハウのeラーニング教材はeラーニングシステム内に蓄積され、必要に応じて受講者に配信をすることができます。
LMSによる学習管理も
LMSには、学習管理機能が搭載されています。
受講者となる社員一人ひとりをアカウントとして管理し、誰がどの教材をどこまで進めたのかがデータ化され自動的に保管されます。ナレッジマネジメント施策においても、この学習管理機能は非常に有効です。
ナレッジマネジメントを成功させるため社内ルールを設定しても、きちんと守られているかどうかをアナログで管理するのは困難です。このような時にLMSがあれば、社員の進捗を正確に把握でき効果的なフォローを行うことができます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングなら「etudes(エチュード)」
ナレッジマネジメントのためにLMSを導入するなら、ぜひ「etudes(エチュード)」をご検討ください。
etudesは、アルー株式会社が20年余りの人材育成ノウハウを結集して開発した、日本国産のクラウド型LMSです。
etudesには教材配信・学習効果測定・アカウントごとの学習進捗管理といった多彩な機能が搭載されており、誰もが操作しやすいUI/UXデザインで構成されている点が大きな特徴です。
使いやすさを追求して開発されたLMSであるため、全社で取り組むナレッジマネジメントにベストなツールと言えるでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
ナレッジマネジメントを導入した企業の事例と、よくある失敗事例をご紹介いたしました。
ナレッジマネジメントが順調に進み、ナレッジがデータとして蓄積しても、暗黙知が形式知に変換するアウトプットを適切に実施しなければなりません。形式知化のベストな方法として、LMSでのナレッジマネジメントをおすすめします。
ナレッジマネジメントのためのLMSの選定に迷ったら、ぜひetudesをご検討ください。
etudesの詳しい製品紹介を知りたい方は『製品紹介資料』をダウンロードください。etudesの特徴やデモ画面、費用についてご紹介しています。