
ナレッジマネジメントはシステム導入でより効率的に!LMSの活用法をご紹介
ナレッジマネジメントという言葉が企業に浸透してから、多くの手法やノウハウが提唱されてきました。企業が継続的に成長していくためには、各社員が個々に保有するナレッジ(経験や知識)を社内全体の資産に変換できるか否かが重要になっています。
ナレッジマネジメントを効率的に実施したい場合は、ツールとしてSFAやLMSといったシステムを選び、導入する必要があります。
この記事では、ナレッジマネジメントに使えるシステムやその導入方法、おすすめのツールなどについてご紹介します。
実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
- 1.ナレッジマネジメントとは
- 2.ナレッジマネジメントに役立つシステムとは
- 3.システムを活用したナレッジマネジメントが効果的な理由
- 3.1.働き方・雇用制度の変化
- 3.2.在宅勤務(テレワーク)の普及
- 3.3.社内DX化の推進
- 4.システム導入で解決できるナレッジマネジメントの課題
- 4.1.ナレッジの整理・棚卸ができない
- 4.2.ナレッジを集約しづらい
- 4.3.情報検索が煩雑になる
- 5.ナレッジマネジメントにシステムを導入すべき理由
- 5.1.暗黙知を形式知に変える
- 5.2.いつでもどこでも効率的にナレッジ共有
- 5.3.あらゆるナレッジの整理・蓄積が可能
- 6.ナレッジマネジメントシステムの選び方
- 6.1.操作性が高い
- 6.2.マルチデバイスに対応している
- 6.3.セキュリティ対策が万全
- 6.4.スモールスタートできる
- 7.LMSをナレッジマネジメントのシステムとして活用する方法
- 7.1.ナレッジをコンテンツ化しLMSにアップロード
- 7.2.必要なメンバーに教材を簡単に割り当て
- 7.3.学習の進み具合を確認
- 7.4.適切なフィードバックの実施
- 8.eラーニングシステム・LMSならetudes(エチュード)
- 9.まとめ
eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
ナレッジマネジメントとは
ナレッジマネジメントは、社員の保有している知識や経験を企業内で共有し、企業全体で活用する経営手法です。
ナレッジマネジメントは、「生産管理」「販売管理」「財務管理」「人的資源管理」「情報管理」に続く第六の管理領域と言われています。集合知とも呼ばれるこの考え方は、マネジメントの領域から注目を浴びています。
ナレッジマネジメントの概要について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
『ナレッジマネジメントとは?意味・考え方から導入のポイントまで解説』
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントに役立つシステムとは
ナレッジマネジメントに役立つシステムとして、以下の3つが挙げられます。
- オンラインストレージシステム
- SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理)
- eラーニングシステムやLMS(学習管理システム)
それぞれのシステムがどのようにナレッジマネジメントに活かせるのか、詳しく解説します。
オンラインストレージシステム
ナレッジマネジメントにおいて、社内の知見やノウハウを一元管理し共有するには、オンラインストレージシステムの活用が有効です。クラウドストレージサービスを利用することで、以下のようなメリットがあります。
- 場所を選ばずアクセス可能
- 常に最新版のファイルを共有できる
- アクセス権限の設定で、情報漏洩リスクを低減
主なクラウドストレージサービスには、DropboxやGoogleDrive、OneDriveなどがあります。
部門やプロジェクト単位で適切なサービスを選定し、ナレッジの蓄積と活用を進めていきましょう。無制限で利用できるストレージがあれば、社員の知恵を結集し、ビジネスの生産性向上につなげることができます。
SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理)
営業職のナレッジマネジメントにおいては、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)の活用は欠かせません。これらのシステムは、顧客情報や商談履歴などの営業活動に関するデータを一元管理し、営業担当者間で共有することができます。
SFAやCRMを活用することで得られるメリットは以下の通りです。
- 顧客ごとの対応履歴や商談状況を共有し、担当者が変わっても円滑に引き継ぎができる
- 商談成功事例などのナレッジを蓄積・共有し、営業活動の効率化と成約率アップにつなげられる
- 営業職全員が顧客の課題やニーズを的確に把握し、最適なソリューションを提案できる
営業のノウハウやスクリプトを紙のマニュアルで管理している企業は、SFAやCRMを導入してナレッジマネジメントを始めてみましょう。
eラーニングシステムやLMS(学習管理システム)
eラーニングシステムやLMS(Learning Management System)は、eラーニングによる社員教育を管理するシステムです。しかし、使い方によってはナレッジマネジメントのシステムとして活用することができます。
LMSの機能を活用すると、オンラインで学習コンテンツを配信・管理することができ、受講状況の把握も可能です。社内のナレッジをeラーニング教材化し、オンライン研修という形で社員に配信することができます。
ナレッジマネジメントはただ知識をデータ化するのではなく、その知識をどうやって社内に残し、次の世代に引き継いでいくかが重要です。LMSは、ナレッジマネジメントをゴールまで導くことができるシステムと言えるでしょう。
ナレッジマネジメントに使えるツールについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
『ナレッジマネジメントツールの選び方・運用の注意点とは?』
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
システムを活用したナレッジマネジメントが効果的な理由
先ほどご紹介したシステムを活用してナレッジマネジメントを行うことが効果的である理由は、次の3つが挙げられます。
- 働き方・雇用制度の変化
- 在宅勤務(テレワークの普及)
- 社内DXの推進
以下にて、詳しく内容を見ていきます。
働き方・雇用制度の変化
近年、働き方と雇用制度は大きく変化しています。
終身雇用や年功序列といった従来の雇用システムが崩れ、ジョブ型雇用への移行が進んでいます。また、在宅勤務やフリーランスなど多様な働き方が広がり、社員の流動性が高まっています。
こうした変化により、個人の知識やノウハウを組織として共有・継承することが難しくなっています。優秀な人材が退職すると、その人の持つ知識も組織から失われてしまうのです。 働き方の変化に対応し企業としての競争力を保つために、システムを用いたナレッジマネジメントは必須といえます。
在宅勤務(テレワーク)の普及
在宅勤務の増加に比例して、これまで社内で行われていた「雑談」が急激に減少しました。知識の共有は、このような雑談の中で日常的に行われており、意図しなくても一定の社員に広まっていた事実があります。
また、知識を教わる立場の社員は、同じ空間にいる上司や同僚には質問しやすいですが、テレワーク中に離れた場所から連絡をとり、質問することはハードルが高く、疑問点が解決しづらいという側面もあります。
対面での指導や雑談が急激に減った現代社会では、企業側が社員に対して知識の共有を促す必要があります。そのため、LMSなどのシステムを使って学びの場を設けるナレッジマネジメントが急務となっています。
社内DX化の推進
これまで、暗黙知として一部の社員だけが持っていた知識をデジタル化し、オンラインで共有してナレッジマネジメントをすることは、社内DXの推進にもつながります。
社内DXとは、デジタル技術を駆使して働き方を改善し、製品やサービスの変革と企業文化・風土のアップデートを目指す取り組みのことです。
オンライン学習システムなどを活用してナレッジマネジメントを実施すれば、社内のノウハウや知識をデジタル化する施策として、社内DX化を推進することとなるでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
システム導入で解決できるナレッジマネジメントの課題

ナレッジマネジメントはシステムを使わずに、ドライブにデータをアップロードするだけといった従来の情報共有の方法を使って実施することも可能です。
しかし、システムを使わずにナレッジマネジメントを行った場合、以下のような課題が発生する可能性があります。
- ナレッジの整理・棚卸ができない
- ナレッジを集約しづらい
- 情報検索が煩雑になる
これらの課題は、システム導入によってどのように解決できるのでしょうか。以下で詳しい内容をご紹介します。
ナレッジの整理・棚卸ができない
情報をドライブに集約しても、どのスキルを、誰が、どの程度保持しているかは可視化されず、結果として必要情報が足りているか、各情報が十分であるかなどの判断がつきにくく情報の整理や棚卸がしづらくなります。さらに、個別の情報をドライブで一元管理したとしても、ナレッジの範囲が広く、より現場に近い内容の場合、管理を担う社員が情報を把握しきれない場合もあります。
例えばLMS(eラーニングシステム)を活用した場合、同じテーマの情報を集約して、1つのeラーニングコースを作成することができます。コース作成をすることによって、ナレッジを分類し、テーマごとに情報を整理し体系化することができます。さらに、作成したコースを必要な人材に割り当てることで、必要な情報を必要な人材へ提供しやすくなります。体系化を通して整理・棚卸することによって、「不足しているナレッジ」が何か、どのようにして対応すべきかの解像度も高まります。
ナレッジを集約しづらい
システムを利用せず、社内ドライブに格納する形でナレッジマネジメントを行うと、部門間の壁によってナレッジが分断されてしまい、全社的な共有が進まないケースが見受けられます。
こうした状況では、ナレッジを効果的に活用することができず、生産性の向上やイノベーションの創出は期待できません。ナレッジマネジメントを行う上で、ナレッジを一つのシステム上に集約することは非常に重要です。
ナレッジマネジメントシステムの導入によって、全社のナレッジを一元管理し、誰もがアクセスできる環境を整備することができます。
情報検索が煩雑になる
ナレッジは、Excelにまとめたり、PDFのデータにしたりすることも可能です。
しかしその方法では、ナレッジを受講する側が知りたい情報に辿り着くのは困難になります。また、部署ごとの新入社員に対して、適切なマニュアルやデータをまとめてメールで送付する、といった手間もかかるでしょう。これが、ナレッジの活用におけるよくある課題の一つです。
LMSは、社員の誰もがアクセスできる学習のポータルサイトとして活用できるため、受講者側は必要な教材を検索でき、管理者側は受講者ごとに必要な教材の配信を自動化できます。蓄積したナレッジを整理し、配信と学習進捗の確認まで効率的に管理したい場合はナレッジマネジメントのシステムとしてLMSの導入が効果的でしょう。
ナレッジマネジメントの事例についてより詳しく知りたい方は、ナレッジマネジメントの成功事例とよくある失敗事例を解説の記事をご覧ください。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントにシステムを導入すべき理由
情報の管理・共有の面から、ナレッジマネジメントの実現にシステムの導入は必要不可欠であると言えます。具体的な理由として、以下の3つをご紹介します。
- 暗黙知を形式知に変える
- いつでもどこでも効率的にナレッジ共有
- あらゆるナレッジの整理・蓄積が可能
暗黙知を形式知に変える
社員が暗黙的に持っている仕事に関する知識を形式知に変えるには、システムを使用するのが最も効率的です。
一例を挙げると、テキストで説明をすることが難しく、暗黙知となってしまっていた作業手順があります。これを、ベテラン社員が実際に行っている様子を動画教材にし、LMSにアップロードすれば、誰もが視聴して学べる形式知となります。
それらの形式知は、会社の財産ともいえるでしょう。
いつでもどこでも効率的にナレッジ共有
システムを使えば、いつでもどこでもオンラインでナレッジにアクセスできます。紙のマニュアルのように、保管に場所をとったり、破損して読めなくなったりといったリスクがありません。
また、時間が経過しても情報が残り、時間・場所の両面で制約を取り払うことができます。
あらゆるナレッジの整理・蓄積が可能
部署ごとにナレッジマネジメントを実施する際、誰かのPC上だけにデジタル化したマニュアルが格納されていたり、バラバラに管理されたりしていては肝心な「共有」ができません。
全社に共通のシステムでナレッジマネジメントを行うことで、部署ごと・業務のステップごとのナレッジがきちんと整理され蓄積されていきます。
これによって、部署間での共有も容易になります。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
ナレッジマネジメントシステムの選び方
ここからは、ナレッジマネジメントシステムの選び方についてご紹介します。ナレッジマネジメントシステムの選び方で気を付けるべきポイントは、以下の4つです。
- 操作性が高い
- マルチデバイスに対応している
- セキュリティ対策が万全
- スモールスタートできる
詳しい内容を見ていきましょう。
操作性が高い
導入したナレッジマネジメントシステムは、社員が容易に使いこなせることが重要です。蓄積された豊富なデータも、システムそのものが使いにくければ形骸化してしまいます。特に、PC操作を得意としない高齢世代の社員でも、直感的に使用できる操作性の高いシステムを選ぶようにしましょう。
マルチデバイスに対応している
PCのみならず、マルチデバイスに対応しているか否かは、無視できない決定のポイントです。多くの仕事を抱えている忙しい社員は、新しいナレッジの習得に時間を割く余裕がありません。しかし、新しいナレッジは常に吸収していかなければ、社員の成長が止まってしまいます。そんなときに力を発揮するのが、マルチデバイス対応のナレッジマネジメントシステムです。マルチデバイス対応のシステムであれば、忙しい社員も、スマホやタブレットを活用し、移動時間などの隙間時間を見つけてナレッジの吸収を行うことができます。
セキュリティ対策が万全
ナレッジは、会社の財産です。大切な財産がウイルスなどの感染により漏えいすることがないように、セキュリティ対策の万全なナレッジマネジメントシステムを選択するようにしましょう。無料のナレッジマネジメントシステムは、セキュリティが弱い可能性があります。導入前に、セキュリティ対策を確認しましょう。
セキュリティ対策については、eラーニング導入時に知っておきたいセキュリティ対策についての記事でもご紹介していますので、あわせてご覧ください。
スモールスタートできる
ナレッジマネジメントには、いくつかの方法があります。一つを選んでいきなり大規模導入をすると、失敗したとき大きなダメージを負ってしまいます。ナレッジマネジメントは、スモールスタートできるシステムを選びましょう。スモールスタートして、社員がシステムの導入に好意的か、反発はないかなど、しっかりと見定めながら徐々に大規模導入に向けて準備していくのが良いでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
LMSをナレッジマネジメントのシステムとして活用する方法
最後に、LMSを使って実際にナレッジマネジメントを行う方法を以下の流れでご紹介します。
- ナレッジをコンテンツ化しLMSにアップロード
- 必要なメンバーに教材を簡単に割り当て
- 学習の進み具合を確認
- 適切なフィードバックの実施
それぞれのステップごとに、詳しくみていきましょう。
ナレッジをコンテンツ化しLMSにアップロード
LMSをナレッジマネジメントのシステムとして活用するには、まず社内のナレッジをコンテンツ化し、学習しやすいeラーニング教材にまとめることが重要です。 eラーニング教材は以下のようなコンテンツが一般的です。
- テキスト教材(PDF等のドキュメント)
- 画像教材(スライドや図解)
- 動画教材(解説動画やデモ動画)
- 小テスト(理解度チェック用)
これらのコンテンツを作成したら、LMSの管理画面から教材をアップロードします。その際、教材のメタデータ(カテゴリや対象者など)を設定しておくと、必要な人が必要な時に教材を見つけやすくなります。
必要なメンバーに教材を簡単に割り当て
ナレッジを蓄積したeラーニング教材をLMSにアップロードしたら、次は必要な社員に教材を割り当てていきます。LMSの機能を活用すれば、以下のように対象者に教材を簡単に割り当てられます。
- 部署や役職、スキルレベルなどでグループ分け
- 各グループに適した教材を一括で割り当て
- 個人に特化した教材の割り当ても可能
このようにLMSのグループ機能と教材割り当て機能を使えば、誰でも簡単に必要な情報にアクセスできるようになります。ナレッジ=専門知識を持つメンバーが社内に点在している場合でも、情報を集約しやすく、お互いに学び合える組織風土が醸成できるでしょう。
LMS「etudes(エチュード)」を導入し、1on1で社員同士が学び合う文化を生かしたナレッジマネジメントを実現した事例を以下のページでご紹介しています。
『「社員全員」が教育コンテンツを作成・配信し、学び合える環境を構築』
学習の進み具合を確認
LMSを活用すれば、社員一人ひとりの学習の進捗状況を把握することができます。
LMSの管理画面では、受講者ごとのコンテンツの閲覧率や完了率が表示されます。また、理解度を確認するためのテストの結果や、オフラインで実施する集合研修への出席率などもデータで管理できます。
「仕事が忙しくて、ナレッジマネジメントのための学習をしてこなかった」ということがないように、社員一人ひとりに対してきめ細かな学習の促進が可能です。
適切なフィードバックの実施
LMSで学習者の理解度を把握することにより、適切なフィードバックを行うことができます。学習の進み具合が遅れ気味の社員に対して、受講を促すメールを配信したり、LMSで確認した進捗データを元に、受講者の上司に対して業務量の調節を進言したりといった対応が可能となるでしょう。
また、LMSの中には受講者にアンケートを配信し、結果を集計する機能が搭載されているものもあります。アンケートを通して受講者の意見を受け、ナレッジマネジメントのシステムとしてブラッシュアップすることもできます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングシステム・LMSならetudes(エチュード)

20年余りに渡り人材育成に携わってきたノウハウを結集して造られたeラーニングシステムが、「etudes(エチュード)」です。
etudesのeラーニングは、数人から数十万人規模で活用することができます。
etudesは教材の作成と配信だけではなく、わかりやすいUI/UXによって教材を整理し蓄積することもできます。あらゆる年齢層や業種の方にとって使いやすいため、ナレッジマネジメントを「複雑そう」「難しそう」と思っている方でもすぐに操作ができるようになるでしょう。
また、etudesなら経験豊富なコンサルタントのサポートを受け、自社オリジナル教材を作成することも可能です。
自社のノウハウをeラーニングによって整理し、企業の将来のために蓄積するなら、多くの大手企業に導入実績があるetudesがおすすめです。
etudesの詳しい製品紹介を知りたい方は『製品紹介資料』をダウンロードしてください。etudesの特徴やデモ画面、費用についてご紹介しています。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら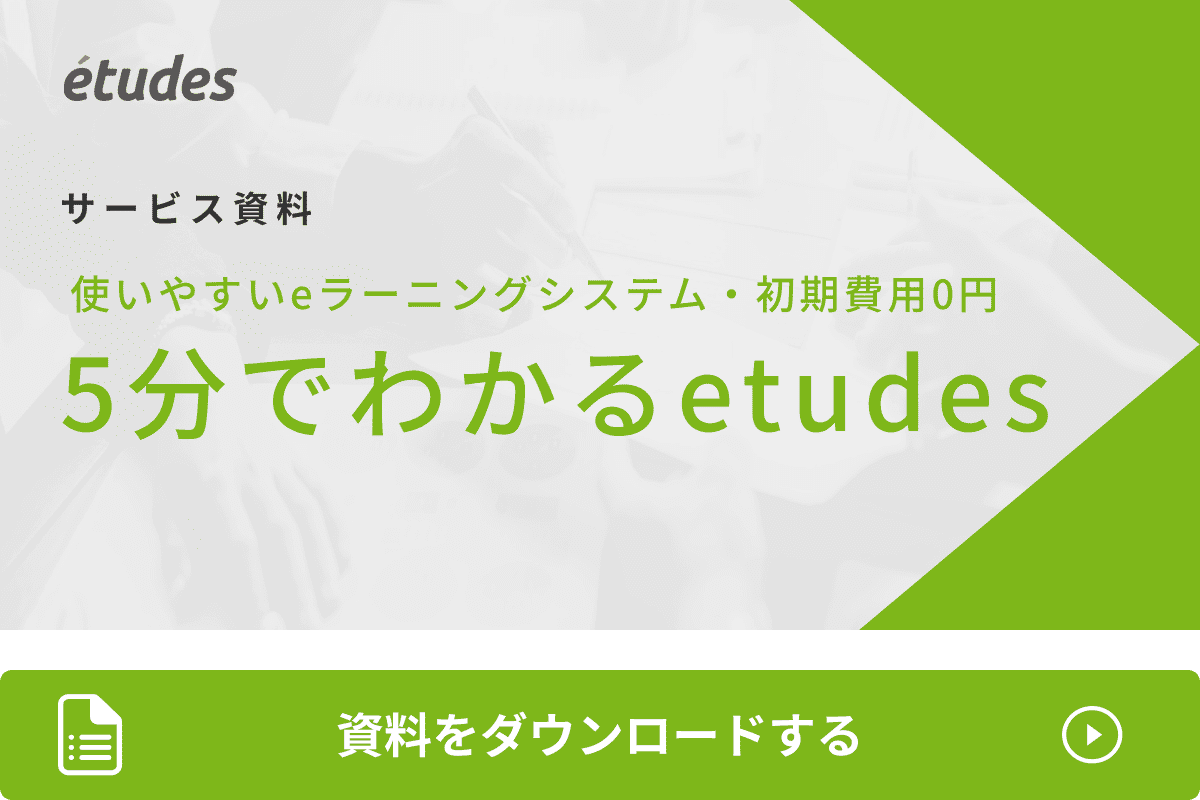
まとめ
この記事では、ナレッジマネジメントを企業に浸透させる際の方法や、活用すべきシステムについてご紹介しました。
働き方改革の影響により、人材の流動性が今後さらに高まると考えられます。人材の流出は止めることができないため、自社が持つノウハウや技術を共有しておく必要があります。
ナレッジマネジメントを行うためのシステムはさまざまありますが、中でもLMSを活用する方法をおすすめします。経験豊富なコンサルタントと共に、etudesでナレッジマネジメントの取り組みを行ってみませんか。












