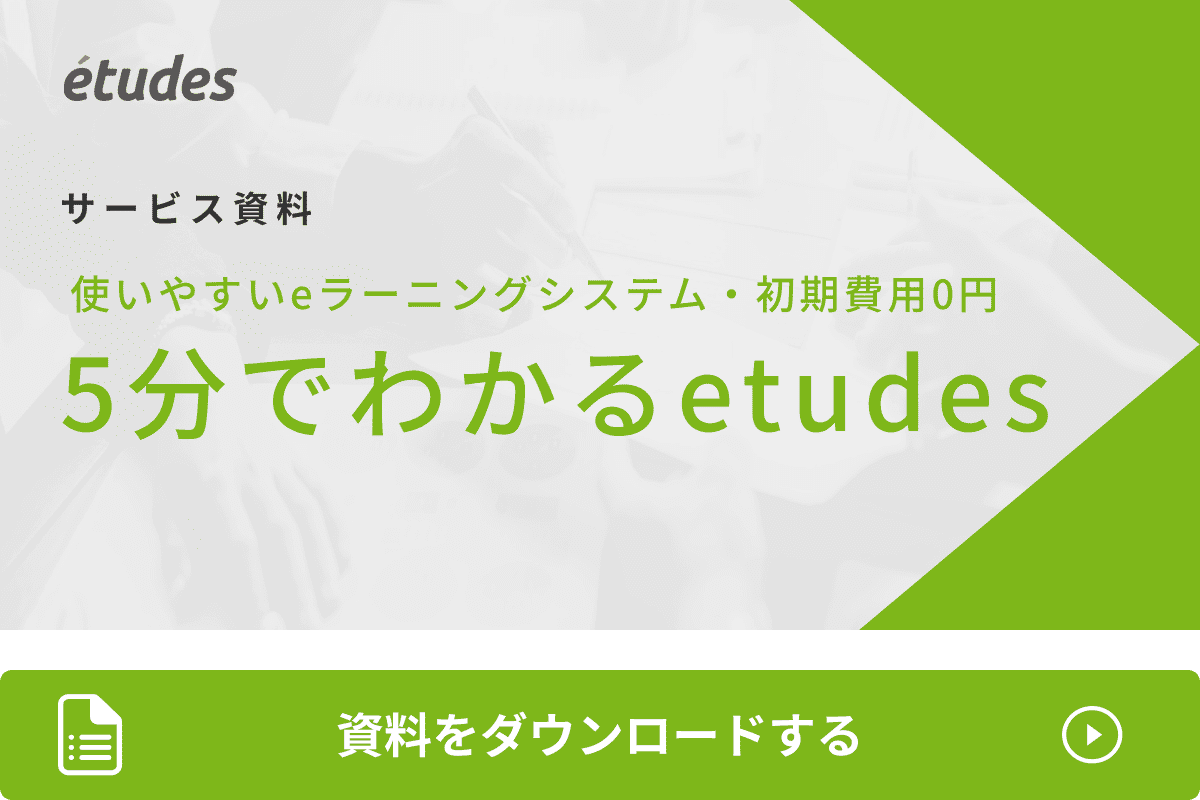eラーニング導入を成功させるポイントは?導入費用や事例もご紹介
働き方の変化や多様化によりリモートワークなどが普及し、企業の人材育成においてeラーニング導入が進んでいます。特に、学習進捗や人材育成の取り組みの成果を可視化したい、人材育成の運営工数を削減したいといった課題がある場合、eラーニングの導入は効果的です。
一方でeラーニングシステム(LMS)は多くのベンダーから提供されており、その機能は多種多様です。自社に適したサービス選定や導入において、課題を感じる場合も少なくありません。今回は、企業がeラーニングを導入する際に明確にしておきたいポイントや、導入のメリット、導入方法をご紹介します。また、導入目的別にベンダーを比較したい場合は、『eラーニング比較検討表』のダウンロードがおすすめです。料金体系や機能を一覧で比較できます。
実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページをご覧ください。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
- 1.eラーニング導入は事前の準備が重要!
- 2.eラーニングの導入を成功させる「6W1H」
- 2.1.eラーニングを導入する目的・目標を明確にする(Why)
- 2.2.eラーニングの学習対象者を決める(Whom)
- 2.3.eラーニング教材の調達方法を決める(What)
- 2.3.1.1.既存のものを教材化する
- 2.3.2.2.既製品の教材を購入する
- 2.3.3.3.教材を新たに作る
- 2.4.導入するeラーニングシステムを選定する(Where)
- 2.5.eラーニングの導入時期を決める(When)
- 2.6.eラーニングの運営体制を整える(Who)
- 2.7.学習履歴データの活用方法を決める(How)
- 3.eラーニング導入のメリット
- 4.eラーニング活用のためのポイント
- 5.eラーニングシステム(LMS)導入に必要な費用
- 5.1.パッケージ型LMS
- 5.2.オープンソース型LMS
- 5.3.フルスクラッチ型LMS
- 6.eラーニングの導入方法
- 6.1.LMS利用の要件を再度確認し、利用方法を確定
- 6.2.LMSの機能の設定
- 6.3.データの登録
- 6.4.運用方法の確定
- 6.5.一部組織でのテスト利用の実施
- 6.6.全社への公開、利用開始
- 7.eラーニングの導入事例
- 8.クラウド型eラーニングシステムなら「etudes」
- 9.まとめ
eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
eラーニング導入は事前の準備が重要!
eラーニングの導入を成功させるには、事前に社内で準備をしておくことが重要です。
eラーニングは、いつでもどこでも学習できるメリットがある反面、学習の進度や意欲は受講者に委ねられるという特性があります。これまで対面で行ってきた研修をeラーニングに切り替える場合は、受講者となる社員に対してeラーニングで学ぶための準備をしてもらう必要があります。
導入のための準備をするのは、受講者側だけではありません。eラーニング研修を管理する人事担当者から管理職に至るまで、全社的にマインドセットを行います。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングの導入を成功させる「6W1H」

実際にeラーニングシステムを導入する前に準備すべきことは、以下の「6W1H」にまとめられます。
- eラーニングを導入する目的・目標を明確にする(Why)
- eラーニングの学習対象者を決める(Whom)
- eラーニング教材の調達方法を決める(What)
- 導入するeラーニングシステムを選定する(Where)
- eラーニングの導入時期を決める(When)
- eラーニングの運営体制を整える(Who)
- 学習履歴データの活用方法を決める(How)
このようにリストアップすることで、準備の抜け漏れを防げるでしょう。
それぞれの項目について、以下から詳しく解説します。
eラーニングを導入する目的・目標を明確にする(Why)
まず重要なことは「eラーニングを導入する目的・目標を明確にする(Why)」ことです。自社の課題をベースに、なぜ導入するのか、導入して何を実現したいのかを明確にしましょう。
例えば、企業側が学習内容を決める場合「基礎的な知識を幅広い対象者に一斉に学習させる」のか、あるいは「専門的な知識を少人数の対象者に学習させる」のかでeラーニングの活用方法は変わります。
また、社員自身が学習内容を決める場合は「一人ひとりが自分の興味のあるものを自由に学習する」ためにeラーニングを用いることもあれば、「社員が自分の専門知識を活かして教材を作成して公開する」ことにeラーニングを活用する場合もあるでしょう。
それに加えて、eラーニングシステムは情報プラットフォームとして活用できる汎用性もあるため、学習以外の使い方もあります。会社の経営方針などの重要な施策の伝達に利用したり、社員同士がコミュニケーションを取りながら互いに教え合ったりする場合にも役立つでしょう。
以下が、企業におけるeラーニング導入の目的や活用方法の事例です。
- 会社が学習内容を決める場合
基礎的な知識を幅広い対象者に一斉に学習させる
専門的な知識を少人数の対象者に学習させる - 社員自身が学習内容を決める場合
社員一人ひとりが自分の興味のあるものを自由に学習する
社員が自分の専門知識を活かして教材を作成して公開する - eラーニングと合わせて情報共有をする場合
会社の経営方針などの重要な施策を伝えるために利用する
自社独自の情報を共有するプラットフォームとして利用する - 社員同士の情報交換や学び合いの環境を作る場合
各社員が持っている知識や情報をシステムに蓄積する
蓄積した知識(ナレッジ)を他者に共有するプラットフォームにする
自社でeラーニングを活用して何を実現したいのかを明確にし、学習以外の利用方法も視野に入れながら、どのLMSを使うのか、eラーニングをどのように利用するのかを決めていくことが大切です。
eラーニングの学習対象者を決める(Whom)
続いて、eラーニングの学習対象者が誰なのか(Whom)を確認しましょう。学習対象者が全社員か、部門ごとか、階層ごとかなど、自社の課題に合わせて対象者を設定します。
対象者を決める方法としては、社員の階層、属性(勤務年数・役職など)で決める方法と、社員が持っている知識・スキルで決める方法の2つがあります。
階層別に対象者を決める場合は、会社がすでに持っている情報で決めることができるためグループ分けが容易です。導入するeラーニングシステムは、階層別に体系化された教材が豊富なものがおすすめです。
知識・スキルで分ける場合には、まず社員の知識・スキルレベルを診断・測定する必要があるため、一定の手間がかかります。さらに、eラーニング教材がテーマやスキル別に選びやすい環境整備が大切です。
eラーニング教材の調達方法を決める(What)
導入するeラーニングシステムの選定が決まったら、次に、利用するeラーニング教材がどのようなものなのか(What)について詳細を決めていきましょう。eラーニング教材は、3つの方法で利用できます。
1.既存のものを教材化する
社内資料やマニュアルなどをアップロードして教材にしたり、社内勉強会や集合研修を動画教材やスライドにする方法です。eラーニングシステムでは、それらの教材を組み合わせて簡単にコースを作成することができます。そのため、すでに自社にある教材を組み合わせるだけでも、自社独自のeラーニング教材が完成します。
eラーニングシステムで使える教材形式はこちらから
eラーニング教材の内製についてくわしく知りたい方はこちらの資料がおすすめです。
2.既製品の教材を購入する
eラーニングのコンテンツを提供している、いわゆるeラーニングベンダーから購入する方法です。eラーニングシステム(LMS)を提供しているベンダーの多くは、一般的な内容のコンテンツを用意しており、eラーニング教材をセットにして受講者に提供しています。
企業研修を専門とするベンダーであれば、階層別に必要なスキルを体系化したeラーニング教材が豊富なだけでなく、テーマ別教材も豊富で、社内育成に活用しやすくなっています。
eラーニング教材についてはこちらから
3.教材を新たに作る
- 自社で作成する
- 研修会社に教材作成を依頼する
という2つの方法があります。
自社で教材を作成する場合には、動画編集などの知識や、機材の調達などが必要になります。eラーニング教材の作成支援サービスを提供している研修会社があれば、、それを活用することで質の良いeラーニング教材の作成ができるでしょう。
また、eラーニング教材の作成を全て外注することも可能です。長く利用する教材の場合や動画編集の知識のある人材がいない場合などは、外注した方がメリットが多いでしょう。
eラーニング教材は購入すべきか、自社開発すべきか詳しく知りたい方は『eラーニング教材は自社開発すべき?購入すべき?受講者と企業の視点で解説』をご覧ください。それぞれのメリット・デメリットをご紹介しています。
導入するeラーニングシステムを選定する(Where)
eラーニングの導入では、多くの場合、受講者と管理者が利用するプラットフォームとなるeラーニングシステム(LMS・学習管理システム)を導入します。このシステムの活用により、スムーズにeラーニングを受講できる環境を自社内に作ることができます。
自社のeラーニング導入の目的に合わせて、eラーニングシステム(LMS)に必要な機能(Where)を選定していきましょう。提供ベンダーによって標準機能が異なるため、自社の目的や運営に適したシステム導入を進めることが大切です。
機能選定では、各部門の要件をヒアリングすると良いでしょう。
例えば「外出の多い社員にも受講しやすいように、スマホで受講できるようにしたい」「社外秘の情報を教材化させるため、社内のみで利用できるようにしたい」など、利用する端末や利用方法を明確にし、総合的に判断することがおすすめです。
また、eラーニングを導入する際、システムや教材の無料トライアルを実施しているベンダーもあります。eラーニングの導入では、システムを複数社比較する場合が多くなりますが、最低でも1社の無料トライアルを行い、実際にシステムの操作性やUI/UXを導入前に確認することをおすすめします。教材については、自社の目的に応じた学びが実現できるeラーニング教材が提供されているかどうかを、導入前に確認しておくことが重要です。
料金についてもベンダーによって違いがあります。初期費用はオンプレミス型、クラウド型で大きく変わるだけでなく、運用コストなどの月額利用料もベンダーによって様々です。
機能面、運営面、コスト面など多角的な視点で導入検討を進めましょう。
eラーニングシステム(LMS)の導入について、詳しくは以下の記事でもご紹介しています。
失敗しないLMS(学習管理システム)導入!比較すべきポイントを解説 | etudes
eラーニングの導入時期を決める(When)
導入時期(When)を想定することも重要です。導入にあたって、さまざまな準備が必要になるため、段取り良く進めるためにも、予め導入時期を決めておきましょう。
クラウド型のeラーニングを導入する場合、必要な準備は以下になります。
- 環境構築
- eラーニング教材・コンテンツ準備
- ユーザー情報等の登録
- 試験運用の実施
- 社内への周知
- 本番運用開始
システムの提供ベンダーが導入支援をしてくれる場合もありますが、運用を開始したい時期から逆算して準備期間の設計をすることがおすすめです。一般的には1~3ヶ月ほどかかります。
導入作業は、人事部門や情報システム部門が担当することが多いと考えられます。新入社員研修の時期や年度末などの繁忙期に導入すると、設定などの管理が行き届かないこともあるので、比較的落ち着いた時期に進めると良いでしょう。
eラーニングの運営体制を整える(Who)
eラーニング導入後にうまく活用するためには、誰が管理や運用をするのか(Who)の体制を設計しておくことが重要です。管理や運用の体制を整える際には、以下のことを意識して進めましょう。
- eラーニングの利用者をいつまでにどのくらい増やしていくのか
- 学習コンテンツをいつまでにどのくらい増やしていくのか
- 受講者の学習履歴をどのように活用していくのか
- システムトラブルがあった場合、どういったオペレーションで対応するのか
各部門の責任範囲や役割分担を明確にしておくと良いでしょう。導入後に決定する場合、うまく運用できないケースも考えられます。予め体制を整えておくと、急なトラブル時でも対応しやすく、社内でスムーズにシステムを使うことができます。
また、eラーニングの受講を全て社員の自律性に任せてしまうと、利用されない、浸透しないという可能性があります。そのため導入初期は、組織全体で積極的に活用を働きかけることをおすすめします。
例としては、eラーニングへの取り組みを人事評価に反映させる、eラーニングと集合研修を組み合わせて効率的に人材育成施策を実施する、などが挙げられます。受講者にとってのeラーニング受講の必然性やメリットを打ち出すことで、社内定着度が変わってきます。
学習履歴データの活用方法を決める(How)
eラーニングを導入したあとは、学習履歴データを元に効果測定・運用改善を行う必要があります。そのため、導入前にどのように効果測定を行うのか、学習履歴データをどう活用するのか(How)を決めておくと良いでしょう。
効果測定には、以下のような指標があります。
- テストやクイズの合格率・不合格率
- 研修満足度
- 研修完了率
- 研修後パフォーマンス
eラーニング受講後、内容に応じたテストやクイズを行うことで効果測定をすることが可能です。LMSにはテスト機能がついていることが多いため、活用してデータを取得すると良いでしょう。
また、研修後のアンケートなどで研修満足度を調査することができます。受講者が研修を受けてどう思ったか、どのような改善が考えられるかを記入してもらい、その内容を参考に改善を行いましょう。
LMSを導入すれば、受講者がどこまで動画を視聴したのかが分かります。完了率が低い動画については、なぜ受講されないのかを分析し、動画の内容を分かりやすく編集する、事前情報となる動画を作成する、などの改善が可能となります。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニング導入のメリット
eラーニングが多くの企業で導入されているのは、受講者・企業双方にとってのメリットが大きいためです。ここでは、受講者側と企業側双方のメリットをご紹介します。
【eラーニング導入】受講者側のメリット
eラーニングを導入することによる受講者側のメリットは、
- 研修をいつでも・どこでも受講することができる
- 自分の学習状況を確認できる
- 興味に応じて自発的に学ぶことができる
- 集合研修の予定調整などもシステムで完結できる
などが挙げられます。
eラーニングはスマホやパソコンなど、インターネットが接続できる環境にあればどこでも受講することが可能です。そのため、
「遠方の支店にいて本社の研修が受けられない」
「研修のために本社に行くのは手間やコストがかかる」
という理由による研修不参加を減らせます。また、自身の業務のすき間時間で学習できるため、業務に注力できる点もメリットの一つです。
また、研修の出欠をシステム上で自分で管理できるため、何度も人事担当者と連絡を取る必要がなく、参加のための日程調整もスムーズになります。
【eラーニング導入】企業側のメリット
eラーニングを導入することによる企業側のメリットは、以下の3点が挙げられます。
- 学習の質や学習機会を均一化しやすい
- 進捗状況等を一元管理できる
- 研修コストの削減につながる
これまで部門や日程ごとに異なる講師が実施していた研修の場合、講師によって内容や質が変わることがありました。eラーニングであれば、録画教材などを活用することで、研修の内容や質を均一に保つことができます。
また、eラーニングシステムを導入し活用することで、社員全員に対する教材の一斉配信だけでなく、一人ひとりの社員のスキル・知識レベルに合った教材の配信といった個別対応ができます。その結果、少ない運営工数で、様々な学習機会を提供する環境整備がしやすくなります。
eラーニングシステムを導入すると、学習進捗や学習履歴のデータを数値で管理することができます。ダウンロードしたデータを分析して、研修内容や人材育成施策の改善につなげることが可能です。研修の出欠や提出物などの管理もeラーニングシステム(LMS)の機能で一元管理できるため、人材育成全体の運営を効率化することができるでしょう。
さらに、コストの面でもメリットがあります。資料の印刷代、会場費用、講師の登壇料といった研修実施にかかるコストを大幅に削減できるだけでなく、従来の集合型研修で必要だった研修日程の調整などの管理工数も減らすことができます。特に、大規模な研修ほど管理工数は増えてしまうため、LMSの導入や活用がおすすめです。eラーニング導入によって運営にかかる負担が軽減できれば、より良い人材育成施策の立案や研修企画に注力することができます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニング活用のためのポイント
eラーニングは受講者側にも企業側にもメリットがあります。反面、eラーニングの有効活用のためには押さえておきたいポイントもいくつかあります。
ここでは、eラーニング導入の際のポイントや対応についてご紹介します。
モチベーションの維持が難しい
eラーニングは「いつでも・どこでも」学べることがメリットですが、集合研修のように時間や場所が決まっていないことから、学習のモチベーション維持が難しいと言えます。特に業務が忙しいと研修は後回しになり、eラーニングの受講率が低いという状況に陥りやすくなります。
対策として、eラーニング受講の成果を人事評価に組み込んだり、eラーニングの受講を集合研修に参加する必須条件とするなどの仕組み作りが必要です。
実技が必要な内容にはeラーニングは不向き
eラーニングは、基本的にスライドや動画を確認して学習する方法であるため、実技が必要な内容は、eラーニングでの学習は困難です。
対応策としては、事前情報としてeラーニングで学習し、実技が必要な部分は集合研修で行うなど、他の研修と組み合わせる手法が考えられます。
システムの導入コスト、利用料がかかる
eラーニング研修を自社で効果的に実施するには、eラーニングシステムの導入が不可欠ですが、eラーニングシステムの導入には、初期費用や月額利用料といったコストが必要です。
一方で集合研修では前述の通り交通費や宿泊費などのコストが発生します。両者を長期的な観点で比較した場合、コストパフォーマンスはeラーニングのほうが高いといえるでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングシステム(LMS)導入に必要な費用
ここで、eラーニングシステムの導入に必要な費用を確認しておきましょう。
LMSは、サーバーの種類によって「クラウド型」と「オンプレミス型」に分けられます。
クラウド型LMSの費用相場は、以下の通りです。
クラウド型 | 費用相場 |
|---|---|
初期費用 | 0円〜100万円程度 |
ユーザー数100人まで | 5万円〜12万円程度/月額 |
ユーザー数200人まで | 7万円〜15万円程度/月額 |
ベンダーによって異なりますが、料金形態としては初期費用+月額料金のサービスが多いようです。サービスによっては、初期費用の有無や金額に差があり、ユーザー数に応じてボリュームディスカウントがあります。
一方、オンプレミス型のサービスの場合の費用相場は以下のようになっています。
オンプレミス型 | 費用相場 |
|---|---|
ネットワーク、ハードウェア費用 | 30万円~100万円 |
ネットワーク構築費用 | 20万円~50万円 |
ネットワーク保守費用 | 40万円~100万円 |
このほかにも、自社運用をする際の人件費やサーバを置く場所にかかる費用が必要になるでしょう。
また、LMSには開発方法によって「パッケージ型」「オープンソース型」「フルスクラッチ型」という3つのタイプがあり、それぞれ導入にかかる費用が異なります。以下から解説します。
パッケージ型LMS
パッケージ型LMSとは、ベンダーが提供する構築済みのLMSを自社でカスタマイズし、導入するタイプです。
自社でゼロから構築しなくても、ハイクオリティなLMSが使える点が大きなメリットです。
完成されたLMSがパッケージになっているので、導入費用(購入費用)として100万円〜250万円ほどが相場となっています。カスタマイズにかかる開発費は10万円ほどになるでしょう。
オープンソース型LMS
オープンソース型LMSとは、一般公開されているソフトウェアのソースコードを利用してLMSを構築するタイプです。
相場はパッケージ型よりも安く、50万円〜250万円ほどです。自社にプログラム開発のリソースがあることが前提となりますが、パッケージ型と比較してより自由度の高い設計ができます。
フルスクラッチ型LMS
フルスクラッチ型LMSは、自社でゼロからLMSを構築するタイプです。
3つの方法の中で最も自由度が高く、完全にオリジナルのLMSを構築できます。ただ構築には、高度なシステム開発スキルが求められます。
フルスクラッチの場合は、搭載する機能によって導入費用が大きく変動します。そのため、相場は150万円〜1,000万円ほどになるでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングの導入方法

ここからは、具体的な導入方法をご紹介していきます。実際に導入する際は、部門横断で関係する部署が複数あるケースも少なくありません。その調整にかかる時間を見越して、余裕を持ったスケジュールを立てておきましょう。
クラウド型LMSを利用する場合は、以下のようなステップで進めます。
- LMS利用の要件を再度確認し、利用方法を確定
- LMSの機能の設定
- データの登録
- 運用方法の確定
- 一部組織でのテスト利用の実施
- 全社への公開、利用開始
各ステップごとに細かく解説します。
LMS利用の要件を再度確認し、利用方法を確定
まずは、LMSを利用する要件を再度確認し、どのように利用するかを確定しましょう。
人材育成に使用する場合「集合研修と組み合わせて利用する」「集合研修の一部をeラーニングにする」「社内大学として活用する」など、活用方法は企業によってさまざまです。
自社の課題や目的に合わせて、LMSをどのように利用するのか、どのような施策を実施するのかを確定しましょう。
LMSの機能の設定
次に、LMSの機能の設定を行います。ここでは、以下のような設定を行います。
- 画面デザインの設定
- 登録するデータ項目の決定・設定
- 権限の設定
- 自動送信メールの設定
- コンテンツのカテゴリの設定
- 他システムとの連携設定
ここでコンテンツを分けて管理したり、自動送信メールの設定をしたりしておくことで、スムーズに運用ができます。
データの登録
次に、LMSの社内運用に必要な各種データを登録していきます。主な内容は下記3つです。
- eラーニングコンテンツの登録
- 社員情報の登録
- 組織情報の登録
社員情報を登録しておくことで、人材配置の管理がしやすくなり、階層別の研修も行いやすくなるでしょう。
例えば「入社1年未満の新入社員」「入社3年未満の若手社員」「入社5年以上の管理職」などで絞りこみ、必要な研修の連絡をする、というような使い方ができます。
運用方法の確定
機能設定やデータの登録が完了したら、運用方法を確定していきましょう。
検討する主な項目は以下の4つです。
- 管理体制の整備と各役割分担の確定
- マニュアルの作成(管理者用マニュアル・受講者用マニュアル)
- 社内問合せ先の設定と周知
- 受講履歴の確認・分析方法の確定
LMSを管理する人は誰なのか、管理体制の構築や役割分担の確定、LMSを使う際のマニュアルの作成、ヘルプデスクの構築、受講履歴の確認や分析方法をそれぞれ決めていきましょう。
一部組織でのテスト利用の実施
設定や運用方法が確定したら、一部組織でのテスト利用を行いましょう。
- LMSの動作確認、改善
- 運用面の問題点の抽出、改善
この二つのステップで進めることがおすすめです。エラーなどが起こった場合の対処や、運用方法の見直しなどを行い、本格的に運用する前に小さなトラブルを無くしていきます。
想定されるエラーを洗い出し、対処法をマニュアルに記載するなどの準備をしておくとスムーズに運用できます。
全社への公開、利用開始
テストが完了したら、全社への公開と利用を開始します。ユーザーに利用案内を配信して、運用を開始します。コンテンツの配信日に、メールを自動送信できる機能を活用するケースが多いです。
社内で対応できる体制の構築に加えて、ベンダーのサポートも欠かせません。導入してからしばらくは、ベンダーの支援を利用しながらLMSの活用を進めていきましょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングの導入事例
ここまでは、eラーニングのメリットや導入の流れを解説しました。しかし、導入後にどのような方法で活用すればよいのか、具体的なイメージが湧かないケースもあるでしょう。
ここでは、実際に弊社が提供しているLMSである「etudes」を利用していただいた企業の導入事例をご紹介します。
株式会社 メガネトップ様
「眼鏡市場」を日本国内に1,000店舗以上展開し、近年は海外にも進出している、国内眼鏡市場No.1メーカー「株式会社 メガネトップ」様。
一人ひとりのニーズに沿った学びを提供するためには、研修のオンライン化や集合型研修だけでは課題が多いと感じていました。そこで、スタッフが任意に受講できる選択型研修でetudesを導入していただきました。
いつでも受講できる環境を用意するだけではなく、お知らせをタイムリーに配信すること、コンテンツの鮮度を高める段階的なリリース、スタッフへの認知向上のためのパンフレット配布などを企画・実行しています。
その結果、選択型研修であるにも関わらず20%以上のスタッフが受講することとなりました。今後は集合型研修をオンラインで実施する場合や、集合型研修とeラーニングを併用する場合にetudesを活用したいとのお声をいただいています。
詳しくは『メガネトップ様 etudes導入事例』をご覧ください。
株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ様
2017年に派遣人材教育のためのeラーニングプラットフォームとして、etudesを採用していただいている「株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ」様。
小売業界初の国家資格「接客販売技能検定」の対策コンテンツを開発し、etudesのシステム上での対策講座販売サービスを展開しています。
受講した方からは、『何回も繰り返し学べるので、試験を受ける際に、自分はしっかり勉強してきたという安心感を持って臨むことができた』という声もいただいているようです。
詳しくは『三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ様 etudes導入事例』をご覧ください。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
クラウド型eラーニングシステムなら「etudes」
アルー株式会社が提供している「etudes」は、人材育成の専門家が開発した、国産のクラウド型eラーニングシステム(LMS)です。
初期費用はゼロで、利用者数に応じた月額の課金制というシンプルな料金体系ですので、eラーニングの導入がはじめてという方でも、スモールスタートがしやすくなっています。
また、受け放題の豊富なコンテンツを提供する「etudes Plus」では、実践的な内容を取り入れた100種類以上の教材を使い放題で、効果的な人材育成をすぐに始められます。eラーニング教材の作成支援も行っていますので、自社独自の教材を作成したいという方もぜひご利用ください。
etudesの詳しい製品紹介を知りたい方は『製品紹介資料』をダウンロードしてください。etudesの特徴やデモ画面、費用についてご紹介しています。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
この記事では、eラーニング導入を成功させるポイントについて解説しました。
eラーニング導入を検討している会社は増えていますが「導入したのになかなか浸透しない」「効果的に使えていない」という企業が多いのも現状です。
このような事態にならないためにも、eラーニング導入前には、6W1Hにそって「eラーニング導入の目的・使用方法」「自社に合ったLMSの選定」「教材作成の有無」などを明確にしておくことが大切です。
この記事を参考にして、eラーニング導入を成功させましょう。