
研修の効果測定方法とは?カークパトリックモデルの活用法や具体例をご紹介
研修は、社員のスキルアップや組織全体の成長を促進する重要な取り組みです。しかし、研修を行ったからといって、必ずしも効果が出るとは限りません。研修効果を最大化するためには、研修の効果測定が大切です。eラーニングシステムを導入すれば、研修の効果測定を効率化できます。本記事では、研修の効果測定を行うメリットや研修の効果測定方法を詳しく解説します。
他社での実施例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
研修の効果測定が必要な理由
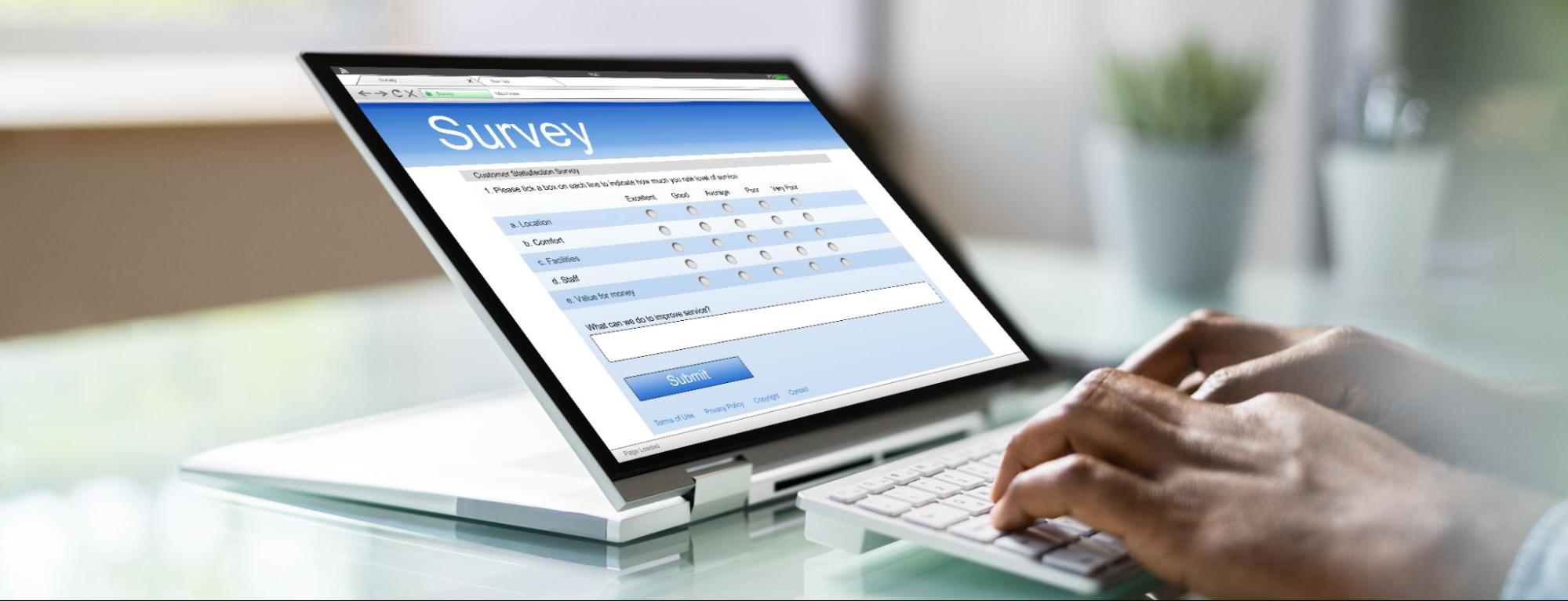
研修の効果測定が必要な理由は、研修の満足度に始まり受講者の行動変容による組織への影響に至るまで、長期的な視点で評価するためです。効果測定をすることで、社員の能力向上の度合いや業務効率の改善点が具体的に把握できます。効果があまり出ていないことがわかれば、研修内容の見直しや受講者への個別フォローなど、具体的な施策を講じられるでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
カークパトリックモデルを活用した研修の効果測定方法
研修の効果測定には、カークパトリックモデルの活用がおすすめです。
カークパトリックモデルでは、反応・学習・行動・成果の4つのレベルで評価を行います。各レベルで適切な評価指標を設定し、段階的に効果を測定することで、研修の成果を多角的に把握できます。
レベル1:反応
レベル1は、研修直後に受講者の反応を見る段階です。
受講者の反応を測るには、アンケートを用いるのが一般的で、内容を鮮明に覚えている研修直後に実施します。
アンケートの結果、研修の満足度が低いことがわかれば、研修プログラムの改訂や講師の変更などを検討します。
アンケート項目の例
研修の効果を測定するアンケートは、研修の狙いに沿った内容にしましょう。
具体的には、下記のようなアンケート項目と目的が考えられます。
アンケート項目 | 目的 |
|---|---|
受講時間や期間は適切でしたか? | 研修のボリュームが受講者のニーズに合っていたかを確認 |
講義や講師の説明、資料はわかりやすかったですか? | 講師の質や資料のわかりやすさを評価 |
受講して得られたことは何ですか? | 受講者に研修内容を振り返らせ、得られた成果を具現化 |
研修で得られたことをどのように業務に活かしますか? | 受講者が今後の実務への活用方法を認識 |
今後受講したい研修やテーマがあれば教えてください | 受講者のニーズを確認し、今後の受講カリキュラムや企画に反映 |
研修の目的に沿ったアンケート項目にすることで、受講者の反応を把握できます。
研修後アンケートの実施方法については、下記の記事で詳しく解説しています。
『研修後アンケートの実施方法|テンプレートや効果的な実施のコツ』
レベル2:学習
レベル2は、受講者が研修内容を十分に理解できているか否かを評価する段階です。
研修で学んだ知識やスキルが、どの程度身についているかを、研修から数日後に測定します。理解度を調査する方法としては、研修内容に関する理解度テストやレポート提出などが考えられます。テストでは、研修で扱った重要なポイントを問う設問を用意し、受講者の習得度を確認します。レポートでは、研修内容を自分の言葉で説明させることで、知識の定着度を測れるでしょう。
テストやレポートの結果から、しっかりと理解していると判断できた場合は、レベル2に達していると評価できます。一方、理解が不十分だと判断された場合は、フォローアップ研修やeラーニングの受講など、理解度を高める施策が必要です。
レベル3:行動
レベル3は、研修後3ヶ月から半年のタイミングで、研修で学んだことを実践できているかどうかを評価します。
評価項目としては、「研修で学んだ知識やスキルを現場で発揮できているか」「研修前と比べて行動にどれほど変化があったか」などが考えられます。評価の際は、評価基準を明確にし、評価者間で認識を合わせておくことが重要です。
評価の結果、受講者の行動に変化が見られない場合は、研修内容の改善やフォローアップ研修の実施、現場環境の整備などを行います。
レベル4:結果
レベル4は、受講者の行動変容によって生み出された成果を評価する段階です。研修で学んだことを実践に移した結果、組織にどのような影響があったのかを、研修後半年から1年以内のタイミングで調査します。
具体的な方法としては、ROI分析が挙げられます。ROI分析とは、投じた費用に対してどれだけの効果を上げられたのかを測定する投資対効果の分析手法です。ROI分析では、研修による成果の増加分を研修費用で割ることで、投資対効果を算出します。
例えば、営業研修を実施した結果、受講者の成約件数が20%増加し、売上が1,000万円アップしたとしましょう。研修費用が100万円だった場合、ROIは10倍(1,000万円÷100万円)となります。このように定量的な指標を用いることで、研修の効果を可視化できます。
ROI分析の結果、投資対効果が低いことが判明した場合は、効率的な研修方法への変更など、投資対効果を高める施策が必要でしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
研修の効果測定を行うメリット

研修を実施する際に、適切な効果測定を行うことで以下のようなメリットが期待できます。
- 費用対効果を適正にできる
- 研修内容の改善ができる
- 結果に応じて個別にフォローできる
それぞれ、詳しくご紹介します。
費用対効果を適正にできる
研修の効果測定を実施することで、研修にかかる費用に見合った成果が得られているか否かを定量的に把握できます。
例えば、集合研修の場合、講師料や会場費、教材費など、多くの経費が発生します。効果測定の結果、効果が低いことがわかれば、実施回数の見直しや内容の改善などの判断を下すことで、経費の適正化につなげられるでしょう。
このように研修の効果測定は、限られた予算を有効活用する重要な指標となります。
研修内容の改善ができる
測定の結果、研修の内容に課題があると判断できた場合は、改善を行いましょう。研修内容の改善を行うことで、受講者の理解度や満足度の向上、さらには研修の目的達成につなげられるでしょう。
具体的な改善ポイントとしては、下記が考えられます。
改善策 | 内容 |
|---|---|
講師の選定 | 受講者の理解度が低い場合は、講師の教え方や知識経験不足が原因の可能性がある 受講者のレベルや職種に合った講師を選定することで、学習効果の向上が期待できる |
カリキュラムの見直し | 受講者のニーズや習熟度に合っていない |
研修の実施方法の変更 | 集合研修だけではなく、eラーニングを組み合わせる |
資料の改善 | わかりにくい資料では、受講者の理解が進まない |
測定結果から改善点を洗い出すことで、研修の質を高め、より効果的な研修を実現できます。
結果に応じて個別にフォローできる
研修の効果測定を行うことで、受講者一人ひとりの理解度や習熟度を把握でき、個別のフォローが可能となります。
例えば、知識は深まったものの実践が不足しているという結果が出た場合は、OJTを実施することで、研修で得た知識を業務に活かせるようにサポートできます。一方、知識が不足しているという結果であれば、追加コンテンツなどのeラーニング受講を促すことで、理解度の向上を図れるでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
研修の効果測定を行うポイント
研修の効果測定を行うポイントは、下記の通りです。
- 評価の目的を明確にする
- 定量と定性の指標で評価を行う
- いつ評価を実施するのかを決める
評価の目的を明確にする
研修の効果測定を行う際は、評価自体が目的化しないよう注意が必要です。
評価は研修の質を測るためではなく、研修の目的達成度や受講者の成長度合いを確認するために実施します。
具体的な評価の目的には、下記のようなものが考えられます。
- 研修内容の改善:受講者の反応や理解度から、研修内容の改善点を見つける
- 受講者の行動変容:学んだ知識やスキルが、業務でどの程度活用されているか確認する
- 組織への貢献:研修が組織の目標達成に、どの程度寄与しているか評価する
評価の目的を明確にすることで、正しい評価指標の設定や効果的なフォローアップにつなげられます。
定量と定性の指標で評価を行う
研修の効果を適切に測定するには、評価基準や評価項目を事前に設定しておく必要があります。評価の基準や項目は、研修の目的に応じて、定量的なものと定性的なものの両方を設定しましょう。「定量」とは数値として計測できる客観的な評価項目で、以下のような例が挙げられます。
定量的な目標
- 営業目標の達成率
- 業務ミスの発生率
- クレームの件数
一方、「定性」とは、受講者の意識変化や理解度を把握する、数値化が難しい指標を指します。
定性的な目標
- 受講の質問・発言の積極性
- 上司や営業リーダーからのフィードバック
- 研修内容を実務に応用しようとする姿勢
定量と定性の両面から評価することで、研修の効果をより正確に測定できるでしょう。
いつ評価を実施するのかを決める
カークパトリックモデルを用いて研修の効果測定を行う際は、各段階の評価をいつ実施するかを事前に決めておきましょう。
具体的には、下記のような時期が考えられます。
- レベル1:研修直後
- レベル2:研修から数日後
- レベル3:研修から3ヶ月後
- レベル4:研修から1年後
また、研修の目的や内容によって、どのレベルまで評価を実施するのかを決定し、研修の際に受講者に伝えておきましょう。あらかじめ伝えておくことで、受講者の意識が高まり、学習効果の向上が期待できます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
研修の効果測定でよくある課題
研修の効果測定では、効果が現れるまでの期間の見極めが課題となります。
知識やスキルの向上は短期的に測定できますが、行動変容や組織への影響は長期的な視点が必要です。そのため、測定すべき期間の設定が難しく、効果測定の実施に踏み切れないケースがあります。また、研修後に業務改善が見られたとしても、それが研修の効果によるものなのか、他の要因によるものなのかの特定が難しいという課題もあります。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
研修の効果測定にはeラーニングシステム
研修の効果測定は、eラーニングシステムを導入することで、効率化できます。
eラーニングシステムを活用すれば、研修後のアンケートやテスト、レポートの提出を一元管理できるため、運営の効率化ができます。また、アンケートやテストの結果から、思ったようにスキルが伸びていないと判断された場合は、追加の研修やコンテンツの受講を促すことで、フォローアップできるでしょう。さらに、システムにログインすれば、受講者の受講履歴などの情報が一目でわかるため、関係者との情報共有もスムーズに行えます。
研修の効果測定にeラーニングシステムを活用するメリットを、以下からご紹介します。
受講者の理解度を見える化できる
eラーニングでは、各コンテンツごとのテストの結果を自動で蓄積できるため、理解度を定量的に測定できます。
どの項目で正答率が低かったか、どの設問に時間がかかったかといった詳細なデータが取得でき、受講者のつまずきポイントを可視化できます。また、受講後アンケートでの定性評価も組み合わせることで、知識定着度だけでなく、意識や態度の変化も含めた総合的な評価が可能になります。
受講データを自動で蓄積・レポート出力できる
eラーニングシステムを活用すれば、受講の進捗状況や研修の出席率などのデータも自動的に蓄積できます。これにより、個別に確認したり手作業で集計したりする手間が不要になります。
さらに、システムによってはグラフ付きのレポートを自動生成できる機能もあり、管理者は一目で全体の習熟度や課題を把握可能です。継続的な効果測定と研修改善にはなくてはならない機能といえるでしょう。
測定結果に基づいたフォローアップもしやすい
eラーニングシステムを導入することで、テスト結果や受講履歴に基づいた個別フォローが容易になります。たとえば、特定のテーマで理解度が低かった受講者に対して再受講を促したり、補足資料を配信したりといった対応が自動化できます。また、受講者ごとの状況に応じたメール配信やリマインドも可能となり、教育効果を高めるフォローアップ体制が構築できます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
研修の効果測定を効率化するツールならetudesがおすすめ

引用元:etudes公式サイト
研修の効果測定を効率化するツールなら、etudesがおすすめです。
etudesは、アルー株式会社による長年の人材育成ノウハウを活かして開発された、eラーニングシステムです。わかりやすいUI/UXを採用しており、操作方法に悩むことなく、すぐに使いこなせます。
テスト・アンケート機能が充実
etudesは、研修の効果測定に必要なテストやアンケート機能が充実しています。
択一式・複数選択式・自由記述式など、様々な設問タイプを用意しており、研修内容に合わせて最適な方法で理解度や満足度を測定可能です。また、過去に実施したすべてのテストやアンケートの結果を管理画面で確認できるため、受講者の理解度や満足度の推移を把握できます。さらに、テストやアンケートの結果は別の形式でエクスポートできるため、データを活用した意思決定に役立てられます。
LMSのアンケート機能の特徴やメリットについては、下記の記事で詳しく解説しています。
『LMSのアンケート機能の特徴やメリットとは?自社に適した選び方も解説』
柔軟に権限設定ができる
etudesでは、14種類の管理者権限を設定できるため、研修の効果測定結果を閲覧できるメンバーを柔軟に設定できます。
例えば、経営陣や管理職、人事担当者だけが測定結果を閲覧できるよう権限を付与すれば、機密性の高い情報を適切に管理しつつ、研修の改善や受講者への個別フォローに役立てられるでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
本記事では、研修の効果測定を行うメリットや研修の効果測定方法を解説しました。
研修の効果を測定することで、費用対効果の適正化や研修内容の改善、受講者への個別フォローが可能になります。カークパトリックモデルを活用すれば、研修の成果を多角的に把握できます。eラーニングシステムを導入することで、研修後のアンケートやテスト、レポートの提出を一元管理できるため、研修の効果測定を効率的に行えます。本記事を参考に、研修の効果測定を導入し、より良い人材育成を目指しましょう。











