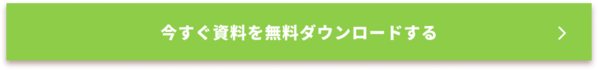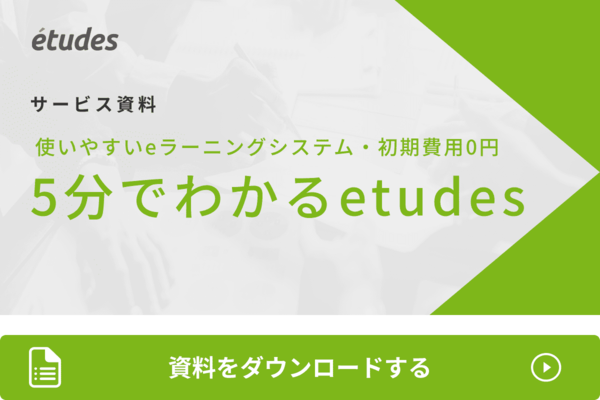eラーニングのプラットフォーム6選をご紹介。企業の研修に必要な機能や選び方は?
eラーニングのプラットフォームとは、eラーニングの受講や配信に利用するシステムのことで、「LMS(学習管理システム)」と呼ばれています。プラットフォーム上でeラーニング教材を配信することで、受講者の学習管理や教材のレコメンドが効率的にできます。
本記事では、eラーニングのプラットフォームの機能や種類、選び方や、人材育成でeラーニングを活用するメリットについて詳しく解説します。プラットフォーム選定について詳しく知りたい方は「LMS選定で考えるべきポイント6選」の無料ダウンロードもおすすめです。
また、用途別に複数のプラットフォームを比較し検討したいとお考えの方は「eラーニング比較検討表」をダウンロードしてください。
実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
- 1.eラーニングとは
- 1.1.学習管理システム(LMS)とは
- 2.eラーニングプラットフォームの機能
- 3.eラーニングプラットフォームの種類
- 4.eラーニングプラットフォームを導入するメリット
- 4.1.学習状況を把握しやすい
- 4.2.無駄な手間やコストを削減できる
- 4.3.教育のレベルを揃えられる
- 5.eラーニングプラットフォームの活用シーン
- 5.1.新卒社員教育
- 5.2.社内研修
- 5.3.社外向けコンテンツ配信
- 6.eラーニングプラットフォームを選ぶポイント
- 7.eラーニングプラットフォームおすすめ6選
- 7.1.etudes
- 7.2.Schoo for business
- 7.3.学び~と
- 7.4.LearningWare
- 7.5.LearnO
- 7.6.ひかりクラウド スマートスタディ
- 8.eラーニングプラットフォームを導入する流れ
- 9.まとめ
eラーニングシステムetudesが分かる2点セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
eラーニングとは
eラーニングとは、パソコンやスマートフォン、タブレットなどを利用して学習をする学習形態のことです。electronic Learningの略称で、直訳すると「電子的な学習」となります。
現在はwebを利用したeラーニングが一般的ですが、1990年代にはCD-ROMを利用したeラーニングが行われていました。、CD-ROMによるeラーニングには、
- 一度配布したら内容修正が困難
- 制作にコストがかかる
- コミュニケーションが単一方向
といったデメリットがありました。それを解決する方法が、webを利用したeラーニングと、「LMS(学習管理システム)」です。
webを利用したeラーニングは、内容の更新性が高く、コストも抑えられます。近年ではライブ配信などの双方向的コミュニケーションも取れるようになり、新しい機能は今後も続々と増えていくことでしょう。
eラーニング導入に必要な基礎知識を知りたい方は、こちらから「eラーニング導入に向けた基礎知識集」をダウンロードしてください。eラーニングの特徴や種類についてご紹介しています。
学習管理システム(LMS)とは
eラーニングは、LMSと呼ばれるシステムによって、その利便性を高めています。LMSとは、Learning Management Systemの略称で、直訳すると「学習管理システム」となります。
分かりやすく言うと、LMSとは、eラーニングのプラットフォーム(土台)となるシステムのことです。LMSを介してeラーニング教材を配信することで、以下のような機能を利用できます。
- 受講者の学習進捗をリアルタイムで確認・管理
- 受講者の学習データ蓄積
- 受講者ごとの学習コース管理
- テストやアンケートの作成・配布
- テストやアンケート結果のデータ蓄積
- 学習教材の保管・蓄積
手動では工数が増えがちな研修管理業務が、LMSによって自動化でき、効率がアップします。LMSは、eラーニングを便利に活用するために必要不可欠なプラットフォームだと言えるでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングプラットフォームの機能
先述した、eラーニングプラットフォームとしてのLMSの機能について、より詳しく見ていきましょう。
- 受講者情報の管理
- 学習進捗の管理
- 教材の管理・配信
それぞれの機能について、解説していきます。
受講者情報の管理
まず、LMSの代表的な機能は、受講者情報を管理できることにあります。たとえば、入社してから1週間が経った新入社員に絞って新入社員研修を行うとき、受講者情報が登録されているプラットフォームを利用すれば、自動的に対象者にeラーニング教材を配信することができます。
プラットフォームを使わない場合は、対象者一人ひとりに担当者からメールを送る必要があり、大規模運用になればなるほどこの作業は手間がかかるでしょう。
学習進捗の管理
学習者の学習進捗を管理することも可能です。誰が、どの学習コンテンツを、どのくらい学習したかを一秒単位で記録できるプラットフォームもあります。
テストの点数やアンケート内容をもとに、学習者一人ひとりにフィードバックを送ることも可能となります。eラーニングは、「いつでもどこでも学習が可能」というメリットがある一方、「いつでもできるから今はやらない」といった心理が働きやすいデメリットもあります。
eラーニングのプラットフォームがあれば、そのような学習者へのフォローアップも可能となり、モチベーションの向上にも効果があるといえます。
教材の管理・配信
eラーニングプラットフォームには、教材の管理・配信機能もあります。多くのプラットフォームが、さまざまなeラーニング教材のセットプランを販売しており、それらの教材の管理や、新たに購入した教材の配信が可能となっています。
また、教材を内製しプラットフォームに上げることが可能なLMSもあります。ベンダーによっては、教材の内製化の支援を行っているところもありますので、必要に応じてプラットフォームを選択するようにしましょう。
LMSの代表的な機能について詳しく知りたい方は、関連記事「eラーニングに役立つLMS(学習管理システム)の機能をご紹介」をご覧ください。弊社LMS「etudes」特有の機能もご紹介しています。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングプラットフォームの種類

eラーニングプラットフォームでは何ができるのかを確認したところで、次はその種類について見ていきましょう。
eラーニングプラットフォームには、以下の2種類があります。
- オンプレミス版
- クラウド版
それぞれ、どのような特徴があるのでしょうか。詳しくまとめていきましょう。
オンプレミス版
オンプレミス版は、自社のサーバーにLMSをダウンロードする形でサービスを利用する方法です。オンプレミス版のメリットは以下です。
- カスタマイズが容易に行える
一方、デメリットは以下です
- 導入にコストと期間がかかる
- サーバーを置く場所が必要になる
自社で運用するサーバーにダウンロードを行うため、プラットフォームのカスタマイズが容易に行えます。一方で、後に紹介するクラウド版より導入にコストがかかったり、サーバーを置くスペースが必要になったりとデメリットもあります。
クラウド版
クラウド版は、仮想環境に構築されたシステムを利用するSaaSサービスです。クラウド版には以下のメリットがあります。
- 安値で導入ができる
- 導入までの期間がオンプレミス版より短い
一方、デメリットは以下の点です。
- サービスが終了する可能性がある
- 同時接続数が多くなると速度が遅くなる場合がある
既に作成されているSaaSサービスを借りるため、導入までに時間がかからないという特徴があります。また、サーバーを用意する必要もないため、比較的安価に導入が可能でサーバー設置場所も必要ありません。一方、サービスが終了する可能性があるなど、オンラインサービスならではのデメリットもあります。
クラウド型とオンプレミス型の比較について詳しく知りたい方は関連記事「クラウド型eラーニングとは?オンプレミス型との比較とメリットについて」をご覧ください。クラウド型eラーニングである「etudes」の導入事例もご紹介しています。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングプラットフォームを導入するメリット
eラーニングプラットフォームを導入するメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- 学習状況を把握しやすい
- 無駄な手間やコストを削減できる
- 教育のレベルを揃えられる
これらのメリットについて、下記で詳しく見ていきましょう。
学習状況を把握しやすい
集合研修を行った場合、対象となる人に研修を行った事実は残りますが、一人ひとりがどの程度理解をしたかの把握は難しいです。アンケートでどの程度理解したかを知ることはできますが、主観的な意見は正しくない可能性もあります。
eラーニングプラットフォームを利用すれば、一人ひとりがどの学習を、どの程度理解しているかを客観的な情報として収集することができます。たとえば、ある学習コンテンツを視聴し終わった後に、テストを実施します。その点数によって、どの程度理解したかを客観的に把握することができます。
学習状況が芳しくない人には、個別に指導やリマインドを行うことも可能となります。このように、eラーニングプラットフォームを導入すると、学習者一人ひとりの学習状況を把握しやすくなる点が大きなメリットです。
無駄な手間やコストを削減できる
eラーニングプラットフォームを導入すると、集合研修で発生する多くの手間とコストを削減できます。削減できるコストや手間は以下のようなものがあります。
- 会場費
- 講師代
- 昼食代・宿泊費
- 資料印刷費
- 研修場所手配の手間
- 講師手配の手間
- 昼食や宿泊施設手配の手間
- 資料作成の手間
集合研修では、研修を行う度にこれらの費用が必要になりますが、eラーニングでは、場合にもよりますが、必要な「講師代」が一度のみにとどまります。集合研修では、研修の規模が大きくなればなるほど、これらの負担は大きくなっていくでしょう。
教育のレベルを揃えられる
たとえば、2回集合研修を開き、それぞれに20人ずつ、計40名に研修を行うとします。第1回と第2回の集合研修は、スケジュールの関係で違う講師を呼ぶことになりました。このようなケースでは、第1回と第2回の集合研修で、教育のレベルを揃えることは困難になります。同じ内容を教えたとしても、一言一句同じ文言で教えられる人間はいないでしょう。講師のその時の言い回しや、質問の有無など、多くの要因により、集合研修で教育のレベルを揃えることは至難の業です。
一方eラーニングプラットフォームを導入すれば受講者がどれだけ増加しても、全ての人が同じ学習コンテンツで学ぶことができます。
一
人ひとりの教育のクオリティを揃えるために、eラーニングプラットフォームは最適です。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングプラットフォームの活用シーン

eラーニングプラットフォームは、社内利用はもちろん、社外向けのコンテンツ販売にも活用されています。eラーニングプラットフォームの活用シーンについて、以下の3つに分けてご紹介します。
- 新卒社員教育
- 社内研修
- 社外向けコンテンツ配信
新卒社員教育
eラーニングは、毎年決まった時期に行われる新卒社員教育に対して、親和性が高い特徴があります。新卒社員教育は内容が一定であることが多く、一度eラーニングコンテンツ化してしまえば、繰り返し使用できるためです。もちろん都度の修正は必要となりますが、集合研修よりコストを削減できます。
基本的なビジネスマナーなどの内容だけであれば、パッケージ化された商品を購入し使用することも可能です。
社内研修
eラーニングプラットフォームは、社員に対してオンライン上の「学びの場」を提供できます。
「若手社員向け」「チームリーダー向け」「部長職向け」など、さまざまなセットプランを活用したり、「ビジネススキル」や「考え方・価値観」などのテーマ別から選択したりと、多岐に渡る社内研修が活用できます。
既存の社内研修の資料やマニュアルをeラーニング化することも可能です。また、職種によっては、実技研修と組み合わせることにより社内研修の幅は大きく広がることでしょう。
社外向けコンテンツ配信
eラーニングプラットフォームは、社内のeラーニング研修だけではなく、社外に向けて教材を有料で配信するといった用途でも活用されています。
自社の専門的な知識・スキルをeラーニング教材にし、学びたい個人や企業に向けて販売することで、新たな収益源を得ることができます。
eラーニングプラットフォームならオンラインでのアクセスが可能なため、時間や場所に縛られることなく学習でき、広範囲な受講者層をターゲットにできます。このようなプラットフォームを活用することで、ブランド認知度の向上や新たなビジネスチャンスを生み出すことができるでしょう。
eラーニングプラットフォームを活用した社外向けビジネスについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。
『自社コンテンツはどこで販売すれば良い?販売の流れや注意点を解説』
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングプラットフォームを選ぶポイント

ここからは、eラーニングプラットフォームを選択するポイントについてまとめていきます。
- 教材内容
- オリジナルeラーニング教材配信の可否
- 対象人数
- 操作性
- 汎用性/互換性
- 料金体系
以下にて、詳しく見ていきましょう。
教材内容
プラットフォームを導入し、eラーニングを配信する際に必ず必要なのが「教材」です。
プラットフォームのベンダーがeラーニング教材も合わせて提供している場合は、教材の充実度が選定のポイントとなります。
自社で教材コンテンツを作ろうと考えている場合は、教材作成ノウハウを持っていたり、教材作成サポートを用意していたりするeラーニングプラットフォームを選択するようにしましょう。
eラーニング教材を購入すべきか、自社開発すべきか詳しく知りたい方は関連記事「eラーニングの教材は購入すべき?開発すべき?良い教材のポイントも」をご覧ください。それぞれのメリット・デメリットをご紹介しています。
オリジナルeラーニング教材配信の可否
eラーニングプラットフォームを選定する際に、重要な基準の一つが「オリジナルeラーニング教材配信の可否」です。自社で作成した独自の教材を配信できるプラットフォームを選ぶことで、より実務に近い内容を社員に学ばせることができます。また、先ほど「活用シーン」でご紹介したように、自社のノウハウや専門的なコンテンツを外部に提供することもできます。
また、教材の更新や管理が簡単に行えるかどうかも重要なポイントです。この機能を活用することで、法令の改訂や業務内容の変更にも柔軟に対応できます。
対象人数
続いてのポイントは、対象人数です。eラーニングプラットフォームは、利用人数の上限や下限が決まっている場合があります。少人数の運用に適していたり、大規模運用に適していたり、eラーニングプラットフォームによって特徴が違います。
小規模運用に適しているeラーニングプラットフォームは、数人から数十人、100人までといったものがあります。一方大規模運用に適しているものは、100人からや1000人から、上限なしで運用できるものもあります。
対象人数の上限がないeラーニングプラットフォームなら、数人の運用からはじめて、様子をみながら大規模運用に移行するスモールスタートも可能です。
操作性
操作性もeラーニングプラットフォームを選ぶ重要なポイントです。学習者が直感的に学習コンテンツを選択できるか、管理者が手間のかかる作業をせずに学習者の管理を行えるか、検討段階でしっかりと確認しておきましょう。
eラーニングプラットフォームの中には、学習コンテンツがパネル式で表示され、直感的に選択ができるようになっているものもあります。学習者画面と管理者画面のサンプルを確認して、実際に操作する時に不便でないかどうかイメージをしてみましょう。
汎用性/互換性
eラーニングプラットフォームが、互換性を持っているかどうかもポイントのひとつです。この「互換性」とは、SCORM規格に則って作成されているかどうかということになります。
SCORMとは、LMSと学習コンテンツの通信を統一化する標準規格のことです。SCORMが適応されているLMSを利用すると、異なるLMS間でも同じ学習コンテンツが利用できます。SCORMに沿って作成をすれば、あるLMSを利用している時に作成した学習コンテンツを、違うLMSでも利用できる、ということになります。
SCORM規格に対応しているかどうかは、長くeラーニングを利用していく中で、重要な検討のポイントとなるでしょう。
料金体系
eラーニングプラットフォームを検討するポイントとして、料金体系も重要になってきます。まず、初期費用がいくらになるかを確認しましょう。オンプレミス版か、クラウド版かによっても差がありますが、ここではクラウド版についてご紹介していきます。
クラウド版の初期費用は、1万円程度から100万円程度まで大きく差があります。一方で、初期費用無料のeラーニングプラットフォームもあります。
1ID毎に課金される料金体系もあれば、月額料金システム、年間利用料を設定しているところもあります。自社のニーズによって、最適な料金体系のeラーニングプラットフォームを選択するようにしましょう。
eラーニングの一般的な料金体系や相場について詳しく知りたい方は関連記事「eラーニングの開発費用、利用料金とは?料金システムと相場を解説」をご覧ください。クラウド型とオンプレミス型など、運用形態別の料金相場をご紹介しています。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングプラットフォームおすすめ6選
eラーニングプラットフォームは各社から提供されていますが、中でもおすすめのサービスを6選に絞ってご紹介します。
- etudes
- Schoo for business
- 学び~と
- LearningWare
- LearnO
- ひかりクラウド スマートスタディ
一つずつ、おすすめのポイントを見ていきましょう。
etudes
etudesは、企業向けに特化したeラーニングプラットフォームで、多くの企業で社員教育や研修に活用されています。
人材育成会社ならではの独自の階層別教材が豊富に揃っており、業務に直結した学びを提供しています。LMSとしての学習管理機能も充実しており、受講者の進捗管理や効果測定が簡単に行えます。管理者向けにレポート機能もあり、効率的な学習運営が可能です。
社内研修のための導入はもちろん、社外向けeラーニング販売のプラットフォームとしても多くの企業から選ばれています。
Schoo for business
Schoo for businessは、企業向けにオンライン研修を提供するeラーニングプラットフォームです。豊富なビジネススキルを学べるコンテンツを提供しており、動画を中心にインタラクティブな学習体験ができます。
社員のスキルアップをサポートするための教材が365日更新されており、コンテンツの充実度が魅力の一つです。
学び~と
学び~とは、学校法人駿河台学園が提供する、企業や自治体向けのオンライン学習プラットフォームです。オリジナル教材の作成しやすさが特徴で、柔軟な学習スタイルをサポートしてくれます。
社外向けのコンテンツを販売する上で、複数の企業に対して一つの教材を配信する際に役立つ「親子機能」など、独自の学習管理機能が魅力です。
LearningWare
LearningWareは、企業向けから教育機関まで幅広く対応しているeラーニングプラットフォームです。コンテンツの作成から配信、進捗管理まで一括で行え、特に企業内での研修や教育プログラムの効率化に役立ちます。
30以上の多言語に対応しているため、海外支社が多い場合や外国人従業員が多い企業におすすめです。
LearnO
LearnOは、シンプルで使いやすいインターフェースを持つ企業向けのeラーニングプラットフォームです。最短で1ヶ月のみの利用も可能という、導入のしやすさが魅力です。
自社オリジナルのWebセミナーを作成・配信したいというニーズに向けて、「Webセミナー代行」というオールインワンパッケージも提供しています。
ひかりクラウド スマートスタディ
ひかりクラウド スマートスタディは、NTT東日本が運営する、企業向けに特化したeラーニングプラットフォームです。初心者でも安心して導入できる、充実したサポート体制が特徴です。
学習管理機能には、自動採点機能だけではなく、自動添削(フィードバック)機能まで搭載されています。また、プラットフォームに対して大手運営による信頼性を求めている企業にも最適です。
eラーニングプラットフォームを導入する流れ
続いて、実際にクラウド型のeラーニングプラットフォームを導入する流れについてご紹介していきます。
- 調査・選定・契約
- 環境構築
- 運用準備・運用開始

以下にて、詳しくまとめます。
調査・選定・契約
まず調査を開始する前に、「なんのためにeラーニングプラットフォームを導入するのか」を明確にしておきましょう。導入目的を明確にした後は、eラーニングプラットフォームの調査を始めます。
さまざまあるeラーニングプラットフォームの中から、自社の目的に沿った教材を配信しているか、対象人数は最適か、UI/UXを追求しているか、SCORM対応をしているか、そして料金体系は最適かを確認し、候補を数社洗い出します。
次に候補企業に問い合わせを行い、不明点を明確にした後、候補企業の比較を行いeラーニングプラットフォームを一社に絞ります。
ここぞという一社を選択したら、契約段階に入ります。
環境構築
続いては、環境構築です。クラウド型のLMSを、カスタマイズせずにパッケージ導入する場合は、5日前後〜数週間で導入が可能でしょう。
カスタマイズをする場合は、数週間から数ヶ月の期間が必要になります。自社がどのような要望をeラーニングプラットフォームに対して持っているかによって、環境構築の期間は変動するため、余裕を持ったスケジュール設計が重要です。
運用準備・運用開始
eラーニングプラットフォームを導入する流れの最終段階は、運用準備・運用開始です。
- 標準版のeラーニングの操作研修
- 管理者権限の設定、パスワードポリシーの設定など、運用に関わる準備
- eラーニング教材作成
- サンプルデータでのテスト運用
- ユーザー情報や教材情報の登録
- eラーニング説明会の開催
などを経て、運用開始となります。場合によっても大きく異なりますが、2週間〜数ヶ月程度かかるでしょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
eラーニングのプラットフォームとなるシステム「LMS」は、受講者の管理や学習進捗の管理、教材の管理配信が行えるツールです。各企業によってeラーニングプラットフォーム導入の目的は異なります。導入目的に沿って、講座や教材内容を検討し、対象人数や金額を検討しましょう。
この記事でご紹介したプラットフォーム6選を参考に、自社に最適なシステムを探してみてください。