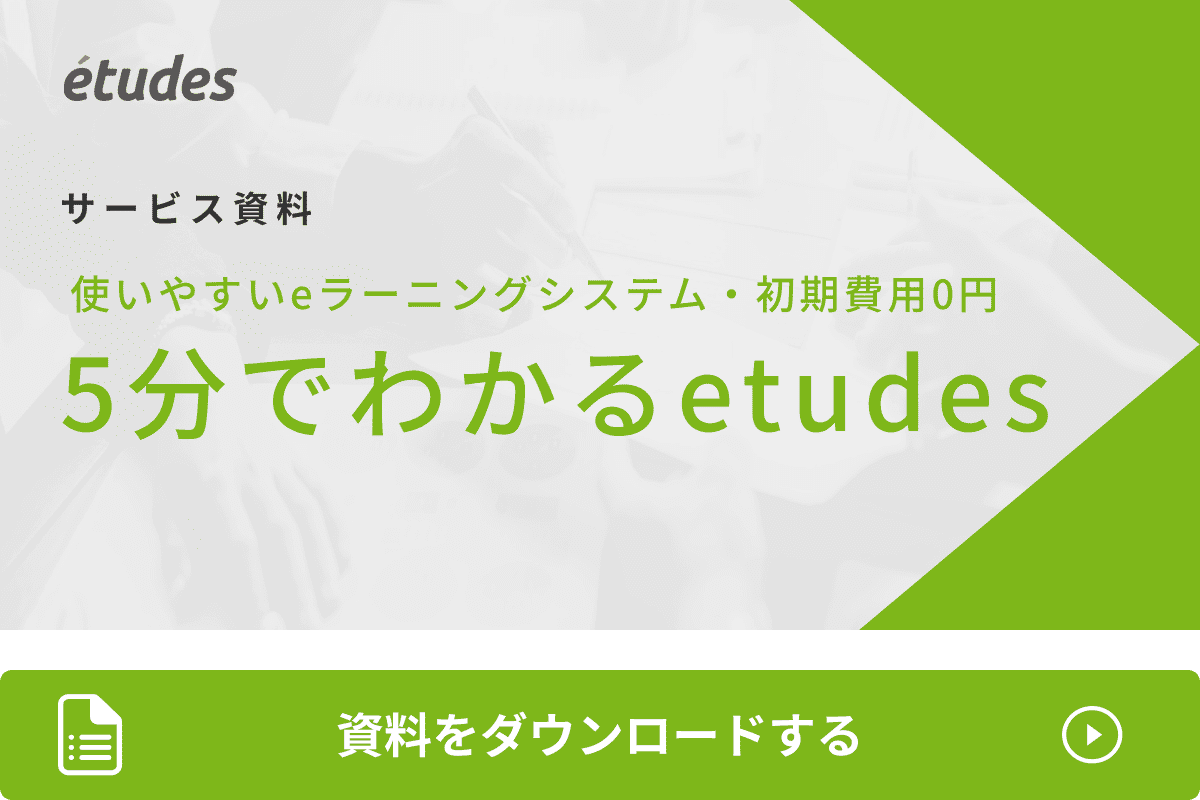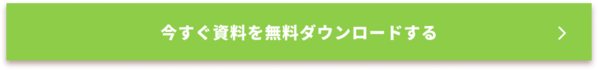eラーニングをスマホ・アプリで行うメリットは?システムの選び方も解説
eラーニングというとパソコンを使ってオンライン学習を行うイメージがありますが、最近ではスマホに対応しているeラーニングシステムも登場しています。中には、「eラーニングアプリ」というものもあります。
eラーニングシステムとは、eラーニングを管理し配信するシステムを指します。PC以外のデバイスでも視聴ができるeラーニングシステムを選ぶことで、スマホやタブレットでeラーニングを行うことができます。eラーニングアプリとは、eラーニングを受講するためにスマホ用に開発されたアプリのことです。
どちらも、スマホでeラーニング学習ができるようになる方法ですが、それぞれ違いがあります。
今回は、スマホで利用できるeラーニングのメリットと注意点、その選び方について紹介します。
実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
- 1.eラーニングはスマホでも受講できる?
- 1.1.eラーニングシステムとは
- 2.eラーニングをスマホで行う方法
- 3.スマホによるeラーニングの学習効果
- 3.1.マイクロラーニングができる
- 3.2.知識が必要な場面ですぐに確認できる
- 4.eラーニングをアプリ・スマホで行うメリット
- 4.1.時間や場所を問わず受講ができる
- 4.2.PCやメールアドレスが無い社員でも受講できる
- 4.3.操作が簡単
- 4.4.通知機能でリマインドが可能
- 5.eラーニングをスマホで行う注意点
- 5.1.実技を伴う研修が実施しにくい
- 5.2.モチベーション維持が難しい
- 5.3.セキュリティ対策が必要
- 5.4.学習画面が狭く操作性が下がる場合がある
- 6.スマホ対応eラーニングシステムを選ぶポイント
- 6.1.教材コンテンツの有無で選ぶ
- 6.2.自社で教材が作成可能かどうかで選ぶ
- 6.3.使いやすさで選ぶ
- 6.4.学習履歴管理が可能かで選ぶ
- 6.5.費用対効果で選ぶ
- 6.6.受講者数に対応できるものを選ぶ
- 7.スマホ対応のeラーニングなら「etudes」
- 8.まとめ
eラーニングシステムetudesが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
eラーニングはスマホでも受講できる?
eラーニングによるオンライン学習の需要は年々高まっており、「いつでもどこでも学習を進めたい」というニーズから、スマートフォンからも受講できる方法が登場しています。
スマートフォンでeラーニングを受講するには、スマホアプリを使用する方法があります。しかし、自社独自のノウハウや業務のマニュアルをオリジナルアプリで配信する場合は、既存のアプリを活用することができません。そのため、まずアプリの開発から始めなくてはならず、手間がかかってしまいます。
そこで、企業のeラーニングにおいては「スマホにも対応しているeラーニングシステムを導入する」という方法が一般的です。
eラーニングシステムとは
eラーニングシステムとは、eラーニングの教材を管理し、配信をするために必要なシステムです。学習管理機能も搭載されており、LMS(Learning Management System)と呼ばれています。
eラーニングシステム・LMSは、サーバー上にシステムとして構築され、受講者がインターネットを通じてアクセスすることでeラーニングの視聴ができます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングをスマホで行う方法
eラーニングをスマホで行う方法として、以下の3つが挙げられます。
- eラーニングのアプリを導入する
- 自社でeラーニングのアプリを開発する
- マルチデバイス対応のeラーニングシステムを利用する
それぞれの方法について、詳しくみていきましょう。
eラーニングのアプリを導入する
まずは、既存のeラーニングアプリを導入する方法です。
アプリストアで販売されている、英会話が学べるeラーニングアプリなどをインストールすることで導入が完了するため、最も手軽に始められる方法です。
ただし、自社の業務やサービスに特化した内容を学ぶことはできません。
自社でeラーニングのアプリを開発する
自社の業務やサービスに特化した内容を、アプリで学ばせたいという要望がある場合は、スマホアプリの開発から始める必要があります。
アプリ開発の専門業者に外注することで、教材としてのクオリティの高さが期待できますが、費用がかかります。
自社で内製すれば開発費用を抑えることができますが、eラーニング教材作りのノウハウがない場合は、開発期間が長くなるリスクがあるでしょう。
マルチデバイス対応のeラーニングシステムを利用する
アプリが無ければスマホでeラーニングができないわけではありません。上述のように、スマホに対応しているeラーニングシステムを利用すれば、PC・スマホ・タブレットからsafariやGoogle chromeなどのブラウザを通じて、eラーニングができます。
このように、PCだけでなくスマホやタブレットなど複数の端末で利用できることを、「マルチデバイス対応」といいます。
あらゆるデバイスから同じ教材にアクセスできるため、PCで視聴する時間が取れない時は移動中にスマホで視聴してカリキュラムを進める、といった学習方法が実現できます。
eラーニングシステムを導入するだけで完了するため、アプリを開発するための手間や費用も発生しません。
マルチデバイスによるeラーニングの実施方法に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
『スマホ・タブレットでeラーニングを実施!効果的な学習のポイントは?』
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
スマホによるeラーニングの学習効果
eラーニングはPCからの受講が一般的ですが、スマホで受講できるからこそ期待できる学習効果が存在します。
スマホによるeラーニングならではの学習効果として、以下の2点をご紹介します。
- マイクロラーニングができる
- 知識が必要な場面ですぐに確認できる
これらの学習効果が自社の社員教育に合っていると感じたら、マルチデバイス対応のeラーニングシステム導入を検討しましょう。
マイクロラーニングができる
マイクロラーニングとは、1分〜5分の短時間で学習する方法です。1回の勉強時間を、人間が集中を持続できる時間内に収めることで、以下のようなメリットがあります。
- 柔軟に学習できる
- 学習内容が定着しやすい
短い時間の学習を小刻みに行い、復習することで学習内容の定着が図れます。
また、研修を管理するうえで教材が適切に細分化されていると、学習教材の調整や修正がしやすいという利点もあります。
eラーニングによるマイクロラーニングの効果について詳しく知りたい方は『マイクロラーニングとは?メリットやコンテンツ作りのコツを解説』をご覧ください。
知識が必要な場面ですぐに確認できる
PCだけではなく、スマホからeラーニングの受講ができるようになると、知識が必要な場面ですぐに確認できます。
例えば、製造業の現場で次の作業を動画コンテンツで視聴しておくことで、正しい手順を把握できるといった効果が期待できます。また、営業ノウハウに関するeラーニング教材を出先で見直し、商談に備えるというケースもあるでしょう。
PCを持ち歩かなくても、いつでもどこでも必要な情報にアクセスできるのは、スマホ対応eラーニングならではの利点です。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングをアプリ・スマホで行うメリット
そもそも、eラーニングをスマホで受けることには、どのような利点があるのでしょうか?
eラーニングをスマホで行う4つのメリットを紹介していきます。
- 時間や場所を問わず受講ができる
- PCやメールアドレスが無い社員でも受講できる
- 操作が簡単
- 通知機能でリマインドが可能
それぞれのメリットを解説します。
時間や場所を問わず受講ができる
スマホでeラーニングを受講すると、時間や場所を問わずいつでも好きな時に学習できるという点が大きなメリットです。
たとえば、以下のようなシーンが想定されます。
- 電車での移動時間
- 仕事と仕事の間のスキマ時間
- テレワーク中の待機時間
- 打ち合わせの待ち時間
スマホを使って簡単にeラーニングができるので、スキマ時間を有効に使えます。教材にアクセスしやすくなるため、より積極的なeラーニング受講につながるでしょう。
PCやメールアドレスが無い社員でも受講できる
全社員に対してeラーニングを受講させたくても、一人一台PCを所有しているとは限りません。eラーニングのためにPCを支給するのは、コスト面で考えると現実的ではないでしょう。
スマホに対応しているeラーニングシステムならスマホさえあればeラーニングの受講が可能となります。
また、近年ではメールアドレスを持たない人も増えています。eラーニングシステムによっては、メールアドレスがなくてもユーザー登録が可能なので、システム選定の際のポイントとして注目しましょう。
操作が簡単
いつも使用しているスマホを使ってeラーニングを行うため、受講者は慣れた操作感でeラーニングを行うことができます。
アプリによるeラーニングは、スマホの画面に最適化されたUIとなっているので、PC操作に苦手意識を持っている受講者でもストレスなく学習をすることができます。
マルチデバイス対応のeラーニングシステムを利用する場合でも、シンプルでわかりやすい画面デザインが採用されていればアプリと同じように操作できるでしょう。
スマホやタブレットからアクセスした際に画面サイズを最適化する「レスポンシブ表示」に対応しているかどうかも、eラーニングシステム選定時の注目ポイントです。
通知機能でリマインドが可能
LMSには、受講者に対してeラーニングに関する通知を自動で送る機能があります。
通勤途中などに通知を受け取った場合でも、スマホでeラーニングを受けられれば、そのタイミングですぐに受講を開始することができます。
以下は、受講者に通知する内容の例です。
- 未受講の研修があります
- テストの受講期限が近付いています
- おすすめの講座が追加されました
eラーニングの受講に社用PCしか使えないと、スマホで連絡を確認しても「あとでやろう」と考えてしまい、効果的なリマインドができません。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
eラーニングをスマホで行う注意点

ではここからは、eラーニングをスマホで受講する際に押さえておきたい事項をご紹介します。主なポイントは以下の4つです。
- 実技を伴う研修が実施しにくい
- モチベーション維持が難しい
- セキュリティ対策が必要
- 学習画面が狭く操作性が下がる場合がある
以下で詳しく紹介していきます。
実技を伴う研修が実施しにくい
インターネットを活用したオンライン学習であるeラーニングには、実技を伴う研修ができないという課題があります。
しかし、スマホによるeラーニングで日々知識を付けていき、実際の作業は対面で実践するという研修スタイルをとることはできます。
インプットした内容をアウトプットする機会を設けることで、より高い学習効果が期待できます。
モチベーション維持が難しい
スマホを利用したeラーニングには、受講者のモチベーション維持が難しいという不安があります。
eラーニングにアクセスしやすい点はメリットですが、それは他のアプリにも容易にアクセスできるということでもあります。そのため、スマホでeラーニング受講中に集中が途切れると、すぐに別のことに気を取られてしまいます。スマホでのeラーニング受講者を意識して、受講者の集中が途切れないよう教材内容や視聴時間を工夫する必要があります。
セキュリティ対策が必要
セキュリティ対策も懸念点の一つです。eラーニングには、学習の記録だけでなく、企業の内部情報が複数登録されています。
企業がセキュリティ対策を施した端末を利用すれば、ハッキングなどの脅威から守られますが、個人端末を利用した場合は個人でセキュリティ対策を行わなければなりません。
eラーニングアプリは、そもそもPCでの利用が想定されておらず、スマホでの使用となります。企業はeラーニングアプリを導入する際には、個人端末のセキュリティ対策を検討しなければなりません。
eラーニングのセキュリティに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
『eラーニング導入時に知っておきたいセキュリティ対策について』
学習画面が狭く操作性が下がる場合がある
eラーニングの学びやすさに大きく関わるのが、学習画面の大きさです。
PCの画面サイズを想定してデザインされた表示が、そのままスマホサイズに縮小されただけでは、文字が小さい、ボタンをタップしにくいといった受講のストレスにつながってしまいます。
eラーニングシステムを選定する際には、無料の体験版やデモ画面においてスマホでの操作性を確認しておきましょう。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
スマホ対応eラーニングシステムを選ぶポイント

マルチデバイス対応のeラーニングシステム・LMSは、さまざまなベンダーから提供されています。
その中から自社に最適なものを選ぶには、以下のポイントに注目してみましょう。
- 教材コンテンツの有無で選ぶ
- 自社で教材が作成可能かどうかで選ぶ
- 使いやすさで選ぶ
- 学習履歴管理が可能かどうかで選ぶ
- 費用対効果で選ぶ
- 受講者数に対応できるものを選ぶ
以下にて詳しく解説していきます。
教材コンテンツの有無で選ぶ
スマホ対応eラーニングシステムを比較する際に最も重要な点は、教材コンテンツが充実しているかどうかです。自社が求めている教材コンテンツがあるかどうか、さらに、そのベンダーが研修教材開発のノウハウをどの程度持っているかが検討事項となるでしょう。
良い教材かどうかのポイントとして、インストラクショナルデザインに基づいているかという点が挙げられます。インストラクショナルデザインとは、企業が持っている問題点を明らかにし、それを解決するための最適な教育設計をすることです。
自社で教材が作成可能かどうかで選ぶ
自社に特化したオリジナル教材を作りたい場合は、教材制作が実現可能なベンダーかどうかが重要です。一例として、以下のような手順で教材コンテンツの作成ができます。
- ヒアリング
- プランニング・お見積もり
- 設計・制作
- 研修教材納品
- 学習効果測定
ヒアリングの段階で、教材作成の手順に悩む担当者の方もいるかもしれません。
その場合は、人材育成に関する経験が豊富なコンサルタントがいるベンダーを選びましょう。自社の問題点を洗い出し、より効果的なeラーニング研修の施策を提案してくれます。
eラーニング教材を購入すべきか、自社開発すべきか詳しく知りたい方は『eラーニングの教材は購入すべき?開発すべき?良い教材のポイントも』をご覧ください。それぞれのメリット・デメリットを紹介しています。
使いやすさで選ぶ
eラーニングシステムを選ぶ時は、管理者だけでなく、受講者の操作性にも重点を置きましょう。使いやすいシステム導入をすることで、eラーニングの定着が図れます。
直感的に学習コンテンツを選択できるか、分かりやすい動画配信ページになっているか、自分の学習履歴を簡単に確認することができるかなど、受講者にとって使いやすいeラーニングかどうかを選択基準とすると良いでしょう。
学習履歴管理が可能かで選ぶ
eラーニングシステムによっては、受講者がどの学習コンテンツを何秒単位で行ったかの学習履歴の記録・確認ができるものがあります。管理者は、受講者一人ひとりの学習進捗を正確に管理でき、適切なフォローアップが可能です。
受講者自身も、自分がどの学習コンテンツをどの程度勉強して、テスト結果は何点であったかをリアルタイムで確認できるため、学習のモチベーションの維持につながります。
費用対効果で選ぶ
対面研修をeラーニング研修に切り替えることで、コストを大幅に削減できます。紙の資料を使用する際の印刷費、研修会場費、講師料、運営全体を管理する人件費など、対面研修で発生していたさまざまな費用が不要となります。
それを踏まえた上で、eラーニングシステム導入による費用対効果を検討しましょう。
自社がどんな目的でスマホ対応eラーニングシステムを導入しようとしているのか、それにかけるコストはどの程度か、きちんと算出した上でベンダーを選ぶようにしましょう。
受講者数に対応できるものを選ぶ
eラーニングシステムによっては、最低受講者数が何人以上と定められているものがあります。使いたいベンダーがあっても、自社の受講者数に対応していなければ、利用できません。
ベンダーを選ぶ際には、受講者数に柔軟に対応できるかどうかを確認しましょう。少人数から始めて、組織単位、会社単位、グループ会社全体へと受講者が増えた場合にも、制限なく利用できるサービスが良いと言えます。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
スマホ対応のeラーニングなら「etudes」
マルチデバイスに対応をしているeラーニングシステムでおすすめなのが、etudes(エチュード)です。人材育成会社として多くの企業をサポートした実績があるアルー株式会社が、そのノウハウを結集して開発したLMS一体型のeラーニングシステムです。
ここからは、etudesの強みについてご紹介します。
- PC・スマホ・タブレットに対応
- 操作しやすく編集しやすい画面デザイン
- 利用シーンに合わせたコースをご用意
- 自社オリジナルの教材作成もサポート可能
以上4つについて、詳しく見ていきましょう。
1.PC・スマホ・タブレットに対応
etudesは、スマホ、PC、タブレット等マルチデバイス対応のLMS一体型eラーニングシステムです。
画面表示にはレスポンシブデザインを採用しています。
そのため、どの端末でeラーニングを使っても、表示される画面の内容は変わりません。端末毎に使いやすいデザインに変更されますが、端末によって表示される内容が異なることはありません。
2.操作しやすく編集しやすい画面デザイン
etudesは、学習コースがパネル型で表示されるなど、直感的で分かりやすい画面デザインを採用しています。たとえば、
- コースが「必須」であるか「任意」であるか
- どのくらいの時間で完了できる学習コースであるか
- あなたがどの程度そのコースを完了しているか
これらが一目でわかるデザインです。
そのほかにも、目次ページ、動画再生ページなど、受講者が迷わないわかりやすいUI/UXを追及しています。
また、eラーニング研修の管理者にとっても操作・編集しやすいシステムとなっています。システム構築のノウハウがなくても、自社の学習プラットフォームが自由に作れます。
eラーニングは、ITリテラシーのある人ばかりが利用する訳ではありません。ITリテラシーの有無にかかわらず様々な人が、直感的にわかりやすく操作できるLMSがetudesです。
etudesの機能について詳しくは『機能・特長』をご覧ください。
3.利用シーンに合わせたコースをご用意
etudesなら、アルー株式会社による人材育成の知見を活かした豊富なeラーニング教材が配信できます。
「新入社員/内定者向け」、「若手社員向け」、「中堅社員向け」、「チームリーダー向け」、「管理職セットスキル編」など幅広く、利用シーンに合わせたコースを選択できます。
アルー株式会社のeラーニング教材のセットプランは、テーマ別で選択することも可能です。社員の考え方や価値観についての研修をeラーニングで実施する場合、選択できるeラーニングコースは22種類あります。マネジメント・部下育成についてのeラーニングコースは23種類、ビジネススキルは45種類、そのほかにも複数のテーマがあります。
このように豊富なeラーニングコースの中から、好きなコースを自由にカスタマイズできることがetudesの魅力です。
etudesの教材について詳しくは『eラーニング教材一覧』をご覧ください。
4.自社オリジナルの教材作成もサポート可能
アルー株式会社では、自社オリジナルの教材作成のサポートも行っています。経験豊富なコンサルタントが、自社の問題点の把握からeラーニングで解決したい課題の抽出、解決策の提示まで、一環してサポートを行います。
既にある研修教材のeラーニング化も、以下のような方法で行えます。
- 映像(動画)撮影
- アニメーション制作
- 講義撮影・ライブ配信
- ナレーション収録
- PPTスライド制作
- 紙を使用した補助教材の作成
- 確認テスト・アンケート導入
- 模擬試験導入
- 研修教材の多言語化
- Adobe Flashでつくられた古いSCORM教材のリメイク
自社ならではのノウハウのeラーニング化も可能です。
etudesのオリジナル教材作成について詳しくは『オリジナル教材を作成』をご覧ください。
etudesの製品紹介を詳しく知りたい方は『製品紹介資料』をご覧ください。etudesの特徴やデモ画面、費用についてご紹介しています。
▼ eラーニングや教育プラットフォームにお困りではございませんか?
初期費用0円・有効IDのみご請求で、繰り返し実施する研修の効率化ができる
⇒ サービス資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
eラーニングをスマホやタブレットから受講するには、
- アプリを導入する
- マルチデバイス対応のeラーニングシステムを利用する
といった方法があります。
既存のアプリであれば導入が簡単というメリットがありますが、自社の研修に最適化させたアプリを開発するにはコストも期間もかかります。
そのため、スマホからも受講できるeラーニングシステムを利用することがおすすめです。
eラーニングシステムには、対応するデバイス以外にも選定のポイントがあるので、この記事を参考に自社に最適なeラーニングシステムを探してみましょう。
マルチデバイスに対応しており、人材育成会社ならではの手厚いサポートも受けられるeラーニングシステムが「etudes」です。
etudesの実際の画面表示をみてみたい、デモ版でトライアルをしてみたいという方は、ぜひお気軽にアルー株式会社へお問い合わせください。