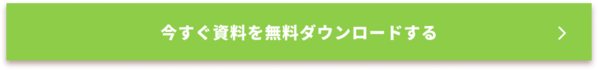コンプライアンスとは?ガバナンスとの違いや事例をわかりやすくご紹介
コンプライアンスは企業が持続的に成長する上で必要不可欠であり、社会的信用を保つためには、社員一人ひとりがコンプライアンスを遵守することが欠かせません。しかし、最近では従業員のモラルの低下や、知識不足によるコンプライアンス違反が表面化するケースが増えています。
本記事では社員のコンプライアンス遵守のための教育のポイントと、eラーニングシステムを活用した効率的なコンプライアンス教育の実施について解説します。eラーニングシステム(LMS)は全社員への一斉教育をシステムで効率化できるだけでなく、知識確認のためのテストの実施や結果、受講履歴がすべてデータで管理できるためコンプライアンス研修に最適です。
実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方は「導入事例:株式会社メガネトップ / 株式会社オカムラ / 他」で詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
- 1.コンプライアンスとは
- 1.1.コーポレートガバナンスとの違い
- 1.2.内部統制との違い
- 2.コンプライアンスを構成する3つの要素
- 3.コンプライアンスはなぜ重要なのか
- 4.コンプライアンスリスクとは
- 5.実際にコンプライアンス違反となった事例
- 5.1.情報漏洩
- 5.2.ハラスメント
- 5.3.不法な時間外労働
- 5.4.SNSへの不適切投稿
- 5.5.著作権侵害
- 6.コンプライアンス違反が発生してしまう原因
- 7.社員にコンプライアンスを教える方法
- 7.1.1.規則・マニュアル作成
- 7.2.2.集合研修
- 7.3.3.eラーニング
- 8.コンプライアンス研修にeラーニングが最適な理由
- 8.1.忙しい社員でも都合の良い時に受講できる
- 8.2.繰り返し実施できる
- 8.3.研修を行った履歴をデータで残せる
- 9.コンプライアンス研修に使えるeラーニング教材
- 9.1.コンプライアンスとハラスメント講座
- 9.2.個人情報保護法講座
- 10.全社員にコンプライアンス教育を徹底するなら「etudes」
- 11.まとめ
定額制受け放題eラーニングetudes Plusが分かる3点セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
コンプライアンスとは
コンプライアンスとは、企業や組織が法令や規則、社会的なルールに従い、適切に行動することを指します。これには、企業が法律を遵守するだけでなく、倫理的な基準や業界規制、さらには従業員が行動する際に守るべき道徳的な指針も含まれます。
コンプライアンスは企業活動における信頼性を高め、リスクを軽減するために欠かせないものです。企業がコンプライアンスを徹底することで、企業価値が向上し、社会的責任を果たすことができます。
コーポレートガバナンスとの違い
コーポレートガバナンスは企業経営の仕組みや管理体制を指し、企業の戦略的方向性や資源配分において、株主をはじめとするステークホルダーの利益を守ることを目的としています。これに対して、コンプライアンスは法令や規則を遵守することに焦点を当てています。
両者は異なる側面に重点を置いていますが、ガバナンスがしっかりしている企業はコンプライアンスも自然と徹底される傾向があります。
内部統制との違い
内部統制は、企業内部で業務が適切に行われるようにするためのシステムや手続きのことです。これには不正の防止や業務の効率化、財務報告の信頼性を確保するための管理体制が含まれます。コンプライアンスとは、法的規制を遵守することに重点を置いていますが、内部統制は業務の内部的な管理と規制に特化しています。
つまり、コンプライアンスが外部のルール遵守に関するものであるのに対し、内部統制は企業内のプロセスや管理体制に関わるものです。
コンプライアンスを構成する3つの要素
現在のコンプライアンスを構成する要素は、以下の3つです。
- 社会倫理
- 企業規則
- 法令
それぞれ、詳しい内容を見ていきましょう。
社会倫理
コンプライアンスにおける社会倫理とは、企業が社会から求められる倫理的な規範のことを指します。法令に直接定められているというわけではありませんが、企業として取引先や顧客から信用を獲得するためにはなくてはならない要素です。近年は、「公序良俗を守る」といった言い方もされ、企業の社会倫理に対する世間の目は特に厳しくなっています。
具体的には、情報漏洩や顧客のプライバシーに関する対策、ハラスメント防止などが社会倫理の一例です。企業は常に最新の社会情勢を注視して、社会倫理を遵守することが求められます。
企業規則
コンプライアンスにおける企業規則とは、それぞれの企業が内部で定める社内ルールやマニュアルのことです。社員が企業内で働くにあたって守らなければならない規則や取り決めのことを指します。
企業規則は一定の条件を満たす企業の場合、必ず定めることが法律で義務付けられています。具体的には、常時10名以上の従業員を雇っている雇用主が、労働基準法に基づいた就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。社会倫理と合わせて、コンプライアンスを構成する重要な要素です。
法令
コンプライアンスを構成する3つの要素の中でも最も基本的で、かつ重要度が高いのが法令です。法令とは、国会が国民に対して定めた法律や、行政機関が制定した政令、省令などの総称です。地方公共団体が法律とは別に条例や規則を定めていることもあり、それらも法令に含まれることがあります。
意図的に法令に違反しなくても、知識や自覚がなかったために法令に反することがあれば、企業にとって大きな失態となります。法律は時代に応じて改正されることもあるため、企業は常に関連する法令に注意を払っておく必要があります。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
コンプライアンスはなぜ重要なのか
直接的な売上に結びつかないコンプライアンスにコストや時間を割くことは、利益を追求する企業にとってマイナスとなるのではないかと思われるかもしれません。しかし、企業が持続的に事業を展開し成長していくためには、コンプライアンスを徹底することが最低限の条件と言えます。最近では、デジタル化の進展やジェンダー平等に対する意識の高まりなども相まって、企業に求められるコンプライアンスがますます多様化され、注目される時代になっています。
コンプライアンスが企業にとって重要な背景を見ていきましょう。
コンプライアンスが必要とされる背景
企業に対し、より厳格にコンプライアンスが求められる背景として企業のコンプライアンス意識の不足や低下によって不正が増加したということがあげられます。
1990年代のバブル崩壊で不況に陥った日本において、企業は目先の利益を重要視し、粉飾決済や食品の産地偽装といった不祥事や不正に関する報道が相次ぐようになっていきました。さらに2000年代半ばを過ぎると、情報漏洩やサイバーセキュリティといった新しい課題も増え、コンプライアンスを徹底せず、結果として問題が表面化した企業がマスコミに取り沙汰されることも増えました。このように利益追求が優先され、企業倫理が低下した企業が増加した結果、コンプライアンスの重視が求められるようになりました。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
コンプライアンスリスクとは
コンプライアンスリスクとは、法令や規範、社会倫理などに違反することで発生する様々なリスクのことを指します。ひとたびコンプライアンス違反が起こってしまうと、企業の抱える問題が一気に表面化し、企業の社会的信用の低下を引き起こします。
また、企業の犯したコンプライアンス違反がインターネット上で瞬時に拡散されてしまうことも珍しくなくなりました。
企業が持続的に成長していくためにも、コンプライアンスリスクの引き金となる以下のようなコンプライアンス違反を理解しておきましょう。
- 法規範違反
- 社内規範違反
- 倫理規範違反
一つずつ、詳しく解説していきます。
法規範違反
コンプライアンス違反の中でも最も代表的なものとして、法規範違反があげられます。例えば消費者と直接契約を行う際には、消費者と事業者が持っている情報や交渉力の不平等さを解消するために、消費者契約法を遵守することが求められます。
さらに、公正で自由な競争を促進するために定められた独占禁止法や下請法、消費者を欺くような表示を禁止する景品表示法など、企業が守らなければならない法律は数多くあります。企業は常に法令を遵守し、法改正等にも迅速に対応することが求められます。
社内規範違反
企業は、従業員が仕事を行う上で守るべき規則である社内規範を定める必要があります。しかし、社内で定めた規範が形だけのものになっており、社員に十分その内容が行き渡っていないことも少なくありません。社内規範が遵守されていないことで、本来は起こるはずのなかったコンプライアンスリスクを招いてしまいます。
特に、情報漏洩については注意が必要です。情報漏洩は企業の社会的信用低下に直結してしまいます。コンプライアンス違反によるトラブルを引き起こさないためにも、社内規範を適切に定め、ルールが徹底される環境を作ることが必要です。
倫理規範違反
倫理規範に対する違反も、コンプライアンスリスクとなりえます。一言で倫理といっても様々な種類がありますが、最近特に注目を浴びているのがハラスメントです。
性的な言動で嫌がらせを行うセクシャルハラスメントや、良識の欠如によるモラルハラスメントなどがハラスメントの代表格ですが、最近ではアルコールハラスメントやパワーハラスメントなども注目されるようになってきました。社員がハラスメントを引き起こさないよう、倫理規範の遵守を徹底する必要があります。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
実際にコンプライアンス違反となった事例

コンプライアンスを徹底することは今や企業にとって必要不可欠になっていますが、どのような行いがコンプライアンス違反になるのか、具体的な事例やイメージが湧かないという方も少なくないのではないでしょうか。また、社内規定が守られ、コンプライアンス違反が起こったことのない企業では「法令や社会的ルールを守る、コンプライアンス重視は当然」「自社には特に関係ないのではないか」といった考えの社員が多い場合もあるでしょう。
しかし実際にはコンプライアンス違反は、身近な実務の場面で発生してしまう可能性があるものです。以下にて、企業で起こりやすいコンプライアンス違反の実例をご紹介します。
- 情報漏洩
- ハラスメント
- 不法な時間外労働
- SNSへの不適切投稿
- 著作権侵害
以下にて、詳しい内容を見ていきましょう。
情報漏洩
企業で発生する重大なコンプライアンス違反の例として、情報漏洩があげられます。具体的には不正アクセスによる顧客情報の漏洩や、クレジットカード情報の漏洩などがあげられます。実際に、大手食品企業や官公庁において、不正アクセスやメールの誤送信により顧客情報が流出した事例があります。
情報漏洩が起こる原因として、まずシステムの脆弱性をついた第三者からの攻撃があります。さらには、ウィルスやスパイウェアの感染による情報漏洩もコンプライアンス違反を引き起こしてしまう要因となります。情報漏洩の社内対策を徹底するには、社内のセキュリティを万全にするだけでなく、不用意に不審なメールを開かないことを社員に周知したり、機密情報が入ったデバイスを外部へ持ち出さないことなど、社員の行動規範についても指針を示し、遵守されているかを確認することが必要です。
ハラスメント
ハラスメントとは、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど、職場において相手の意に反する行為や行動によって相手を不快にさせたり、結果として相手の尊厳を傷つけてしまう行為を指します。ハラスメントは、行為者本人に意図がない場合でも、受け取る側が不快な感情を抱けば成立します。そのため、指導やアドバイスとハラスメントの線引きや定義を各社員に理解してもらうことが重要です。
昨今では、ハラスメントは多様化しています。企業内でハラスメントが起これば社員が心身に不調をきたすだけでなく、職場の心理的安全性が低下し、働きやすい環境が守られなくなります。また、実際にハラスメントが起こった際に、当事者がハラスメントだと自覚していないケースも多いです。例として、管理職が部下の成長のために必要だと思って行った指導であっても、結果的に受け手側の社員が不快になったり、尊厳を傷つけられたと感じる場合には、パワーハラスメントとなります。ハラスメントを防ぐためには、従業員のパワハラに対する知識を深めることが有効です。
不法な時間外労働
不適切な時間外労働も、コンプライアンス違反の一例です。サービス残業が当たり前になってしまっていたり、法令で定められた時間以上の残業が発生したりすると、コンプライアンス違反となる場合があります。さらにこれらが長期化してしまうと、従業員の退職や過労死といった重大な事態を招いてしまいます。
不適切な時間外労働については、通常の勤務時間では終わらない業務量や、高い目標達成が求められるなど、明確に残業を指示されていなくても結果として時間外労働をせざるを得ない状況があります。こうした場合は黙認せず、適切な人員配置や業務量の調整など、従業員が通常の勤務時間や定められた時間外労働の時間内で業務遂行できるように、環境改善を実施することが必要でしょう。
SNSへの不適切投稿
ソーシャルメディアの普及とともに増加しているコンプライアンス違反の事例として、SNSでの不適切な情報公開があげられます。例えば、厨房で勤務する社員が、食品衛生法に反する行為を動画で撮影し、その動画をソーシャルメディアを使ってインターネット上で公開した例があげられます。また、安全性が守られるべき職場で、重機に人を乗せた動画がSNSに投稿された事例もあり、いずれのケースも個人が簡単に情報発信ができるソーシャルメディアを利用する中で起こったコンプライアンス違反です。
SNSを通じてインターネット上に、企業に関する情報を社員個人が公開してしまった場合、限定公開の画像や動画であっても、簡単に転載できてしまいます。勤務時間における規則や行動指針、各社員のITリテラシーを高めることが必要になるでしょう。
著作権侵害
企業による著作権侵害も、コンプライアンス違反の一例です。インターネットの普及から、著作権侵害にあたる行為も多様化しています。著作権侵害は、ハラスメントと同様に「違反する意図がなかった」場合でも、結果として重大なコンプライアンス違反となることがあります。
個々の社員が判断して行動することのないように社内の法務確認を徹底するだけでなく、どのような事案において確認が必要かなど、各社員の著作権に関する知識習得が必要になるでしょう。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
コンプライアンス違反が発生してしまう原因
コンプライアンス違反が発生する主な原因には、企業文化や業務環境、管理体制の問題があります。これらの原因は、従業員の行動に大きく影響を与えるため、問題を未然に防ぐためには根本的な原因を特定し、改善策を講じることが重要です。
規則やルールを守らない場合、その背景には企業内での教育やコミュニケーション不足、または過剰な業務負担が影響していることが考えられます。
コンプライアンス違反が発生してしまうよくある原因を、次からみていきましょう。
社員のコンプライアンス知識が不足している
社員がコンプライアンスに関する基本的な知識を欠いていると、意図せず規則違反を引き起こす可能性があります。
例えば、法令や社内規則に対する理解が浅い場合、業務を進める中で誤った判断をしてしまうことがあります。そのため、定期的なコンプライアンス教育や研修を実施することが、社員全員の意識を高め、違反を防ぐために重要です。
業務におけるノルマが厳しくプレッシャーが大きい
厳しい業績ノルマやプレッシャーが従業員にかかると、目の前の目標達成を優先し、法令や倫理規範を軽視することがあります。特に、売上や成果を急ぐあまり、無理な手段に走ってしまうことがコンプライアンス違反を引き起こす原因となります。
これを防ぐためには、業績目標とコンプライアンスの徹底をバランスよく設定し、プレッシャーが過度にならないような業務環境を整えることが求められます。
コンプライアンス違反を未然に防ぐシステムが無い
企業がコンプライアンス違反を防ぐためのシステムや仕組みを整備していないと、問題が発生してから対処することになり、違反が広がる可能性が高まります。
効果的な監視体制や報告システムが整っていない場合、社員が違反行為に気づかず、そのまま進行してしまうことがあります。したがって、予防的な措置として、リスク管理体制や内部監査を強化し、定期的にチェックを行うことが重要です。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
社員にコンプライアンスを教える方法

法令や倫理観に対する社員の理解不足は、コンプライアンス違反が起こる大きな要因の一つです。コンプライアンス違反が起こらないような組織体制を構築するためには、社員にコンプライアンスについての知識をしっかりと教育する必要があります。
コンプライアンスを社員に浸透させるための方法はいくつかありますが、中でも規則やマニュアルの作成、研修実施による教育などが主な手法です。社員にコンプライアンスを教える方法について、3つご紹介します。
1.規則・マニュアル作成
まず、コンプライアンスを重視した行動規範となる規則や、その規則を実務に応用する際の具体的なマニュアルの作成があげられます。例えば顧客情報には限られた担当者しかアクセスできないような規則を設定したり、機密情報を管理するシステムにアクセスする際のマニュアルを作成したりすることで、情報漏洩によるコンプライアンス違反を防ぐことが可能です。
しかし、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなど、社員の行動に関するハラスメントの場合は規則やマニュアル作成だけでは教育が不十分な場合もあります。そうした内容でもコンプライアンス違反を防ぐために、他の手法と組み合わせながら教育施策を実施するのが効果的です。
2.集合研修
社員にコンプライアンスに関する知識を身につけてもらう手法として、集合研修の実施があげられます。集合研修の実施は、法令や規則、ハラスメントに関する知識を必要な社員に一度に伝えることが可能です。最近では、集合研修の実施を外部委託するケースも増えており、研修を外部委託することで、自社で研修プログラムを開発する手間や費用を抑えることができることに加え、専門ベンダーに委託することで研修の質を高めることもできます。
外部委託による集合研修の実施はコンプライアンスについての知識を身につけてもらうためには有効な手段のひとつですが、集合研修の場合は、各社員の時間調整が難しく欠席せざるをえない社員が出る可能性があります。コンプライアンスに関する研修は全社員に必須になるため、このような事態は避けなくてはいけません。
3.eラーニング
集合研修のデメリットをカバーしつつ、限られた時間でも効果的に研修を行える方法が、eラーニングです。先述したように、コンプライアンス違反が起こる要因は社員のコンプライアンスに関する知識不足があります。社会が定めた規則や求められている倫理規範などについての認識が不足していることで、様々なコンプライアンス違反を招いてしまいます。
eラーニングを用いることで、社員はコンプライアンスについての知識を効率的に学習することができます。オンラインで学習するため、各社員は自分のスケジュールに合わせて効率的にコンプライアンスに関する知識を身につけることができます。
また、eラーニングを導入した場合、eラーニングと集合研修など、さまざまな教育手法を組み合わせたブレンディッドラーニングも実施することができます。事前にeラーニングで知識習得をしてから、集合研修で演習を行えば、限られた研修時間でも、より教育効果が高まります。集合研修と比較すると実施のコストも低く、わからない箇所は繰り返し学習できるため、知識の定着度が高いこともeラーニングの特徴です。
コンプライアンス研修にeラーニングが最適な理由
コンプライアンス研修を行うには、eラーニングによる実施がおすすめです。その理由として以下の3つが挙げられます。
- 忙しい社員でも都合の良い時に受講できる
- 繰り返し実施できる
- 研修を行った履歴をデータで残せる
忙しい社員でも都合の良い時に受講できる
eラーニングは、社員が自分の都合の良い時間に受講できるため、忙しい業務の合間でも学習が可能です。通常の研修では、社員全員が同じ時間に集まる必要がありますが、eラーニングでは時間帯を選ばず、社員が自分のペースで学ぶことができるため、業務に支障をきたすことなくコンプライアンス研修を実施できます。これにより、社員の参加率も向上し、研修の効果が最大化されます。
繰り返し実施できる
eラーニングは、必要に応じて研修内容を繰り返し受講できる点が大きな利点です。コンプライアンスに関する情報は一度学んだだけでは十分に理解できないことも多く、定期的に復習することが重要です。社員が自分のタイミングで何度でも確認できるため、理解度が深まり、違反行為を未然に防ぐための意識づけが行いやすくなります。
研修を行った履歴をデータで残せる
eラーニングでは、社員が研修を受講した履歴や進捗状況をデータとして記録できます。このデータを活用することで、どの社員が研修を完了したか、どの部分でつまずいているかを把握することができます。
企業側は、研修の効果をモニタリングできるだけでなく、コンプライアンス研修の実施状況を証明するために必要な情報を正確に管理でき、後の監査や報告にも対応しやすくなります。
コンプライアンス研修に使えるeラーニング教材
コンプライアンス研修をeラーニングで実施する際に活用できる教材として、eラーニングシステム「etudes」の教材をご紹介します。
- コンプライアンスとハラスメント講座
- 個人情報保護法講座
コンプライアンスとハラスメント講座
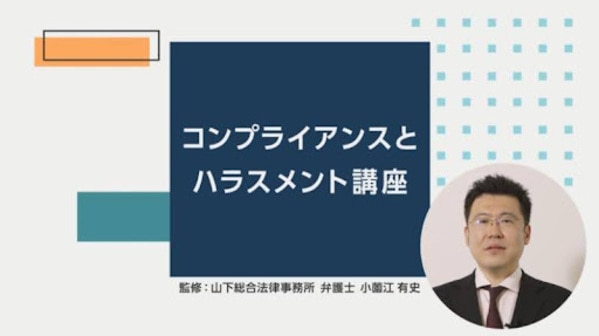
コンプライアンス研修において、ハラスメントに関する講座は必ず取り入れたい内容です。
etudesの「コンプライアンスとハラスメント講座」なら、社員のコンプライアンス意識を向上させる基本情報や、社会問題となっている企業内でのハラスメントに関する正しい知識を、eラーニングで学ぶことができます。
内容は、以下の8セクションに分かれています。
- コンプライアンスとは?
- ハラスメントとは?
- パワーハラスメント
- セクシャルハラスメント
- マタニティハラスメント
- その他のハラスメント
- 企業に求められるハラスメント対策
- ハラスメントが生じた場合の対処
コンプライアンスの観点から、社内のハラスメント予防を目的としたカリキュラムとなっています。企業法務分野での豊富な経験を有する弁護士監修であるため、法令に関する正しい理解を得ることができます。
個人情報保護法講座
コンプライアンス研修に使えるeラーニング教材として、「個人情報保護法講座」もあります。
企業が遵守すべき法令の一つである、個人情報保護法について詳しく学ぶ内容です。個人情報漏洩による影響の大きさや、漏洩させない対策、漏洩してしまった場合の対応方法などを、40分間で受講するカリキュラムです。
あらゆる業務のオンライン化が進む昨今、個人情報に関するトラブルは多発しています。このカリキュラムを通じて、全社員が個人情報保護法について正しく理解することで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
全社員にコンプライアンス教育を徹底するなら「etudes」
コンプライアンスに関する正しい知識について社員教育を実施することは、企業において必須となります。全社員を対象に効率的にコンプライアンスに関する知識を身につけてもらうためには、「etudes」がおすすめです。
etudesは学習管理システムとしての機能が搭載されたeラーニングシステムです。eラーニングの配信だけではなく、集合研修の出欠管理や、オンライン研修のURL配信といった人材育成に役立つ機能が揃っています。
etudesを用いることで、全社員に対する実施が必要なコンプライアンス研修であっても、研修管理業務が煩雑にならず効率的に実施できます。
etudesなら自社資料をアップロードしてコースを簡単に作れる
etudesは、PPTやPDFといった自社にある資料をアップロードし、簡単にコースを作成することができます。アルー株式会社の教材で学ぶだけでなく、自社社員のコンプライアンスの徹底に必要な、具体的な過去事例や社内の取り決め、必要な知識や社内フローについてなどは、コースを内製することができます。
コースを作成したあとに、任意で「必須コース」の設定ができるため、全社員を対象にコースを割り当てたうえで、受講必須とすることでコンプライアンス教育を徹底することができます。
知識確認のためのテスト実施やリマインドメールも可能
コンプライアンス教育は実際の社員のコンプライアンス徹底のために実施するため、必要な知識を社員がしっかりと把握できているのか理解度や定着度を測ることも重要です。etudesでは、内製でマルバツ式や選択問題、自由記述などのテスト問題を作成できるだけでなく、解答回数や解答時間、合格点の設定なども自在に設定できます。実施したテストの結果はシステムにデータとして蓄積されるため、過去の取り組みをすべて管理することが可能です。
また、必須研修の場合は受講率100%にするための運営工数が膨大になりますが、etudesを活用すれば、シークバーによる動画の飛ばし見の有無などが正確に受講率に反映されるだけでなく、未受講者や受講率が基準より低い社員に受講を促すリマインドメールを送ることも可能です。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
コンプライアンスについて、企業にとっての必要性やコンプライアンス違反の実例、さらにはコンプライアンスを社員に教える方法などについて解説しました。昨今では企業に対する世間の目がより厳しくなっており、コンプライアンス違反が大きな社会問題となった例もあります。また、ソーシャルメディアなどの普及で過去にない事例のコンプライアンス違反も増えてきました。eラーニングを用いて効率的に全社員に適切なコンプライアンス教育を実施し、企業の社会的信用を低下させるコンプライアンス違反を未然に防ぎましょう。