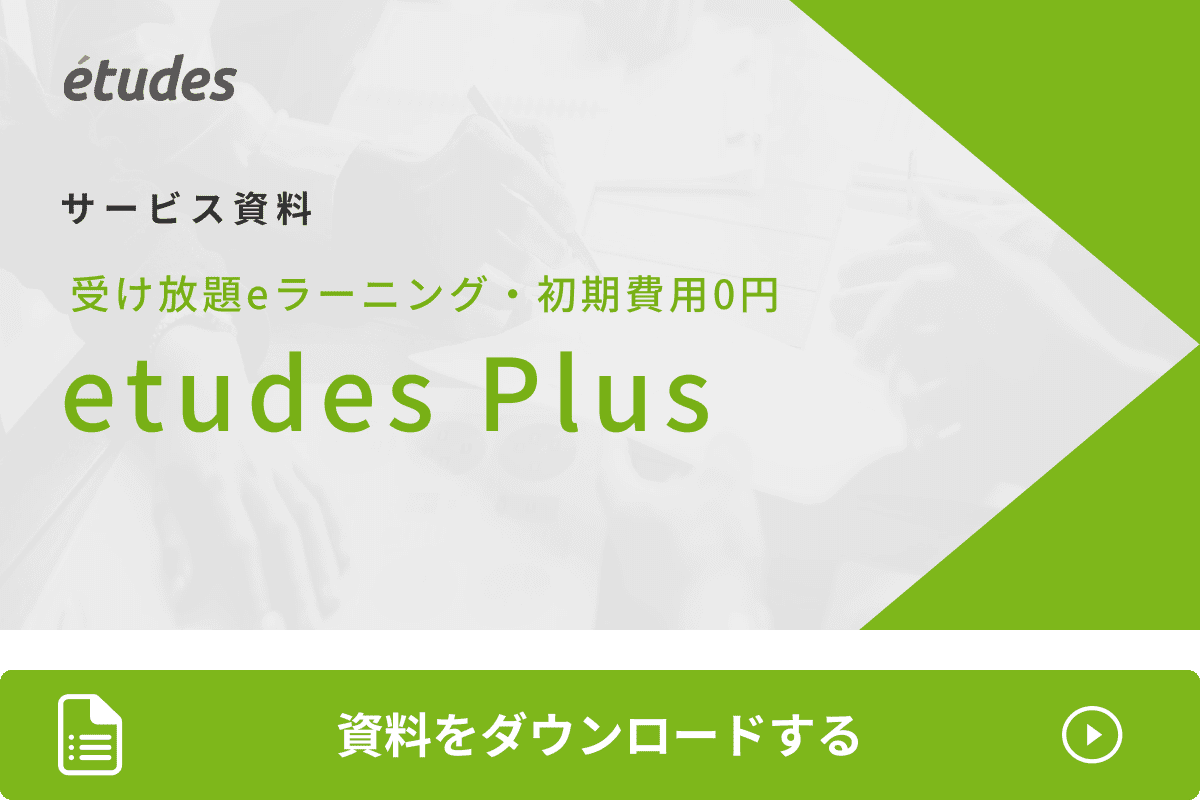リスキリングとは?DX化の成功につながるポイントをご紹介
国内の企業の多くが、DXを実現させる施策として「リスキリング」に取り組んでいます。リスキリングは、多様化する働き方に適応しつつ、IT・デジタル人材不足を解決し、企業の未来を支える重要な施策です。今や一部の業種だけではなく、全ての企業がリスキリングを始めるべき状況となっています。
この記事では、リスキリングの基本から、リスキリングを行うメリット、効果的に実施する方法まで詳しく解説します。
さらに詳しく知りたい方はリスキリングを効果的に進めるための社内教育のポイントをご覧ください。
実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
- 1.リスキリングとは
- 1.1.リカレントとの違い
- 1.2.アンラーニングとの違い
- 1.3.生涯学習との違い
- 2.リスキリングの対象者
- 3.日本のリスキリングへの取り組み状況
- 4.リスキリングが注目されている理由
- 4.1.働き方の変化
- 4.2.DXの推進
- 4.3.国内外でのリスキリングに関する宣言
- 4.4.経済産業省がリスキリング推進を開始
- 5.社内でリスキリングに取り組むメリット
- 5.1.業務の効率化
- 5.2.新たなアイデア・イノベーションの創出
- 5.3.採用にかかるコストの低減
- 6.リスキリング導入の3ステップ
- 7.リスキリングの実施方法
- 8.実際にリスキリングを導入した企業の事例
- 8.1.富士通株式会社
- 8.2.旭化成株式会社
- 8.3.住友生命保険相互会社
- 9.リスキリングを実施する上での注意点
- 10.リスキリングの実施なら「etudes」がおすすめ
- 11.まとめ
定額制受け放題eラーニングetudes Plusが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
リスキリングとは
リスキリングとは、社会の変化に合わせて社員に新たなビジネススキルを獲得させることです。
働き方の変化やIT技術の発展に伴って、今のスキルのままでは失業してしまう可能性がある社員に対して、新たなスキルを教育することで、職を失う不安とIT人材不足を同時に解決できる施策です。
リスキリングは、国内企業の多くが取り組む「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の実現のため、広く実施されるようになりました。
リスキリングには、「リカレント」「アンラーニング」「生涯学習」といった、似た用語がいくつかあります。
それぞれの用語との違いについて詳しく解説します。
リカレントとの違い
リスキリングと似た用語として「リカレント」があります。
どちらも学び直しといった意味で使われますが、リカレントの場合は社会人が大学などの教育機関で学ぶことを指します。
リスキリングは、企業が用意した学習プラットフォームや研修によって学習が行われるため、より「ビジネススキルを獲得する」意味合いが強いです。
リスキリングとリカレントの違いに関して詳しくは「リスキリングとリカレント教育の違いは?効果的な実施方法も」をご覧ください。
アンラーニングとの違い
リカレントと同じように、リスキリングと似た意味合いで用いられる言葉として「アンラーニング」があります。
アンラーニングとは、これまで学んできた古い知識を捨て、新しい知識を身につけることを指します。
アンラーニングと異なり、リスキリングはこれまでの知識やノウハウを活かして新しいスキルを獲得することが目的です。
生涯学習との違い
社会人として学ぶ姿勢がリスキリングと「生涯学習」で似ているため、混乱を招きがちです。
生涯学習とは、より豊かな人生を送るために学習を続けることを指します。
リスキリングには「仕事やキャリアに活かせるスキルを身につける」という目的がある点が大きな違いです。
社会人になってから新たなスキルを学ぶという点では同じですが、リスキリングと生涯学習ではそもそもの目的が異なります。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
リスキリングの対象者
企業が行うリスキリングの対象となるのは、その企業で働く全ての従業員です。特に、IT技術の進化によって機械に置き換わる可能性がある業務に従事している従業員に対して、積極的に実施されています。
例えば、更なる効率化のため工場でのライン作業にロボットアームが導入されたとします。これまでライン業務にあたっていた従業員が失業してしまわないよう、ロボットアームの操作や制御に関するIT技術を学ばせるのも、リスキリング施策の一つです。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
日本のリスキリングへの取り組み状況
リスキリングは、国外の有名企業などが実際に取り組み、成果をあげてきました。
日本もそれに続いて、多くの企業がリスキリングを始めています。
2022年10月には、当時の岸田首相による所信表明演説において「5年間で1兆円を投じてリスキリング支援を行う」という発表があり、大きな話題を呼びました。
日本では、国をあげて「そもそも学ぶ機会が無い」という状況を変えようとしています。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
リスキリングが注目されている理由
冒頭で少し触れたリスキリングが注目されている背景について、さらに詳しく掘り下げていきましょう。
リスキリングが多くの企業で導入されている理由には、以下の4つが挙げられます。
- 働き方の変化
- DXの推進
- 国内外でのリスキリングに関する宣言
- 経済産業省がリスキリング推進を開始
一つずつ見ていきましょう。
働き方の変化
まず初めに挙げられる理由が、働き方の変化です。2020年以降、国内で急速にリモートワークと業務のオンライン化が進みました。
この流れは一時的なものではなく、今後も同様の働き方が続くでしょう。そのため、全社員を対象にデジタルリテラシーなどの新たなスキルを身につけてもらう必要があります。
また、ITとAI(人工知能)の発展により、業務の進め方そのものが大幅に変化している点も、あらゆる業種でリスキリングが求められている要因の一つです。
業務を自動化するツールの開発は、ITエンジニアだけの領域ではなく、事務職や経理職の業務内容にも関わります。そのため、多くの企業がリスキリングによって社員のITリテラシーの底上げを図っています。
DXの推進
先述の通り、DXの推進はリスキリングの実施に大きな影響を与えています。DX化の下準備として社内の業務をデジタル化していくにあたり、一部のIT人材だけに業務が集中してしまっては効率的ではありません。デジタル化の推進において、対応が属人化しボトルネックとなる可能性があります。
そこで行われるのが、リスキリングです。DXを実現するには、まず自社でIT人材の育成が重要という考え方です。
国内外でのリスキリングに関する宣言
リスキリングは日本国内だけの課題ではありません。世界的に取り組むべき施策として、国内外でリスキリングに関する宣言が掲げられています。
2020年に開催された世界経済会議では。「2030年までに地球人口のうち10億人をリスキリングする」という方針が発表されました。
また、国内では2020年11月に経団連が発表した「新成長戦略」のなかで、リスキリングの必要性に触れています。
参考記事:
一般社団法人日本経済団体連合会「新成長戦略」
Towards a Reskilling Revolution Industry-Led Action for the Future of Work
経済産業省がリスキリング推進を開始
日本において、社外学習や自己研鑽を行っていない個人の割合は、46.3%と半数を占めます。この現状は諸外国と比較して最も低く、さらに低下傾向にあります。
この事態を改善すべく、経済産業省は2023年3月から「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の公募を開始しました。
企業から与えられた教育を受けるだけではなく、在職者が自らのキャリアについて相談し、リスキリング講座を受講、就業支援までをトータルでサポートする事業です。
多くの企業でリスキリング推進の課題となっている「キャリアの相談を受けられる人材がいない」「リスキリング講座の提供が難しい」といったハードルを下げる取り組みとなっています。
出典:
経済産業省_令和4年度補正予算「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の公募について
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
社内でリスキリングに取り組むメリット
リスキリングは、社員に学習の場を与え長期的に学習管理をする必要があります。決して簡単な施策ではありませんが、リスキリングに取り組むべきメリットは多くあります。以下に3つのメリットをご紹介します。
- 業務の効率化
- 新たなアイデア・イノベーションの創出
- 採用にかかるコストの低減
一つずつ見ていきましょう。
業務の効率化
リスキリングによって多くの社員が新たなスキルを身に着けることで、今まで一部の人材に依存していた作業や、アナログで非効率的だった作業を、効率よく進めることができるようになります。
リスキリングのために学習をする時間を割いてでも、その後の効率化の方が企業として重要と考えられています。また、1人当たりの生産性が上がることにより、企業全体の売上を向上させることができます。
新たなアイデア・イノベーションの創出
リスキリングを行うことは、企業としての新たなアイデアやイノベーションの創出につながります。
社員にとって新しく学ぶことが無い、つまりインプットが無い状態のままでは、これまでと代わり映えしないアイデアしか出て来ないでしょう。
リスキリングにより、新しい知識やスキルが身につくと、仕事の幅が広がるだけでなく、新たな発想というアウトプットもできるようになります。
常に新しいことにチャレンジできる、時代に取り残されない企業となるにはリスキリングを実施すべきでしょう。
採用にかかるコストの低減
昨今は、特にIT関連の人材不足が深刻化しています。デジタルスキルのある人材を新規採用するには、求人広告を出したり人材派遣会社に依頼したりするコストがかかります。求める人材を採用しても、業務が集中しすぎるなどの理由ですぐに離職されては、採用コストが無駄になってしまいます。
新たに人材を雇用するよりも自社の社員に対してリスキリングを実施する方が、コストがかからず人材の定着も見込めます。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
リスキリング導入の3ステップ

ここまで、リスキリングが一部の企業だけでなく、全ての企業にとって重要である理由をご紹介しました。ここからは、実際にリスキリングを導入する際の手順について、見ていきましょう。
リスキリングを導入するステップは次の3つです。
- 求めるスキルと教育対象者の決定
- 社外の専門サービスやコンテンツを活用
- 社員のフィードバックをもとに継続的に実施
流れにそって解説していきます。
1.求めるスキルと教育対象者の決定
まず、会社としてリスキリングによって獲得したいスキルと、どのような人材を教育対象とするかを決定します。
事業方針や経営戦略をもとに、自社に求められる人材要件や未来の組織像を固めていきましょう。これを明確にしておくことで目指すべきゴールが明らかになり、現状とのギャップがみえてくるため、当事者である社員の納得感が得やすくなります。
リスキリングにぜひ取り上げたい講座は、以下の記事で詳しく解説しています。
『リスキリングで学ばせるべき講座5選|ベストな教育方法とは』
2.社外の専門サービスやコンテンツを活用
リスキリング施策のゴールと対象者が決定したら、学習方法の検討をします。
リスキリングは、社員に対して学習の”場”を提供することが大切です。オンライン学習ができるLMS(学習管理システム)などを活用すると良いでしょう。
社内で学習プラットフォームを開発している企業もありますが、リスキリング用の学習プラットフォームをすべて社内で開発するのは効率的とは言えません。社外のLMS(学習管理システム)等を活用することで、開発のコストや負担をかけずに質の高い学習プラットフォームが利用できます。
社外サービスを利用したリスキリングの実施方法は、後ほど詳しく解説します。
3.社員のフィードバックをもとに継続的に実施
リスキリングの実施は、一度きりの研修だけではなく継続的に行うことが重要です。
そのため、学習管理の不手際や不十分な学習計画によって社員自身の学ぶ意欲が低下しないよう、当事者である社員からのフィードバックを大切にしましょう。
社員の意見を参考に、リスキリングの実施方法や学習管理方法をブラッシュアップすることで、より学びやすく身につきやすいリスキリング施策が実施できます。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
リスキリングの実施方法
リスキリングの実施方法として、以下の3つが挙げられます。
- 集合研修
- 書籍の提供
- eラーニング
それぞれのメリットや特徴について、詳しく見ていきましょう。
集合研修
リスキリングを実施する方法の一つに、集合研修があります。集合研修では、社員が研修の会場に集まって講師の指導を受けます。集合研修のメリットは以下の通りです。
- 受講者同士の交流により、モチベーションが高まる
- 講師に直接質問できるため、理解が深まりやすい
- 実習や演習を通して、実践的なスキルが身につく
一方で、集合研修はスケジュール調整が難しく、業務の関係で欠席せざるを得ない社員が出てしまう点がデメリットです。
特にリスキリングのような長期的な教育施策では、受講者の欠席が続いてしまうと十分な成果が得られない可能性があります。
書籍の提供
リスキリングにおいて、関連書籍を提供することも効果的な学習方法の一つです。会社が選定した書籍を社員に配布することで、自主的な学習を促すことができます。書籍の選定にあたっては、以下のポイントを押さえましょう。
- 会社のDX戦略に沿った内容の書籍を選ぶ
- 実践的で応用しやすい知識が得られる書籍を優先する
- 読みやすく、モチベーションが上がる内容の書籍を選ぶ
書籍による自習は、集合研修のように業務の状況で欠席してしまうリスクが避けられる反面、全ての受講者が意欲的に学習するとは限らない点は無視できません。
集合研修と書籍での自習のいいとこ取りができる学習方法が「eラーニング」です。
eラーニング
eラーニングは、時間と場所を選ばずリスキリングの学習ができる手法です。eラーニングのメリットは以下の通りです。
- 自分のペースで学習を進められる
- いつでもどこでも学習できる
- コストを抑えられる
- LMSで学習履歴の管理がしやすい
実際にリスキリングを成功させた企業の多くが、eラーニングによるオンライン学習を導入しました。
成果にこだわってリスキリング施策を行いたいとお考えなら、eラーニングでの実施を検討しましょう。
実際にリスキリングを導入した企業の事例
リスキリングを実際に導入している国内企業の事例をご紹介します。
富士通株式会社
富士通株式会社は、独自のDX施策として「Fujitsu Transformation」略して「フジトラ」の推進を行っています。その一環として、13万人にもおよぶグループ社員に対して
- デザイン思考
- アジャイル
- データサイエンス
のスキル習得に向けたリスキリングを行っています。
2020年の時点で、「今後5年間に5,000〜6,000億円をかけて変革を加速する」という方針を発表しているため、リスキリングにも精力的に取り組んでいます。
旭化成株式会社
旭化成株式会社では、全従業員をデジタル活用人材へと育てるためのリスキリングを行っています。社内のeラーニングシステムでオンライン学習を行い、テストの結果によってレベル1〜5のバッジを付与する「DXオープンバッジ制度」という評価システムが特徴的です。
バッジの種類や数は人事評価には影響せず、受講者のモチベーションを高めるために活用されています。2023年6月時点で、国内の約半数の社員がレベル3のバッジを受け取っています。メールフッターや名刺ロゴ、SNSなどにバッジを表示してスキルをアピールできる仕組みによって学習への意欲を高めています。
参考:組織風土改革にもつながった 旭化成の「DXオープンバッジ」制度
住友生命保険相互会社
住友生命保険相互会社では、上流工程にいるエンジニアを対象にリスキリングを実施しています。
社内で「Vitality DX塾」という教育プログラムを発足し、実務ベースのスキルアップを狙ったカリキュラムを提供しました。集合研修とオンライン研修を組み合わせたプログラムは、DX人材としての意識の変革をメインとした研修内容です。
全社員を対象とするのではなく、特定の層から適切な人材を選出して集中的に教育をすることで、リスキリングを成功に導いた事例です。
リスキリングを実施する上での注意点
リスキリングを導入する前に、知っておきたい注意点があります。
- 社内の協力体制を事前に構築する
- 自社のリスキリングに最適なコンテンツを選ぶ
- リスキリングに対するモチベーションの維持を行う
- 適切な学習管理を行う
実際にリスキリングを行ってからつまずくことが無いように、確認しておきましょう。
社内の協力体制を事前に構築する
リスキリングは、単なる社内研修ではありません。企業の存続に関わる、大事な経営戦略と言えるでしょう。
しかし、実際に日々の業務の中にリスキリングのスケジュールを入れると、周囲から「この時間は働いてもらいたいのに」「社内ミーティングの時間をずらさなくてはいけない」といった不満の声が上がる可能性が高いです。このような状況になると、リスキリングの対象である社員が仕事をしづらくなってしまったり、リスキリングに対する印象が悪くなってしまいます。リスキリングを成功させる第一歩は、社内にリスキリングの重要性を浸透させる協力体制を構築することです。
導入する前に全社員に向けた説明会を実施するなどして、リスキリングに対して前向きに取り組める環境づくりをしましょう。
自社のリスキリングに最適なコンテンツを選ぶ
リスキリングのために、評判の良い学習コンテンツを利用したとしても、その内容が自社のリスキリング実施目的に合っていなければ、学習効果は期待できません。
既存のコンテンツでは補いきれない専門性の高い内容や、自社独自の内容の場合は、オリジナル教材を作ることも視野に入れましょう。eラーニングシステムを提供するベンダーの中には、オリジナルのeラーニング教材の作成をサポートしてくれるサービスもあります。
教材の内容だけではなく、学習プラットフォームとしての使いやすさも重要です。複雑な操作のオンライン学習では、リスキリングを進めることに消極的になってしまうリスクが考えられます。
リスキリングに対するモチベーションの維持を行う
プログラミングなどの、習得難易度が高いスキルのリスキリングを行う場合は、社員のモチベーションを維持できるかどうかが成功の鍵となります。
以下のような対策を行って、モチベーションを落とさないように工夫しましょう。
- 同じスキル習得を目指す仲間を集めて取り組ませる
- スキル習得に対してインセンティブを用意する
- リスキリングによって成長できていることを体感させる
eラーニングで自主学習をさせる場合は、学習の進捗にそった適切なフィードバックもモチベーション維持に役立ちます。
適切な学習管理を行う
リスキリングを実施する上では、従業員の学習状況を適切に管理することが重要です。学習状況の管理には、LMS(学習管理システム)を活用しましょう。
LMSには、以下のような学習管理機能が搭載されています。
- 受講者ごとの学習進捗の可視化
- テスト結果の集計
- 受講者を属性ごとに分け、グループ別に教材配信
- 集合研修・オンライン研修の出席管理
リスキリングは長期的な取り組みとなるため、LMSによる管理業務の効率化が成功の鍵となります。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
リスキリングの実施なら「etudes」がおすすめ

etudesは、多くの企業に選ばれている実績のあるeラーニングシステムです。
管理者も受講者も使いやすい、直感的に操作ができる画面デザインや、初期費用が無料で利用料はユーザー数ごとの課金制という導入のしやすさが評価されています。eラーニングによる社内研修がetudesの主な利用シーンですが、リスキリングの管理にも最適なLMSです。
その理由を次から見ていきましょう。
人材育成会社が作り上げたeラーニングシステム
etudesを開発したのは、企業向けの人材育成を行っている「アルー株式会社」です。20年以上に渡ってさまざまな人材育成を行ってきたアルー株式会社だからこそ、成果にこだわるeラーニングシステムを作り上げることができました。
etudesには、階層別研修からスキル別研修まで活用できる豊富な教材が揃っています。それだけではなく、自社オリジナルeラーニング教材を作成する支援サービスも行っています。
リスキリングを実施するために自社のノウハウをeラーニング化したいという要望も、etudesにお任せください。人材育成のプロフェッショナルが、効果的なeラーニング教材作りをトータルでサポートします。
「etudes Plus」ならeラーニングが受け放題
etudesの教材をご利用いただくにはコンテンツ費用が発生しますが「etudes Plus」をお選びいただけば、月額料金のみで100以上のeラーニング教材が受け放題になります。
全社的にリスキリングに取り組む、あるいは複数の部署でリスキリングを実施するのであれば、etudes Plusはお得なプランと言えるでしょう。費用面での制限を気にせずに、受けたいeラーニングを選んで受講することができます。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
国内外の多くの企業が取り組む「リスキリング」について、具体的な内容やその導入方法、成功事例について詳しく解説しました。
リスキリングは、単なる学び直しとは異なり、新しいスキルの獲得やスキルアップによって社員の新たな価値創造を行うための手法です。
今からリスキリングを導入し意欲的に取り組むことで、5年後、10年後の企業の在り方が変わるといっても過言ではないでしょう。
さまざまな企業の成功事例から、リスキリングにはeラーニングなどのオンライン学習が効果的であることがわかります。eラーニングシステムの導入をお考えならLMSの「etudes」と、人材育成会社による豊富な教材が受け放題になる「etudes Plus」の導入をぜひご検討ください。