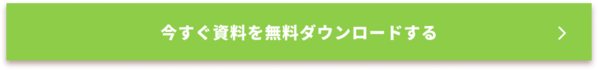コンセプチュアルスキルの研修の方法は?|目的と内容をご紹介
ビジネスの場において、物事の本質を的確に見抜き素早い状況判断を行うために必要不可欠なコンセプチュアルスキル。グローバル化やIT化によって目まぐるしく変化する現代社会に対応するには、階層や役職、職種に関わらず全ての社員に身につけさせるべきと言えます。
今後ますます重要度が高まるコンセプチュアルスキルを社員に効率的に習得してもらうためには、eラーニングなどを活用しながら効率的にコンセプチュアルスキルの人材育成施策や研修を実施するのがおすすめです。
実際に企業でどのように人材育成をしているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
定額制受け放題eラーニングetudes Plusが分かる3点セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
コンセプチュアルスキルとは
コンセプチュアルスキルとは、複雑な物事の本質を素早く見抜いて、最適な解決策を提案する能力のことを言います。日本語では「概念化能力」と訳されますが、人材育成の業界では「コンセプチュアルスキル」とそのまま用いられることが一般的です。
コンセプチュアルスキルは、アメリカの経済学者であるロバート・カッツが提唱した「管理職に求められる3つのスキル」のうちの1つを構成する重要な能力です。
ビジネスでは様々な状況で判断を下す必要に迫られますが、しっかりとしたコンセプチュアルスキルが身についていると、曖昧な物事や複雑な事態に遭遇した際に素早く現状を分析した上で、課題解決に向けた的確なアプローチを取ることができます。
コンセプチュアルスキルが求められる役職
かつて、コンセプチュアルスキルは、特に会社の舵取りを担うトップマネジメント層や管理職以上に求められるスキルでした。役職が高くなるにつれ、直面する課題の影響範囲は広くなり、かつ、複雑になります。トップマネジメント層が企業を取り巻く複雑な経営状況をしっかりと把握し、より良い判断を行うことが会社の命運にも直結します。
しかしながら、最近ではトップマネジメント層や管理職層のみならず、管理職手前の中堅社員や若手社員にまで、コンセプチュアルスキルが求められるようになってきました。
コンセプチュアルスキルが幅広い層に求められるようになった背景を、詳しく見ていきましょう。
コンセプチュアルスキルが求められる背景
コンセプチュアルスキルは管理職を始めとした多くの社員に求められる重要な能力ですが、なぜ最近これほどまでにコンセプチュアルスキルが重視されるようになってきているのでしょうか。
コンセプチュアルスキルが重要性を増している理由として、市場の変化や技術の発展が速くなっているという点が挙げられます。
10年前にはAIがここまで普及しているとは考えられなかったように、もはや10年後の状況を予測することは不可能といっても過言ではありません。そのような時代には、素早く適正な決断を行うことで、社会の変化に対して柔軟かつ迅速に対応できるようなるのです。
判断が必要になるのは、トップマネジメント層だけではありません。現場でも日々目まぐるしく状況が変化しますが、毎回のように管理職層の承認を取っていたら変化に乗り遅れてしまいます。そのため、現場で活躍する中堅社員や若手社員にもコンセプチュアルスキルが求められるようになってきました。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
コンセプチュアルスキル研修を行う目的

コンセプチュアルスキルが高い人材、というと、「生まれつき頭のいい人」を想像するかもしれません。確かに生まれつき高いコンセプチュアルスキルを持った人がいることは事実ですが、コンセプチュアルスキルは教育によって後天的に身につけることができます。コンセプチュアルスキル研修を実施する目的について見ていきましょう。
生産性の向上につながる
コンセプチュアルスキルを身につけると、物事を論理的に体系的に整理することができるようになります。組織で仕事をする上で、認識の齟齬から生じるミスや手戻りが発生することもあるでしょう。物事が誰にでもわかりやすく整理されていれば、こういったすれ違いを防ぐことができ、生産性の向上につながります。
研修を通じて社員のコンセプチュアルスキルを底上げすることは、企業全体の生産性を向上させることに直結します。 管理職のコンセプチュアルスキルが高まると、重要な意思決定や判断をより的確に行うことができるようになるという効果が期待できます。また、中堅社員や若手社員のコンセプチュアルスキルを高めることで、現場の状況をわかりやすく整理し、組織に対して本質を見極めた的確な提言を行うことができるようになるでしょう。
本質的な課題を抽出し、問題解決力をつける
コンセプチュアルスキル研修を実施する目的として多いのが、本質的な課題を抽出することで、問題解決力をつけることです。問題解決をするためには、自分の置かれている現状を的確に把握した上で、適切な打ち手を考える必要があります。
売上数字や原価率といった定量的データももちろん重視しますが、特定した課題に対して、「この課題の原因は何だろうか?本当にそうだろうか?他にはないだろうか?」と深く深く思考できるのが高いコンセプチュアルスキルを持った人材の特徴です。本質的な課題を抽出することで、的確に問題解決を行うことができるようになります。
組織の方向性や全体像を共有できるようになる
高いコンセプチュアルスキルを持った人材は、自社の置かれている状況をわかりやすく整理し、的確に分析することができます。組織がまとまらず、高いパフォーマンスを発揮できていないケースでは、自社の課題はどのような点にあり、今はどのような目標に向かっているのか、といった組織の方向性が社員に伝わっていないことが多々あります。
管理職以上の社員を対象に、的確に状況を把握できる人材を増やすこともコンセプチュアルスキル研修を行う目的です。
組織にイノベーションをもたらすことができる
コンセプチュアルスキルを身につけることで、社員は固定観念や常識といった枠にとらわれない思考ができるようになります。これまで当たり前に取り組んできたことについての「そもそも」を考えることで、組織のイノベーションにつながる発想を引き出すこともコンセプチュアルスキル研修を実施する目的です。
コンセプチュアルスキルを高めることで、これまでにない製品やサービスを生み出すことに繋がることはもちろん、業務フローの改善に向けた提言や、手続きプロセスの改善といった日常的な業務のイノベーションも期待できます。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
アルー株式会社のコンセプチュアルスキル研修の内容
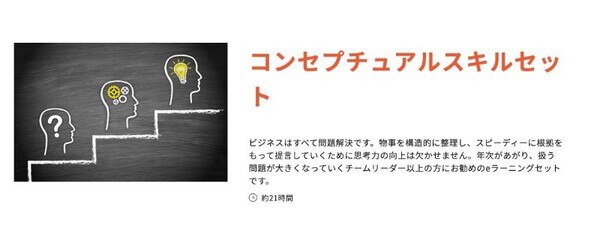
ここまで紹介してきたように、コンセプチュアルスキルは変化の激しい時代を生き残っていくために必要不可欠な能力です。人材育成会社の「アルー株式会社」では、様々なコンセプチュアルスキル強化の研修パッケージをご用意しています。約20年の企業研修支援のノウハウをもとに、独自のeラーニングも制作しています。
ロジカルシンキングや問題解決思考、定量的思考など、コンセプチュアルスキルのパッケージで取り扱うトピックについてご紹介します。
アルーのeラーニング教材「コンセプチュアルスキルセット」詳細ページ
ロジカルシンキング
ロジカルシンキングは、日本語では「論理的思考」と訳され、物事を筋道立てて体系化するスキルです。コンセプチュアルスキルのなかでも基礎的なスキルであり、ビジネスの現場において欠かすことのできない能力です。ロジカルシンキングスキルが高まることで、より良い問題解決やわかりやすいコミュニケーションにつながります。
アルー株式会社が提供するロジカルシンキングはすべての階層の方におすすめです。ロジカルシンキングの原則からはじめ、グルーピングや根拠づけ、MECEといったロジカルシンキングの中核をなすルールについて学習することが可能です。
問題解決思考
アルー株式会社が提供する「問題解決思考」は、合理的に問題解決を行うための思考プロセスの基本について学ぶことができるカリキュラムです。
このカリキュラムでは、ビジネスは問題解決の連続であるということを把握してもらい、問題解決に向けた思考法の全体像について学びます。さらに、問題の明確化や問題の所在の特定といったトピックについて、ケーススタディを交えながら学習することが可能です。原因追求や対策立案、実行・検証のプロセスについても学びます。
設定型問題解決
「設定型問題解決」においては、あるべき姿を高くおくことで自ら問題を設定して解決を行うプロセスについて学ぶことができます。
このカリキュラムでは、動画での学習を通じて問題の定義の仕方や、発生型・設定型・創造型の問題解決の違いについて学習します。それぞれの問題解決の手順について、正しい説明を選択する演習問題に取り組み知識の定着を図ります。
学んだ知識を生かして自部署の問題設定にも取り組ませることができます。問題設定から課題解決までの一連のプロセスを体験して身につけられる研修です。
仮説思考
仮説を立てることで問題の特定や課題解決を目指す仮説思考の方法は、コンセプチュアルスキルを構成する重要な要素の一つです。仮説思考のカリキュラムでは、仮説思考の定義や原則、さらには仮説思考の重要性についての認識を深めることができます。
このような、思考法を学ばせる研修では、身につけた知識を実践できる演習問題によってスキルを定着させるサイクルが重要です。
アルー株式会社の仮説思考のカリキュラムは、仮説を立てるためには論点の明確化が必要だといった基本的な知識から、「店舗の2号店を出店するべきなのか」といった具体的な演習問題への取り組みまで網羅しています。
定量的思考
定量的な思考は、物事をより的確に判断するために必要な思考です。数字やデータといった具体的な根拠に基づいた判断を下すことで、周囲を納得させることができる意思決定が行なえます。アルー株式会社では、この能力を高めるための「定量的思考」カリキュラムも提供しています。
定量的思考では、「回転すしの年間市場規模を求める」といった演習問題に取り組みます。最適なプロモーションの推計などの実践的な内容もふんだんに含まれているため、具体的な定量的思考の手法について学ぶことが可能です。
ロジカルコミュニケーション
ロジカルコミュニケーションは、相手との円滑なコミュニケーションを行うため、自分の考えを論理的に伝える能力のことを指します。わかりやすく情報を伝えるとともに、相手の話を的確に整理して理解するという点も重要です。
ロジカルコミュニケーションのカリキュラムでは、ロジカルコミュニケーションの概要を動画を通じて確認し、情報のピラミッド構造化といった活動に取り組みます。また、グルーピングや根拠付け、MECEといった論理的思考の基礎となる事項を確認し、論理的な思考を相手に的確に伝えるためにはどのようにすればよいのかを演習を通じて確認します。
プレゼンテーション
プレゼンテーション能力は、相手にとって納得感のある説明を行うための能力です。高いプレゼンテーション能力があると、説得力のある説明を行うことができ、組織そのものを動かすこともできます。
アルー株式会社のプレゼンテーションカリキュラムでは、効果的なプレゼンテーションを行うための資料作成方法について学習します。プレゼンテーションの内容をピラミッド構造に基づいて構成する手法や、スライド1枚1枚に意義をもたせるといったプレゼンテーション構成の原則について学ぶことが可能です。
ロジカルシンキングドリル
先ほどご紹介した「ロジカルシンキング」では、ピラミッド構造という重要な構造化手法について学びます。ピラミッド構造を素早く、的確につくるためには一定の経験値を積む必要があります。そこで、ピラミッド構造を作るための4つのルールについて、一問一答形式のドリルに取り組むことでロジカルシンキング力を高められるのがロジカルシンキングドリルです。
ロジカルシンキングドリルのカリキュラムでは、ふんだんに演習問題が用意されていることが特徴です。4問ずつで構成されたパートが12パート用意されており、約4ヶ月間をかけながら少しずつロジカルシンキングの能力を身につけていくことができます。
問題解決思考ドリル
ビジネスの現場は、常に問題解決の連続です。高い問題解決能力があると、自分の目の前の仕事を効率的にこなせるようになるばかりか、組織全体の生産性を向上させることにも繋がります。
問題解決思考ドリルは、問題解決プロセスについての一問一答を集めたカリキュラムです。ロジカルシンキングドリルと同様に4問ずつのパートが12パート用意されており、約4ヶ月間をかけながらじっくりと問題解決プロセスについて学習することができます。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
コンセプチュアルスキル研修の効果を高める方法
コンセプチュアルスキル研修を実施することは、社員の判断能力の向上や生産性の向上といった面で様々なメリットがあります。それでは、実際にコンセプチュアルスキル研修の効果を高めるためには、どのような点に注意したらよいのでしょうか。
本当に効果があがるコンセプチュアルスキル研修を実施するためには、インプットだけでなくアウトプットにも注力することも必要です。
インプットだけではなくアウトプットを実施する
コンセプチュアルスキル研修は、ロジカルシンキングの能力や水平思考の能力など、ともすれば座学だけで完結してしまう内容になりがちです。しかし、社員がただ講演を聞くだけの研修を実施してしまうと、社員の能動的な学習を引き出せず、研修に対するモチベーションを低下させてしまいかねません。
コンセプチュアルスキル研修を実施する際には、「〇〇店の売上を向上させるためにはどのようなアプローチが良いか、ディスカッションしてもらう」といったように、実務に近い演習を通じたアウトプットの機会を用意することがポイントです。研修終了後に、理解度確認のためのテストを行うことも効果的でしょう。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
コンセプチュアルスキル研修の実施方法

コンセプチュアルスキル研修を行う際には、従来の対面型研修のほか、外部での研修に参加してもらう、eラーニングを活用してもらう、といった様々な方法が考えられます。
それぞれの方法にはメリットとデメリットの双方が存在するため、研修の目的に合わせてこれらを上手く使い分けていくことがポイントです。コンセプチュアルスキル研修の実施方法について3つ紹介します。
外部研修
コンセプチュアルスキル研修の方法として、社員に外部で実施している研修やセミナーへ参加してもらうという方法が挙げられます。外部研修では、論理的思考能力やクリティカルシンキングといった、コンセプチュアルスキルを高める上で欠かせない知識について体系的に学ぶことができるのが特徴です。
一定の質が担保されているというメリットがある一方で、外部研修はコストがかさみやすいというデメリットがあります。会社の規模によっては、金銭的な負担が大きく効果がコストに見合わないというケースもあるかもしれません。
社内での対面研修
最もオーソドックスな研修方法として、社内での対面研修が挙げられます。
研修の対象となる社員に会場へ集まってもらい、その場で研修を行う方法です。講演者を外部から呼んで講演してもらう場合もあれば、社内で研修の内容を用意する場合もあります。
社内での対面研修の場合、コンセプチュアルスキルのような複雑なスキルであっても集中的に時間をとって学習してもらいやすいというメリットがあります。一方、外部講演を依頼する場合ではコストがかかるという点がネックです。また、研修に使う資料を印刷したりテストの集計をするといった研修管理側の負担も考慮する必要があります。
eラーニング
eラーニングは、パソコン、スマートフォンといった端末を利用して、動画コンテンツなどを用いたオンライン学習ができる研修方法のことです。eラーニングを活用することで、研修対象者はいつでもどこでも学習を行うことができます。
eラーニングを用いた研修を実施するメリットとして、在宅勤務中の社員や遠方に住んでいる社員の負担を軽減することができるという点が挙げられます。また、オンライン上で実施するテストを通じて、理解度をすぐに確認できるという点もメリットです。
eラーニングによってコンセプチュアルスキル研修を行えば、受講者にとってわからないところや理解ができない箇所があったら巻き戻して見返せるという利点もあります。わからないまま講義をつい聞き流してしまい、結果的にスキルが身に付かなかったという事態を避けることができるでしょう。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
etudesならコンセプチュアルスキル研修を簡単に実施可能

アルー株式会社が提供するLMS「etudes」では、コンセプチュアルスキルと思考力をあわせて高めるためのセットプラン「思考力・コンセプチュアルスキル」をご利用いただくことができます。コンセプチュアルスキルを構成する要素は多彩で複雑なため、eラーニングを通じて効率的に学習させることがおすすめです。
また、アルー株式会社では「etudesPlus」というeラーニング受け放題プランもご用意しています。etudesPlusなら、コンセプチュアルスキル研修も月額料金定額の受け放題でご利用いただけます。また、コンセプチュアルスキルと思考力のいずれか一方のみをバラで受講したい、というケースにも柔軟に対応させていただいております。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
まとめ
コンセプチュアルスキルを高めるための研修方法や、コンセプチュアルスキル研修の内容などについて解説しました。IT技術の発展やグローバル化に伴って目まぐるしく時代が変化している現代において、物事の本質を素早く把握して適切な問題解決を行うことができるコンセプチュアルスキルは必要不可欠です。
社員のコンセプチュアルスキルを底上げするためには、コンセプチュアルスキルを高めることに特化した研修の実施が有効です。ぜひこの記事の内容を参考にして、効果的なコンセプチュアルスキル研修を実施しましょう。