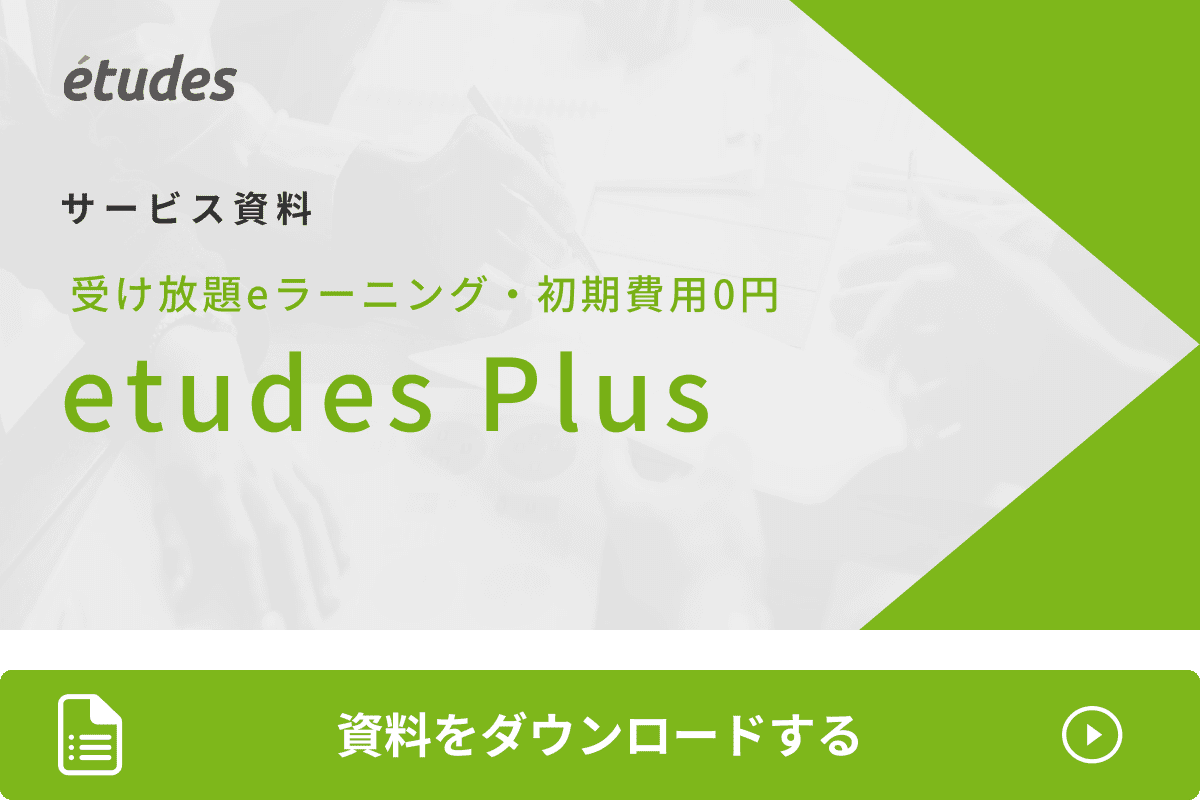ポータブルスキルとは?具体例や鍛える方法についてご紹介
現代のビジネス環境は、変化と競争が激しくなっています。各企業は、社員一人ひとりが持っているスキルを最大限に活用し、組織全体の競争力を高めることを求められています。そのなかで職種や業種を問わずに活用できる汎用性の高いポータブルスキルが注目されています。最近では、社員のポータブルスキルの向上・育成にeラーニングを活用する企業が増えてきています。本記事では、ポータブルスキルの定義、具体的な例、社員のポータブルスキルの鍛え方についてご紹介いたします。
実際に企業でどのようにeラーニングを活用しているのか、他社事例を知りたい方はこちらのページで詳しくご紹介します。
etudesでは「人材育成の運営工数を削減したい」「eラーニングで育成施策の成果を上げたい」企業様をご支援しています。人材育成にお困りの方はお気軽にご相談ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
目次[非表示]
- 1.ポータブルスキルとは?
- 1.1.厚生労働省のポータブルスキルの定義
- 1.2.アンポータブルスキルとの違い
- 1.3.テクニカルスキルとの違い
- 2.ポータブルスキルが必要とされる理由
- 2.1.雇用体制の変化
- 2.2.雇用の流動性の高まり
- 2.3.VUCAへの対応
- 3.ポータブルスキルの要素
- 3.1.仕事のし方(対課題)
- 3.2.人との関わり方(対人)
- 4.ポータブルスキルの具体例
- 4.1.情報収集力
- 4.2.問題解決力
- 4.3.コミュニケーション能力
- 4.4.マネジメント能力
- 4.5.リーダーシップ
- 5.ポータブルスキルを診断する方法
- 6.社員のポータブルスキルを鍛える方法
- 7.ポータブルスキルの習得ならetudesをご利用ください
- 8.まとめ
定額制受け放題eラーニングetudes Plusが分かる資料セット(会社紹介・サービス概要・導入実績)をダウンロードする
ポータブルスキルとは?
ポータブルスキルとは、個々の職業や業種、職場環境に依存せず、どんな状況でも活かせる普遍的なスキルのことを指します。
具体的には、コミュニケーション能力や問題解決力、自己管理能力などが該当します。これらは特定の専門知識や技術とは異なり、場所や状況を問わずあらゆる業種や職種で必要とされるスキルです。
ポータブルスキルを効率的に身につける手段として、eラーニングを活用することがおすすめです。eラーニングは、インターネットがあれば自身の都合に合わせて学習ができ、何度でも復習することができます。また、映像などのコンテンツもあるため、視覚的に理解しやすく学習を進めることができます。
eラーニングには様々なテーマのコースが用意されていますが、ポータブルスキルの向上には、etudesの思考力・コンセプチュアルスキルコースがおすすめです。
思考力・コンセプチュアルスキルコースでは、物事を緻密に考え伝えるためのロジカルシンキング、合理的に問題解決を行うための問題解決思考などビジネスに必要な思考力をアップすることができます。
思考力がアップすることで、業種、職種、職位に関わらずビジネスの基礎的なスキルを習得するための基礎を固めることができます。思考力のアップも汎用性の高いポータブルスキルの一つとなります。
etudesの思考力・コンセプチュアルスキルコースについては、以下からご覧ください。
※関連ページ:思考力・コンセプチュアルスキル
厚生労働省のポータブルスキルの定義
厚生労働省は、ポータブルスキルを「職種の専門性以外に、業種や職種が変わっても持ち運びができる職務遂行上のスキル」と定義しています。
参考:ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)
業種や職業を問わず、どのような仕事についていても必要なスキルで、先行きの不透明なVUCAの時代で働くビジネスパーソンには必須のスキルといえるでしょう。
厚生労働省の定義するポータブルスキルは、「仕事のし方」と「人との関わり方」の2つに分けることができます。この2つについては、「ポータブルスキルの要素」で紹介いたします。
アンポータブルスキルとの違い
アンポータブルスキルとは、特定の職種や業界特有のスキルを指します。
たとえば、特定のソフトウェアを使いこなす能力や、医師や弁護士などの専門的な知識が該当します。アンポータブルスキルは、その職種での専門性を高め、業界内での競争力を上げられますが、別の職種や業界では役立たない可能性があります。
対して、ポータブルスキルは、どの職種や業界においても使える汎用性の高いスキルを指します。たとえば、コミュニケーション能力や問題解決力などが該当します。ポータブルスキルは、あらゆる状況で活用できるため職種や業界を問わず必要となります。
具体的な違いは、下記の通りです。
項目 | ポータブルスキル | アンポータブルスキル |
特徴 | 汎用性が高く応用可能なスキル | 特定の業界や職種に特化したスキル |
活用場面 | どの場面でも活用可能 | 活用できる場面が限定的 |
例 | コミュニケーション能力、問題解決能力など | 特定のプログラム言語、特定の機械操作能力など |
以上がポータブルスキルとアンポータブルスキルの大きな違いです。それぞれを適切なバランスで身につけることが、キャリア形成において重要となります。
テクニカルスキルとの違い
ポータブルスキルとテクニカルスキルは、どちらも職場で求められるスキルですが、その特徴には大きな違いがあります。
テクニカルスキルとは、特定の職種や業界で直接活用できる専門的な技術や知識を指します。例えば、プログラミングスキルや会計知識などが該当します。テクニカルスキルは、その分野で働く上で必要不可欠なものであり、専門性や深い知識が求められるため習得には時間と経験が必要です。
一方、ポータブルスキルは職種や業界を問わず広く活用できる汎用的な能力・スキルを指します。具体的には、リーダーシップや問題解決力、コミュニケーション能力などがあります。これらのスキルは、どの職場でも活かすことができ、途中で転職した場合でも活用していくことが可能です。
具体的な違いは、下記の通りです。
スキルの種類 | 定義 | 具体的な例 | 違い |
テクニカル | 特定の職種や業界で直接活用できる専門的な技術や知識 | プログラミング能力、会計知識など | 特定の業界で働くために必要で、専門性や深い知識が求められる |
ポータブル | 職種や業界問わず広く活用できる汎用的な能力・スキル | リーダーシップ、問題解決能力、コミュニケーション能力など | どの業界でも活かすことができ、転職した場合でもそのまま活用できる |
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
ポータブルスキルが必要とされる理由

ここからは、ポータブルスキルが必要とされている理由をご紹介します。
ポータブルスキルが必要とされる理由は、下記の通りです。
- 雇用体制の変化
- 雇用の流動性の高まり
- VUCAへの対応
簡潔にまとめると、下記の通りです。
ポータブルスキルが 必要とされる理由 | 内容 |
| 終身雇用制度や年功序列などが見直され、リモートワークの普及など働き方が多様化 |
雇用の流動性の高まり |
|
VUCAへの対応 | 先行きが不透明なVUCAの時代でも、ポータブルスキルは有用 |
ポータブルスキルの鍛え方については、以下の記事で詳しく解説しています。
【ポータブルスキルの鍛え方|社員にポータブルスキルを身につけてもらうメリット】
雇用体制の変化
現在の日本のビジネス環境では、従来では一般的だった終身雇用や年功序列などの制度が、少子高齢化やリモートワークの普及などの働き方の多様化によって、変化が起こっています。
ポータブルスキルは仕事を行う上で、どのような職種・業種であっても必要な汎用的スキルです。世界情勢や雇用体制が変わったとしても、活躍できる人材になるため、ポータブルスキルは注目されています。
雇用の流動性の高まり
終身雇用の見直しや、多様な働き方が増えた現在では、人材の流動性が高まっています。個人では、所属組織の中で活躍の場を広げたり、転職活動を見据えた市場価値向上を目的にポータブルスキルは注目されています。
一方で企業側から見ても、ポータブルスキルが長けている人材は、変化に対応しやすくキャリア育成がしやすいため、積極的に採用したい人材です。
そのため、個人においても企業においてもポータブルスキルは注目されているのです。
VUCAへの対応
先行きが不透明で、将来の予測ができない「VUCA」の時代である今、想定外の出来事や業界の常識を覆す価値観やサービスの登場が起こっています。
例えば、これまで高度なシステムで自社サーバーにシステム構築が必要だったものも、クラウド化によって月額制で簡単に利用できるようになっていたり、急速な環境変化が起こっています。
このような先行きが不透明でビジネスの変革が急速な時代でも、ポータブルスキルは有用です。ポータブルスキルは、特定の業種や時代背景にとらわれることなく、活用できるスキルです。ポータブルスキルを身につけていれば、VUCAの時代で突然のキャリアショックに遭ったとしても、特定の分野だけでなく、さまざまな分野で活躍できる可能性が高まり、キャリアの選択肢を広げることが可能です。
変化の激しい時代に、汎用性の高いポータブルスキルを持つ人材の需要はますます高まっていくことが予想されます。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
ポータブルスキルの要素
では、ポータブルスキルとは具体的に、どのようなスキルなのでしょうか。
ここでは、厚生労働省が定義しているポータブルスキルをもとに、ポータブルスキルの要素を一覧で紹介いたします。
仕事のし方 | 現状の把握 | 取り組むべき課題やテーマを設定するために行う情報収集やその分析のし方 |
課題の設定 | 事業、商品、組織、仕事の進め方などの取り組むべき課題の設定のし方 | |
計画の立案 | 担当業務や課題を遂行するための具体的な計画の立て方 | |
課題の遂行 | スケジュール管理や各種調整、業務を進めるうえでの障害の排除や高いプレッシャーの乗り越え方 | |
状況への対応 | 予期せぬ状況への対応や責任の取り方 | |
人との関わり方 | 社内対応 | 経営層・上司・関係部署に対する納得感の高いコミュニケーションや支持の獲得のし方 |
社外対応 | 顧客・社外パートナー等に対する納得感の高いコミュニケーションや利害調整・合意形成のし方 | |
上司対応 | 上司への報告や課題に対する改善に関する意見の述べ方 | |
部下 | メンバーの動機付けや育成、持ち味を活かした業務の割り当てのし方 |
引用:ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)
それぞれの要素について、以下で詳しく紹介いたします。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
仕事のし方(対課題)
仕事のし方は、業種や職種に依存しない、業務を遂行する上で必要なスキルです。具体的な要素としては、以下の5つに分けることができます。
- 現状の把握
- 課題の設定
- 計画の立案
- 課題の遂行
- 状況への対応
それぞれ詳しく見ていきましょう。
現状の把握
状況の把握とは、担当業務に必要な情報を収集しているかどうかや、部署や顧客の情報を収集し、自社に与える影響を多角的に分析できるかどうかなどの情報収集のスキルです。
階層ごとに情報収集の範囲が変わり、始めは担当部署、最終的には業界全体の情報収集ができるかどうかが求められます。
課題の設定
課題の設定は、現状の課題においてどのように問題解決をしていくかのスキルです。
課題の設定の能力のレベルは、解決困難度から見た課題のレベルで測定されます。最初は既存の解決策の中から適切な方法を選択して対応可能な課題を扱えるようになることが目標で、最終的には前例がなく、自ら仮説を立てて解決策を導き出す必要がある課題を扱えるようになることが求められます。
計画の立案
計画の立案は、戦略や目標立てができるスキルです。最初は担当業務の計画の立案から始まり、最終的には会社全体の計画・戦略を立案することが求められます。
社内のリソースを把握したうえで、適切な業務遂行の計画を立てられているかどうかが求められます。
課題の遂行
課題の遂行は、課題の解決方法を考案して仕事を進めるスキルです。
最初は上司から指示を受けて進められるようになることから始まり、最終的には課題解決の方法を考案して仕事を進められるかどうかが求められます。
スケジュール管理や各種調整など、業務を進める上でのボトルネックとなるものを排除する力や、プレッシャーを乗り越える力なども求められるでしょう。
状況への対応
状況への対応は、仕事を行う上で柔軟な対応ができるスキルです。
最初は既存の方法やマニュアルに沿った対応ができることを目指し、最終的には経営上のリスクを考慮して、既存の方法やマニュアルを超えた柔軟な対応ができるかどうかが求められます。予期せぬ出来事やトラブルの対応なども含んだスキルも含まれます。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
人との関わり方(対人)
人との関わり方のスキルは、上司や経営層などの社内の人とのコミュニケーションや、顧客や他社との関わり方など、全方向の対人スキルのことです。
具体的には、以下の4つに分けられます。
- 社内対応
- 社外対応
- 上司対応
- 部下マネジメント
それぞれ詳しく以下で紹介いたします。
社内対応
社内対応は、幅広く社内の相手とコミュニケーションが取れるスキルのことです。
最初は所属する部署の人との業務連絡や担当業務の説明ができることが求められます。最終的には他部署の人とも新たな価値を生み出すためのコミュニケーションを取れるようになるスキルを求められます。
社外対応
社外対応は、社外の人と新しい価値を生み出すためのコミュニケーションが取れるスキルです。社外の人と情報交換を行えるようになることから始まり、社外の人と新たな価値を生み出すためのコミュニケーションを行うことが最終的に求められます。
上司対応
上司対応は、直属の上司とコミュニケーションを取って仕事を進められるスキルです。
直属の上司に報告・相談とフィードバックを受けて仕事を進めることから始め、階層が上がるにつれて経営層にも自社の課題や改善策を提案できるようになることが求められます。
部下マネジメント
部下マネジメントは言葉の通り、部下に対してマネジメントができるスキルです。
最初は同僚や後輩に助言を行い、最終的には会社のビジョンや経営戦略に基づいて部下指導・育成ができるようになることが求められます。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
ポータブルスキルの具体例
ここからは、ポータブルスキルの具体例をご紹介します。
ポータブルスキルの具体例としては、以下の5つです。
- 情報収集力
- 問題解決力
- コミュニケーション能力
- マネジメント能力
- リーダーシップ
それぞれ詳しく紹介いたします。
情報収集力
情報収集力とは、企業が成功するための不可欠なスキルの一つです。
内部および外部の情報源からデータや情報を効率的に収集し、適切に分析してビジネス上の意思決定を行う能力を指します。
ビジネスにおける情報収集力の役割と理由は、下記のように多岐にわたります。
役割 | 理由 |
市場動向の把握 | 市場の変化やトレンドを正確に把握し、それに基づく適切な戦略を立てる |
競合他社の分析 | 競合他社の動向や戦略を把握し、それに基づく自社の戦略を調整する |
顧客のニーズの理解 | 顧客のフィードバックや市場調査データを収集し、製品やサービスの改善を行う |
業界動向の把握 | 業界の動向や法規制の変化を追跡し、適切な対応策を講じる |
意思決定のサポート | 十分な情報を収集し・分析することで、リスク回避や新規チャンス発見、より適切な戦略や方針策定ができる |
以上が情報収集力の役割と理由になります。これらを理解し、自身の情報収集力を高めることで、ポータブルスキルを高めていくことができます。
問題解決力
問題解決能力は、どんな業種や職種でも直面する問題や課題を解決するために必要とされるポータブルスキルの一つです。
問題を明確に定義し、その原因を分析し、可能な解決策を検討・考案し、最適な選択を行い、実行する能力を指します。
具体的な問題解決ステップは、下記のようになります。
ステップ | 内容 |
問題定義 | 問題や課題を明確に定義し、解決すべきポイントを把握する |
原因分析 | 問題の根本原因を探り、その要因を理解する |
解決策検討・選択 | 問題を解決するための複数のアプローチを考案し、最適なものを選び出す |
実行 | 選んだ解決策を具体的な行動に移す |
評価 | 実行した結果を評価し、必要に応じて改善策を考える |
問題解決能力を磨くことにより、どのような状況においても冷静に解決策を導き出すことが可能となります。
コミュニケーション能力
コミュニケーション能力とは、他人との意思疎通を円滑に行うための重要なポータブルスキルの一つです。
コミュニケーション能力が優れていると、チームの一員として他のメンバーと効率よく協働することが可能となり、組織全体のパフォーマンスも向上します。
コミュニケーション能力を高めるためには、以下の3つが必要です。
- 伝達スキル:情報やアイデアを明確に、かつ効果的に伝える能力。自分が伝えたい内容を明確にし、話の筋道を整理してロジカルに伝えることが求めれる
- 関係構築スキル:他者の意見や観点を理解し、受け入れる能力。他者の立場や感情に共感し、適切な距離感を持って他者と関係を築くことが重要
- 質問スキル:適切で効果的な質問を行う能力。質問を通じて情報を収集し、相手の考えや意図を明確にすることが求められる
これらのスキルは、日々の業務や人間関係の中での練習を通じて、身につけることが可能です。たとえば、社内ミーティングの際に、自分の意見を明確に伝える練習をしたり、他者の意見を理解し反映するような行動を意識的に行うことで、能力を高めることができます。
マネジメント能力
マネジメント能力は、チームやプロジェクトを適切に管理・運営するスキルです。
戦略的な思考力や意思決定力、人材の育成やコミュニケーション、業務の効率化やリスク管理など多岐にわたる能力が求められます。
マネジメント能力は、個々の業務能力だけでなく、組織全体のパフォーマンス向上に直結し、ビジネスの成功を左右する重要な要素です。
マネジメント能力の内容は、大きく下記の通りです。
スキル | 内容 |
戦略的思考力 | ビジョンや目標に向かって成果を出すための道筋を導き出す |
意思決定力 | 問題を的確に認識し、最適な解決策を選択する |
人材マネジメント力 | チームメンバーの能力を伸ばし、適切な役職に配置する |
リスク管理力 | 潜在的な問題を把握し、リスクを最小限に抑える |
マネジメント能力を身につけることで、職業や業種、職場環境に依存せずどんな状況でも活躍していくことが可能です。
リーダーシップ
リーダーシップは、部下やチームメンバーを指導・鼓舞し、組織の生産性や結束力を引き上げる能力のことを指します。リーダーシップは、企業や組織で働く上で、特に重要性が認識されているポータブルスキルの一つです。
リーダーシップを発揮する上で特に重要とされる要素は以下の3つです。
- ビジョンの提示:明確な目標や方向性を示し共有する
- 人の育成:チームメンバーや部下の成長を促すための教育やフィードバックを行う
- 組織運営:リーダーシップには、チーム全体が円滑に機能するようにリソースの分配や役割分担を行う
上記の要素を兼ね備えたリーダーは、組織の生産性を向上させ、チームの結束力を高めることができます。
ポータブルスキルを診断する方法
ポータブルスキルを具体的に診断する方法として、厚生労働省が提供している「ポータブルスキル見える化ツール」を活用することがおすすめです。
ポータブルスキル見える化ツールは、個々の仕事のスキルや能力を可視化するために設計されており、自己のポータブルスキルを明確に把握することが可能です。
ポータブルスキルの診断を行うことで、自分が持っているスキルを明確に理解し、必要なスキルの強化計画を立てることができます。
このツールは自己評価に基づくものであるため、他者からのフィードバックを得ることで、より客観的な評価が可能となります。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
社員のポータブルスキルを鍛える方法

では、社員のポータブルスキルを鍛えるためには、どのような方法があるのでしょうか。
ここでは、社員のポータブルスキルを鍛えるために人事担当者が知っておくと活用できる教育手法をご紹介いたします。
社内の学習に関する仕組みづくりをする
社内研修やワークショップを定期的に開催することで、社員の学びの場を提供することが可能です。
また、ナレッジマネジメントシステムを取り入れることで、経験豊富な社員からの知識やスキルの共有ができるようになるでしょう。
また、eラーニングの教材を社員が自由に閲覧できるようにすることで、社員の自発的な学習を推進できます。
外部の研修を活用する
ポータブルスキルを鍛える場合は、外部の研修会社が提供する研修を利用するのも一つの手です。研修を通じて最新の知識を習得することができ、社内にはない新しいスキルを導入することもできるでしょう。
アルーでは、ポータブルスキルを鍛えるために役立つ研修を実施しています。
アルーが提供している研修は以下のページからご確認いただけます。
テーマ別研修一覧|企業研修・人材育成ならアルー
厚生労働省の研修資料を活用する
厚生労働省は、ポータブルスキルの活用教材を用意しています。
キャリアコンサルタントが、ホワイトカラー職種の求職者や相談者向けに配信している研修資料を活用し、社内研修のヒントにしても良いでしょう。
厚生労働省が公表している動画やテキストは、以下のページからご確認いただけます。
ミドル層のキャリアチェンジにおける支援技法
ポータブルスキルを鍛えるなら、eラーニングがおすすめ
ポータブルスキルは、さまざまなスキルが必要になるため、全てのスキルを集合研修で行うのには時間がかかります。また、ポータブルスキルは汎用的なスキルのため、自社オリジナルの内容にせずとも、質の高い教材はたくさんあります。
そのためポータブルスキルを鍛えるなら、eラーニングを活用することをおすすめします。
スキル別eラーニングプログラムはこちらから
アルーが提供しているetudesでは、ポータブルスキルを鍛えることができる教材を提供しています。eラーニングの活用をお考えであれば、ぜひ一度ご連絡ください。
▼ 階層別・スキル別eラーニング教材をお探しですか?
初期費用0円で・1ヶ月から利用できる演習が豊富な定額制受け放題eラーニング
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
ポータブルスキルの習得ならetudesをご利用ください
ポータブルスキルは、今後企業にとっても個人にとっても重要なスキルです。
eラーニングを活用してポータブルスキルを社員に習得させるなら、アルーが提供しているLMS「etudes」をご活用ください。
ここでは、etudesが選ばれる理由についてご紹介します。
管理はetudesで全て完結
etudesは、eラーニング受講、対面やオンライン研修の管理から受講までをシステムで一元管理できるeラーニングシステムです。eラーニング受講の緻密な学習管理や履歴の取得はもちろん、提出物管理やテストの実施など、幅広い研修の運営に必要な機能が標準装備されています。
eラーニングの受講管理だけでなく、集合研修を行う際の出欠確認や提出物管理もできますので、社員教育の全体を効率化させることが可能です。
多様なスキル別eラーニングの受講が可能
etudesでは、多様なポータブルスキルに特化した独自のeラーニングコンテンツを提供しています。専門家による質の高いコンテンツを通じて、社員のスキルアップを効果的にサポートします。また、より自社に合わせた教材を作成したいという場合には、教材作成の支援も行っています。
etudesでご用意しているeラーニング教材は、以下のページから確認していただけます。
eラーニング教材 一覧
まとめ
ポータブルスキルの概要や、鍛える方法などをご紹介いたしました。今後先行きの予測できない現代において、どの業種・どの職種でも活用することができるポータブルスキルは、企業においても社員個人においても重要なスキルです。
ポータブルスキルを社員に効果的に身につけてもらうには、外部研修を依頼したり、eラーニングなどを活用し、社内の学習に関する仕組みづくりをしていくことが大切です。アルーでは、eラーニングや研修を効率的に管理できるLMS「etudes」を提供しています。ポータブルスキルを社員に身につけさせたい、鍛えたいという人事担当者の方は、ぜひ一度ご相談ください。