株式会社NTTデータMSE
1,700名超に向けた鮮度の高い情報セキュリティ研修をeラーニングで毎月実現
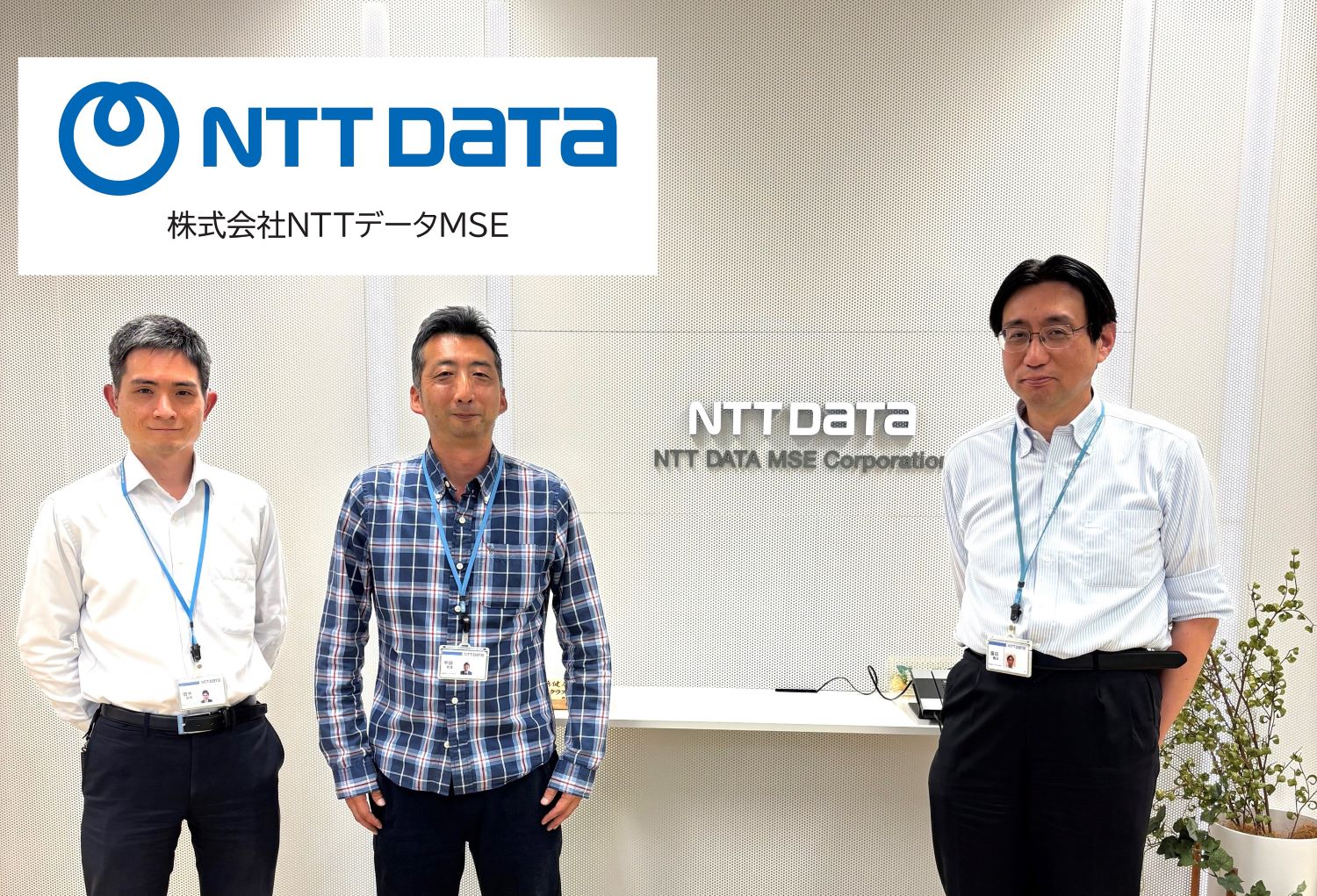
株式会社NTTデータMSE様
コーポレート本部 情報システム部 情報セキュリティ課
担当者名:
佐々木 祥昌様、三ケ尻 佳孝様、藤田 義治様、増井 徳秀様
<研修利用部門>
コーポレート本部 総務部 法務購買課
担当者名:
横山 泰明様、半田 克佳様、中村 大様、長谷川 さくら様
| 導入の背景 |
|
|---|---|
| 導入の決め手 |
|
| 導入後の効果 |
|

貴社の事業についてお教えください。
当社は1979年にパナソニックグループのソフトウェア会社として創業し、2008年に株式会社NTTデータが、2016年に株式会社デンソーが資本参加し、現在に至ります。「情報技術で新しい価値を生み出し、豊かな未来社会の創造に貢献する」という経営理念を掲げ、主に「IoT」「プロダクト」「オートモーティブ」の3つの事業領域において、人と社会をつなぐ新たなサービスを創出しています。
主力事業として車載機器向けソフトウェア開発を手掛ける他、大手通信事業者のサーバー・システム開発なども手掛けております。
貴社の人財育成制度の概要や、etudesご導入時の課題感をお教えください。
半田様:
当社は以前より人財育成には力を入れておりました。競争力の源泉であるエンジニアリング力を高めるため、全社研修担当部門が主幹となり、プロジェクト管理や開発スキル・組織管理などを階層・年代ごとに分けて、集合研修方式で定期的に実施していました。
一方で、情報セキュリティの対策・強化のための研修内容・機会が情報セキュリティに対する脅威が年々増している情勢に追い付けていませんでした。また、社内でのセキュリティに関連する課題に対して、その予防策の一環として「研修を通じた情報セキュリティの理解・浸透」が重要視されてきました。そのため、情報セキュリティ部門に講師の依頼が急増し、通常業務との両立が求められる状況となっていました。
全社研修担当部門に情報セキュリティ研修の対応が可能か相談したのですが、情報セキュリティ研修は内容が高度で、専門性も求められるため、対応が難しく、情報セキュリティ部門で研修を企画・運営する必要がありました。
eラーニングシステムの導入を進めた背景をお教えください。
藤田様:
当社でのeラーニングの利用は、親会社から受講を求められるeラーニングを年に1回受講する程度でしたが、より幅広く活用することが可能ではと考えていました。
特に、セキュリティ意識の向上に向けた情報セキュリティ教育を、今後より頻繁に、重点的に実施する必要があると考えていました。一方で、集合研修の頻度が増すと現場に対する負担が大きくなるため、効果的な研修を提供するために、eラーニングを活用する方針を決定しました。
いくつかのeラーニングシステムを比較検討されたかと思われますが、そのプロセスをお教えください。
半田様:
当社が重視していた要件は以下の3点です:
- 管理者/受講者ともに直感的に使えるシステム
- 管理者として、部署ごとの受講割当や進捗管理が行いやすいこと
- 研修教材としてパワーポイントファイルを活用できること
eラーニングシステムは市場に多く存在するため、要件に基づいて比較表を作成し、3社の製品に絞り込んでトライアルを実施し評価を行いました。
etudesを採用していただいたポイントをお教えください。
藤田様:
実際に運用することを想定してトライアルしたところ、etudesの進捗管理や受講の督促を手軽に行える点が特に高評価でした。また、当社は人事異動や組織変更が頻繁に行われるので、eラーニングシステム側にも迅速に反映する必要があります。この反映作業もetudesでは手間をかけずに行えました。
システムを運用する側だけでなく、研修を受ける方にとってもetudesは最も使いやすいシステムでしたので、採用に至りました。
etudes の運用担当者様のご感想をお教えください。
増井様:
<組織・ユーザー登録>
組織・ユーザーの登録は、XLSXフォーマットに記載してアップロードするだけなので、非常に簡単です。指定フォーマットに組織名、社員名、アカウント名など必要な情報のみを記載すれば、当社内の台帳から転記するだけでアップロード用のファイルが完成します。
<教材登録>
当社では資料スライドとテスト・アンケートを使用しています。etudesの教材登録手順を一通り確認しておけば、以降は困ることなく登録できています。
<受講者への教材割当>
部門単位や事業本部単位で一括受講者に教材を割り当てられることができるため、効率的に準備できます。現在は1,700名以上の方に向けて毎月eラーニングを実施していますが、人事異動情報の反映から教材登録・受講割当まで、etudesの一連の準備は2時間も要しません。
<受講案内>
情報セキュリティの受講対象者は1,700人規模になりますが、etudesに案内文を用意し、日時を設定するだけで一斉配信できるので、とても手軽に案内できています。
<進捗確認>
受講状況の確認権限を個別に付与することができるので、情報セキュリティ部門だけでなく、各事業本部の研修担当者にも確認権限を付与し、それぞれの部署が受講状況を管理しています。
etudesをご導入いただいた以降の、貴社の研修・教育の変化についてお教えください。
藤田様:
<教育の実施頻度の向上>
最新の社内事例やグループ会社事例に基づいたセキュリティ教育を毎月実施することができるようになり、全社的にセキュリティリテラシーが向上しました。お取引先様からも当社のセキュリティ教育の充実度についてご評価いただくこともあります。
セキュリティ教育だけではなく、他の社内教育での活用頻度が増え、現場からはetudesの研修配信頻度を調整して欲しいという声が上がるほど、社内教育に広く活用されています。
<受講状況のリアルタイム把握・分析>
etudesにより、受講状況をいつでもチェックできる状態になりました。
etudesを情報セキュリティ研修に導入した直後は、どの部門の受講率が高い/低いか、受講状況を役員に報告していました。当社経営層もセキュリティへの取り組みを積極的に推進しており、経営層のメッセージとしても情報セキュリティ研修の受講がアナウンスされるようになり、受講率が向上しました。
最近は100%受講完了している状態が数年続いており、役員会での報告も不要になるほど浸透しています。
また、集合研修では受講結果を分析するのが大変でしたが、etudesでは確認テストを分析することで、理解が浅い点を把握し、その対策を打つことができるようになったことも大きな改善です。
<全社展開>
etudesを導入した2018年の頃は情報セキュリティ教育だけで利用していましたが、コンプライアンスや環境に関する全社教育にもetudesが徐々に取り入れられ、現在ではetudesを全社標準のeラーニングシステムとして活用されています。
この背景には、全社研修担当部門にも集合研修を行うための講師の手配や会場の確保、出席者の調整・研修実績の取りまとめなどの業務負荷に課題があり、情報セキュリティ部門でeラーニングの活用が進んだことから、etudesの使用を希望する声が上がり、現在に至ります。
etudesの導入・定着にあたり、実施された工夫があればお教えください。
藤田様:
<未受講者への督促>
情報セキュリティ研修は全社員、100%の受講率を必須としていたので、受講督促を徹底しました。
導入直後から受講督促を強化し、役員会でも受講状況発信し、経営層から受講を促すことにより、社員の受講意識が上がり、早期受講が定着しました。現在では、受講開始から約1週間で約80%の社員が受講を完了するようになっています。
<短時間で受講できる教材の作成>
教材の受講にかかる時間を5~10分程度になるように研修テーマに対してポイントを絞って教材を作成しています。etudesでの受講は「スキマ時間を前提」にしているためです。
研修教材は、資料スライド、テスト、アンケートの構成であり、動画や音声は用いておりません。結果として、教材作成にかかる工数も抑えられています。受講者への操作説明は行いませんでしたが、全社員問題なくetudesを使いこなしています。
個別研修で利用している部門のご担当者様からみたetudesについてお教えください。
中村様:
コンプライアンス研修を全社員に対して実施する際、理解度をチェックするのに多大な時間と手間がかかっていました。etudesを利用することで、研修の実施も理解度チェックも効率化され、業務負荷を大きく削減することができました。
開発部門からも、「通常業務において必要な知識を毎年研修してくれることはとても良い取り組みだ」という評価をもらっています。集合研修ではどうしても時間を取られていましたが、etudesに置き換えることで、現場にとって業務の間のちょっとしたスキマ時間で研修を受けられると聞いています。
実際の運用においても、増井さんが作成されたetudes運用マニュアルが非常に分かりやすく、マニュアルに沿って作業を進めることで苦労はありませんでした。
全体として使い勝手の良いetudesですが、もし改善点を挙げるならば、テスト結果の分析が最終結果のみを対象としているため、「テストの点数の推移」も可視化・分析できれば、合格するまでの受験回数や低得点の項目が明確になり、弱いところを追加教育できるようになるので、さらなる教育の幅が広がると考えます。
長谷川様:
etudesは受講進捗状況をいつでもすぐに把握できるのが助かります。また、研修結果やアンケートに基づく分析の幅が格段に増え、その結果を、次回教材のブラッシュアップに活かしています。また、etudesの活用により社員教育準備等への時間が減り、その時間を他の業務に回すことができるようになりました。
今後実施していきたいことがあれば教えてください。
半田様:
最近はAI英会話アプリが話題ですが、etudesでもAIを活用して、希望する教育コンテンツがAIから提案されるような双方向型の研修ができるようになると、研修の幅が広がると考えます。
事例を読まれている方に向けて一言お願いいたします。

半田様:
当社では、etudesの運用やセキュリティ教材の作成を担当している社員の中に情報処理安全確保支援士の資格を取得している社員がいます。その方は聴覚にハンディキャップがありますが、情報セキュリティの専門家として豊富な知見をetudesを通じて全社員に展開しています。etudesは学びの場だけでなく、ハンディキャップを持った社員の活躍の場ともなっています。
藤田様:
当社内で作成した資料をそのまま使えるので、最新情報を用いた研修をスピーディに実施できます。etudesは直感的に操作できるため、システム管理者の負担が軽減され、研修のオンライン化をスムーズに実現できます。ぜひトライアルしてみてはいかがでしょうか。
関連記事
人材育成・eラーニングのどんなお悩み・疑問にも
私たちがお答えします。
お問い合わせください
お役立ち資料はこちらから
©Alue Co., Ltd. All Rights Reserved.


